2008年02月23日
要約筆記の限界
長い間ブログを更新できなかった。とにかくやたら忙しかった。毎年のことではあるけれど、年末から年度末まで、私が属している業界はなかなか忙しい。部下の退職、その後始末という仕事もあった。一段落ついたので、気を取り直して、またこのブログを書いていきたい。私の場合、どうしても一つのテーマで書くことが長くなってしまう。あまり長くならないようにして、書き継ぐようにできれば、とも思うのだが、なかなか、これが。
 さて、名古屋の要約筆記者が、要約筆記の取り組み方を変えてから丸2年が過ぎた。この2年間、私たちは、自分たちの取り組みに対して確かな手応えを感じてきた。自分たちが変えた要約筆記の取り組みは、目標を明確にして取り組むことだった。それは、「できないと諦めて、手近な目標に切り替える」ことではなかった。目標は、明確になった分だけ、高くなったとも言えるかも知れない。
さて、名古屋の要約筆記者が、要約筆記の取り組み方を変えてから丸2年が過ぎた。この2年間、私たちは、自分たちの取り組みに対して確かな手応えを感じてきた。自分たちが変えた要約筆記の取り組みは、目標を明確にして取り組むことだった。それは、「できないと諦めて、手近な目標に切り替える」ことではなかった。目標は、明確になった分だけ、高くなったとも言えるかも知れない。
要約筆記をやっていて、中途失聴者難聴者から、「聞こえなくても一緒に笑いたい」といわれてきた。その言葉に対して、「今はできないけど、少しでも近づけるようにがんばる」というだけですむなら、なんと安易な対応だろう。がんばるボランティア。それは見た目は美しい話かもしれない。その一方で、その場の情報から取り残され、当たり前の権利を保障されずにいる人がいる。自らの主体性を奪われて、口惜しい思いをしている人がいる。「がんばるボランティア」にとっても、それは放置しても良いことであるはずがない。
「その場の情報を保障する」−−文字にすればたった11文字のこのことを、きちんと実現しようとすれば、どれだけの修練と経験とチームプレーと環境整備とが必要になるだろう。目標を明確にしてその実現に向けて取り組んだとき、初めてそれが分かった。要約筆記を使う人が読み疲れない表記、すぐに利用できる表記、話し言葉の伝達効率を高める要約、その場ですぐ利用できる形で情報を手渡すこと、聴覚障害者と要約筆記の利用場面との関係に応じた支援の方法、情報伝達の環境の整備、それら一つ一つをカバーしていくことは簡単ではない。それらができて初めて、「その場の情報を保障する」というたった11文字の作業が現実的なものになる、聴覚障害者の人権を保障する最初の一歩になる。
確かに、保障すべき対象は広く大きい。もちろん、その場にいる聞こえ人と同じように感動したい、笑いたい。その道は、しかし最初の一歩を踏み出す以外にたどることができない道なのだ。
2年前を振り返ると、私たちは、大きな書き割り(舞台背景として描かれたもの)の前で要約筆記を演じていたような気がする。書き割りには、理想の要約筆記らしきものが描かれていた。そこには、話し言葉のすべてを伝えたい、という要約筆記者の願いも描かれてはいたが、書き割りに過ぎないから、その頂(いただき)に至る実際の道はなかった。もちろん目標としては正しい。正しいが役に立たない。書き割りとしては美しいから、観客は手を叩くが、現実の頂まで歩いていこうとする者には何の役にも立たない。
名古屋の要約筆記者は、その書き割りを捨てる、という決断をしたのだと思う。書き割りを捨てて、私達は実際に歩いていける丘の頂をまず目標とした、そして歩き始めた。すると、丘の頂でさえ、そこまで歩むことの困難さは、書き割りの前の、要するに平坦な舞台の上とは全く違うことが分かった。一つの丘まで登れば、次の、より高い頂が見えてきた。道はあるのかないのかもよく分からないが、歩くほかはない。私達は書き割りを捨てたのだから。
書き割りに描かれた高い頂、見事な稜線、それは美しいかもしれない。比べれば、現実の丘は貧相だし、たいした高さには見えないかもしれない。しかし、登ることのできない書き割りの山頂より、自分たちで、登録要約筆記者の会という志を同じくする仲間たちと登る丘の方が、重要ではないか。切実なものではないか。遙かな高みに登るふりをして過ごすより、本当の丘に登ろう。登ればまた次の目標が見えてくる。遠くまで行こう。行けばまた、次の道程が見えてくる。
要約筆記をやっていて、中途失聴者難聴者から、「聞こえなくても一緒に笑いたい」といわれてきた。その言葉に対して、「今はできないけど、少しでも近づけるようにがんばる」というだけですむなら、なんと安易な対応だろう。がんばるボランティア。それは見た目は美しい話かもしれない。その一方で、その場の情報から取り残され、当たり前の権利を保障されずにいる人がいる。自らの主体性を奪われて、口惜しい思いをしている人がいる。「がんばるボランティア」にとっても、それは放置しても良いことであるはずがない。
「その場の情報を保障する」−−文字にすればたった11文字のこのことを、きちんと実現しようとすれば、どれだけの修練と経験とチームプレーと環境整備とが必要になるだろう。目標を明確にしてその実現に向けて取り組んだとき、初めてそれが分かった。要約筆記を使う人が読み疲れない表記、すぐに利用できる表記、話し言葉の伝達効率を高める要約、その場ですぐ利用できる形で情報を手渡すこと、聴覚障害者と要約筆記の利用場面との関係に応じた支援の方法、情報伝達の環境の整備、それら一つ一つをカバーしていくことは簡単ではない。それらができて初めて、「その場の情報を保障する」というたった11文字の作業が現実的なものになる、聴覚障害者の人権を保障する最初の一歩になる。
確かに、保障すべき対象は広く大きい。もちろん、その場にいる聞こえ人と同じように感動したい、笑いたい。その道は、しかし最初の一歩を踏み出す以外にたどることができない道なのだ。
2年前を振り返ると、私たちは、大きな書き割り(舞台背景として描かれたもの)の前で要約筆記を演じていたような気がする。書き割りには、理想の要約筆記らしきものが描かれていた。そこには、話し言葉のすべてを伝えたい、という要約筆記者の願いも描かれてはいたが、書き割りに過ぎないから、その頂(いただき)に至る実際の道はなかった。もちろん目標としては正しい。正しいが役に立たない。書き割りとしては美しいから、観客は手を叩くが、現実の頂まで歩いていこうとする者には何の役にも立たない。
名古屋の要約筆記者は、その書き割りを捨てる、という決断をしたのだと思う。書き割りを捨てて、私達は実際に歩いていける丘の頂をまず目標とした、そして歩き始めた。すると、丘の頂でさえ、そこまで歩むことの困難さは、書き割りの前の、要するに平坦な舞台の上とは全く違うことが分かった。一つの丘まで登れば、次の、より高い頂が見えてきた。道はあるのかないのかもよく分からないが、歩くほかはない。私達は書き割りを捨てたのだから。
書き割りに描かれた高い頂、見事な稜線、それは美しいかもしれない。比べれば、現実の丘は貧相だし、たいした高さには見えないかもしれない。しかし、登ることのできない書き割りの山頂より、自分たちで、登録要約筆記者の会という志を同じくする仲間たちと登る丘の方が、重要ではないか。切実なものではないか。遙かな高みに登るふりをして過ごすより、本当の丘に登ろう。登ればまた次の目標が見えてくる。遠くまで行こう。行けばまた、次の道程が見えてくる。
2007年12月07日
情報量の格差と聞こえの保障
以前にこのブログで2度、聞こえの世界を二次元の図にして示したことがある。あえて三掲すると、
横軸:前もって準備できるものか、その場で対応するしかないものか
縦軸:話の内容が重要か、どんな風には話されたかといった表現が重要か
内容が重要
☆ ↑ ★ 会議
事 | 講演
前 ◆映画 プラネタリウム
に←————————┼——————→その場で発言
準 芝居 |
備 |
落語 ↓
表現が重要
(等幅フォントで表示してください)
となる。これは「聞こえの保障」の世界を一つの考え方で整理したものであって、整理の仕方はもっといろいろあるだろうと思う。最近、気づいた整理として、この縦軸を「情報量の格差」とする見方がある。つまりこうだ。
横軸:前もって準備できるものか、その場で対応するしかないものか
縦軸:コミュニケーションしている両者の間の情報量の格差
格差がない
↑ 会議
事 |
前 | 講演
に←————————┼——————→その場で発言
準 プラネタリウム
備 |
↓ 教育 医療
格差が大きい
(等幅フォントで表示してください)
会議などでは、互いの情報の格差は小さい。情報量に差があっても、それは構造的なものではなく、個人差に過ぎないことが多いだろうと思う。こうした場合には、通訳としての要約筆記は十分機能するだろう。
講演では、講師の持っている情報量は、講演のテーマに関しては、聴衆の持つ情報量よりかなり多いだろう。だからこそ、講演を聴きに来ているとも言える。こうした話し手と聞き手の間に情報量の格差がある場合、通訳を介した情報の伝達は、おそらく会議の場と異なる様相をもつと考えられる。
一例を挙げよう。情報量の多さは、時に、講演の内容に関連した原典からの引用といった形で現われることがある。例えば、松尾芭蕉についての講演会で芭蕉の俳句を引用する、山田洋次監督の映画について講演会で「寅さん」の台詞を引用する、ということはあり得る。原文のまま味わうことを、講演者が聴衆に求めるなら、その言葉については、レジュメに掲載する、板書するといった配慮をすることが求められる。これは聴覚障害者だけの話ではなく、一般の聴衆に対する場合にも言える話だ。情報を大量に持っている側が、少ない側に何らかの配慮をしないと、十分に情報は伝わらないからだ。それでも講演者が、耳からの情報だけに頼って、原文を引用して講演をすることがあり得る。そうした場合、引用される言葉をそのまま要約筆記で再現することは難しい。したがって、話し手と要約筆記通訳者との連携、事前の打ち合わせなどが、より重要になる。
更に、教育の現場や、医療の現場では、よりこの傾向は強まる。先生と生徒、医者と患者では、情報量の格差はとてつもなく大きい。こういう場合、単に要約筆記を付けるだけでは、教育保障にならない。先生の教えのスタイルは同じで、要約筆記通訳を利用すれば良い、ということにはならないのだ。情報量の格差が大きい場合には、単に通訳を挟むのではなく、その場所全体の聞こえの保障をデザインすることが必要になるのではないか。

対等な二者の間の情報の交換はコミュニケーションと呼ぶことができるが、彼我の立場や保有する情報量に圧倒的な差がある場合は、コミュニケーションではなく、「教育」であり、「医療」であり、あるいは「司法」(取り調べ、裁判)だということだ。したがって、単に通訳者を配置するだけでは、こうした場面では、足りないのだ。私たちのプラネタリウムでの経験でも、ある程度きちんと情報を伝えられていると感じることができるようになったのは、話し手である学芸員の方の協力的な姿勢がはっきり感じられるようになったあたりからだった。
自立支援法は、コミュニケーション支援を謳うが、ここでは、コミュニケーション支援だけではなく、もう少し大きなとらえ方、その場全体を見て聞こえない人にどのように情報を手渡していくかを考えなければならない、ということになるだろう。
横軸:前もって準備できるものか、その場で対応するしかないものか
縦軸:話の内容が重要か、どんな風には話されたかといった表現が重要か
内容が重要
☆ ↑ ★ 会議
事 | 講演
前 ◆映画 プラネタリウム
に←————————┼——————→その場で発言
準 芝居 |
備 |
落語 ↓
表現が重要
(等幅フォントで表示してください)
となる。これは「聞こえの保障」の世界を一つの考え方で整理したものであって、整理の仕方はもっといろいろあるだろうと思う。最近、気づいた整理として、この縦軸を「情報量の格差」とする見方がある。つまりこうだ。
横軸:前もって準備できるものか、その場で対応するしかないものか
縦軸:コミュニケーションしている両者の間の情報量の格差
格差がない
↑ 会議
事 |
前 | 講演
に←————————┼——————→その場で発言
準 プラネタリウム
備 |
↓ 教育 医療
格差が大きい
(等幅フォントで表示してください)
会議などでは、互いの情報の格差は小さい。情報量に差があっても、それは構造的なものではなく、個人差に過ぎないことが多いだろうと思う。こうした場合には、通訳としての要約筆記は十分機能するだろう。
講演では、講師の持っている情報量は、講演のテーマに関しては、聴衆の持つ情報量よりかなり多いだろう。だからこそ、講演を聴きに来ているとも言える。こうした話し手と聞き手の間に情報量の格差がある場合、通訳を介した情報の伝達は、おそらく会議の場と異なる様相をもつと考えられる。
一例を挙げよう。情報量の多さは、時に、講演の内容に関連した原典からの引用といった形で現われることがある。例えば、松尾芭蕉についての講演会で芭蕉の俳句を引用する、山田洋次監督の映画について講演会で「寅さん」の台詞を引用する、ということはあり得る。原文のまま味わうことを、講演者が聴衆に求めるなら、その言葉については、レジュメに掲載する、板書するといった配慮をすることが求められる。これは聴覚障害者だけの話ではなく、一般の聴衆に対する場合にも言える話だ。情報を大量に持っている側が、少ない側に何らかの配慮をしないと、十分に情報は伝わらないからだ。それでも講演者が、耳からの情報だけに頼って、原文を引用して講演をすることがあり得る。そうした場合、引用される言葉をそのまま要約筆記で再現することは難しい。したがって、話し手と要約筆記通訳者との連携、事前の打ち合わせなどが、より重要になる。
更に、教育の現場や、医療の現場では、よりこの傾向は強まる。先生と生徒、医者と患者では、情報量の格差はとてつもなく大きい。こういう場合、単に要約筆記を付けるだけでは、教育保障にならない。先生の教えのスタイルは同じで、要約筆記通訳を利用すれば良い、ということにはならないのだ。情報量の格差が大きい場合には、単に通訳を挟むのではなく、その場所全体の聞こえの保障をデザインすることが必要になるのではないか。
対等な二者の間の情報の交換はコミュニケーションと呼ぶことができるが、彼我の立場や保有する情報量に圧倒的な差がある場合は、コミュニケーションではなく、「教育」であり、「医療」であり、あるいは「司法」(取り調べ、裁判)だということだ。したがって、単に通訳者を配置するだけでは、こうした場面では、足りないのだ。私たちのプラネタリウムでの経験でも、ある程度きちんと情報を伝えられていると感じることができるようになったのは、話し手である学芸員の方の協力的な姿勢がはっきり感じられるようになったあたりからだった。
自立支援法は、コミュニケーション支援を謳うが、ここでは、コミュニケーション支援だけではなく、もう少し大きなとらえ方、その場全体を見て聞こえない人にどのように情報を手渡していくかを考えなければならない、ということになるだろう。
2007年11月26日
要約筆記を使って実現すること
以前に、中失難聴者が、すべての音声を回復したいと願うのは当然の要望だと書いた。音声認識の技術や人工内耳の更なる改良などが、そうした要望に応える日がいずれ来るだろう。とはいえ、それは今日ではないし、明日でもない。

要約筆記に関わっている中で、時に感じるのは、以前にもこのブログに書いたのだが、音声情報のすべてを回復したいという中失難聴者の要望の強さだ。先日も、ガイドツアーの時に要約筆記者が「鳥の声が聞こえる」「鴬が鳴いている」と書いてくれてとてもうれしかった、是非書いて欲しい、という話を聞いた。ガイドツアーの解説を筆記した上で、ということだろうけれど、鳥の声や小川のせせらぎといった音も含めて、音声情報を回復したいという要望は強い。
音声情報のすべてを回復したいという要望それ自体は、当たり前のことだと思うが、現状では、その要望を受けとめるのが「要約筆記者(要約筆記奉仕員)」だというところに様々な問題の出発点があるような気がする。音声情報のすべてを回復したいという要望を実現するには、音声認識や人工内耳などの更なる改良が必要だろう。そのためには、行政を動かし、研究開発に予算を付ける、という運動がなければならない。かつて全難聴の福祉大会で、音声認識技術のデモが行なわれたことがあった。すべての音声情報の回復を真剣に求めるなら、こうした運動は避けては通れないはずだ。聴覚障害者の「すべての音声情報を回復したい」という要望が、行政や研究者、さらには福祉関連企業に真剣に受けとめられるなら、IT技術の進歩と共に、事態は思っているより早く改善される可能性がある。
しかし、現実を見回すと、音声情報のすべてを回復したいという要望を一番真剣に受けとめているのは、聴覚障害者本人およびその家族を除けば、要約筆記者ではないだろうか。音声情報のすべてを回復したいという要望を受けとめた要約筆記者は、どうするだろうか。まず文字数を増やしたいと考えるだろう。手書き文字の場合、整った字で書ける限界は、個人差はあるものの60から70字/分だと思う。それを超えた文字数を求めれば、いきおい、文字は乱れ、書き殴りに近づく。それでもとうてい話しことばそれ自体をそっくり書き起こした場合の文字数には及ばない。話し手の言葉をできるだけそのまま書こうとすれば、一部は書けても、残りの大部分は書き落とす、ということの繰り返しになる。全体を書き落とすまいとして体言止めや助詞止めを増やせば、「ぶち切れの筆記で話し手の雰囲気が分からない」と言われる。かといって文末をそのまま書いていたのでは、どんどん遅れてしまう。「講師が冗談を言ったら、私たち聞こえないものも一緒に笑いたい」と言われれば、確かにその通りだと感じるから、冗談も書き取ろうとし、書いている間に本論は進み、後からシートを読み返すと、本論も冗談も区別ができず、まるで論旨の通らない筆記になっていることを知ってがっくりする。
音声情報のすべてを回復したいという要望それ自体は、間違っている訳ではないし、当然の要求だ。しかし、と私は思う。音声情報それ自体の価値とは何だろうか。いや、音声情報それ自体にも価値はあるのだが、私たちは音声情報を使って何かをしようとする、そういう側面が本当は高いのではないか。講師の講義を聴くとき、講師の声にうっとりしたいのではない。講義の内容を知り、学びたいのだ。人の話を聴き、自分の意見を言い、要はコミュニケーションしたいのだ。社会の情勢や緊急事態について知りたいのだ。確かに情報は、文字によっても伝えられる。新聞や週刊誌、多数の書籍、あるいは文字放送によっても情報は伝えられる。しかし音声情報によって最初に伝えられるという情報も少なくない。映像を得意とするテレビでさえ、音声を消してみれば、内容の過半は理解できない。
現代は情報化社会だと言われる。「情報化社会」とは、とりもなおさず、情報が価値を生む社会ということだ。情報それ自体が価値なのではない。その情報を使って価値を生み出す社会ということだ。要約筆記は、そのためであれば、機能させることができる。要約筆記を使って講義を聴く、内容を知る、会議に参加する、議論する、そういうことは要約筆記を使って可能だと私には思える。もちろん、参加を支える情報保障を実現することは簡単ではない。簡単ではないが、実現可能な目標だと私には思える。しかし、音声情報のすべてを回復することは、要約筆記の仕事ではない、と思う。音声情報のすべてを回復したいという要望を、要約筆記者は理解することができる。その理解に立って、聴覚障害者の切実な願いを、社会に実現していく運動に共に加わることもできる。その運動のための意志決定や判断を支える情報を提供する仕事、要するに情報保障の仕事を担うことは喜んでする。情報保障の制度をこの社会に根付かせ、使えるものとして維持することは、私たち要約筆記者の切なる願いだ。
しかし、音声情報のすべてを回復することは、要約筆記者が自らの筆記で実現することではない。音声情報の丸ごとの回復を、要約筆記それ自体の目標にしてはいけない。音声情報のすべてを回復したいという願いを、中失難聴者の身近にあって理解してきた要約筆記者の存在は、中失難聴者の運動にとって、とても大きかったと思う。ただ、その要望を理解することが、要約筆記にできることとできないことの区別を曖昧にした、ということは否めないように思う。
音声情報のすべてを回復したいという要望と、音声情報を利用して何かをすることの意義とを、切り分けていくという作業が、要約筆記にとって、今、最も求められているのではないだろうか。音声情報のすべてを回復したいという要望を正しく理解し、その要望が存在することは認めつつ、音声情報を使って何かをする、自分たちの福祉の運動を進めようとする、学ぼうとする、働こうとする、社会に進出していこうとする、そういう中失難聴者のために、音声情報を使える形で提供する要約筆記を実現する、と考えたい。端的に言えば、「音声情報それ自体を回復するのに要約筆記を使う」のではなく、「自らがやりたいことに取り組むために要約筆記を使う」ということだ。後者の立場を徹底すれば、要約筆記者が何をすべきかは自ずと見えてくると思う。

要約筆記に関わっている中で、時に感じるのは、以前にもこのブログに書いたのだが、音声情報のすべてを回復したいという中失難聴者の要望の強さだ。先日も、ガイドツアーの時に要約筆記者が「鳥の声が聞こえる」「鴬が鳴いている」と書いてくれてとてもうれしかった、是非書いて欲しい、という話を聞いた。ガイドツアーの解説を筆記した上で、ということだろうけれど、鳥の声や小川のせせらぎといった音も含めて、音声情報を回復したいという要望は強い。
音声情報のすべてを回復したいという要望それ自体は、当たり前のことだと思うが、現状では、その要望を受けとめるのが「要約筆記者(要約筆記奉仕員)」だというところに様々な問題の出発点があるような気がする。音声情報のすべてを回復したいという要望を実現するには、音声認識や人工内耳などの更なる改良が必要だろう。そのためには、行政を動かし、研究開発に予算を付ける、という運動がなければならない。かつて全難聴の福祉大会で、音声認識技術のデモが行なわれたことがあった。すべての音声情報の回復を真剣に求めるなら、こうした運動は避けては通れないはずだ。聴覚障害者の「すべての音声情報を回復したい」という要望が、行政や研究者、さらには福祉関連企業に真剣に受けとめられるなら、IT技術の進歩と共に、事態は思っているより早く改善される可能性がある。
しかし、現実を見回すと、音声情報のすべてを回復したいという要望を一番真剣に受けとめているのは、聴覚障害者本人およびその家族を除けば、要約筆記者ではないだろうか。音声情報のすべてを回復したいという要望を受けとめた要約筆記者は、どうするだろうか。まず文字数を増やしたいと考えるだろう。手書き文字の場合、整った字で書ける限界は、個人差はあるものの60から70字/分だと思う。それを超えた文字数を求めれば、いきおい、文字は乱れ、書き殴りに近づく。それでもとうてい話しことばそれ自体をそっくり書き起こした場合の文字数には及ばない。話し手の言葉をできるだけそのまま書こうとすれば、一部は書けても、残りの大部分は書き落とす、ということの繰り返しになる。全体を書き落とすまいとして体言止めや助詞止めを増やせば、「ぶち切れの筆記で話し手の雰囲気が分からない」と言われる。かといって文末をそのまま書いていたのでは、どんどん遅れてしまう。「講師が冗談を言ったら、私たち聞こえないものも一緒に笑いたい」と言われれば、確かにその通りだと感じるから、冗談も書き取ろうとし、書いている間に本論は進み、後からシートを読み返すと、本論も冗談も区別ができず、まるで論旨の通らない筆記になっていることを知ってがっくりする。
音声情報のすべてを回復したいという要望それ自体は、間違っている訳ではないし、当然の要求だ。しかし、と私は思う。音声情報それ自体の価値とは何だろうか。いや、音声情報それ自体にも価値はあるのだが、私たちは音声情報を使って何かをしようとする、そういう側面が本当は高いのではないか。講師の講義を聴くとき、講師の声にうっとりしたいのではない。講義の内容を知り、学びたいのだ。人の話を聴き、自分の意見を言い、要はコミュニケーションしたいのだ。社会の情勢や緊急事態について知りたいのだ。確かに情報は、文字によっても伝えられる。新聞や週刊誌、多数の書籍、あるいは文字放送によっても情報は伝えられる。しかし音声情報によって最初に伝えられるという情報も少なくない。映像を得意とするテレビでさえ、音声を消してみれば、内容の過半は理解できない。
現代は情報化社会だと言われる。「情報化社会」とは、とりもなおさず、情報が価値を生む社会ということだ。情報それ自体が価値なのではない。その情報を使って価値を生み出す社会ということだ。要約筆記は、そのためであれば、機能させることができる。要約筆記を使って講義を聴く、内容を知る、会議に参加する、議論する、そういうことは要約筆記を使って可能だと私には思える。もちろん、参加を支える情報保障を実現することは簡単ではない。簡単ではないが、実現可能な目標だと私には思える。しかし、音声情報のすべてを回復することは、要約筆記の仕事ではない、と思う。音声情報のすべてを回復したいという要望を、要約筆記者は理解することができる。その理解に立って、聴覚障害者の切実な願いを、社会に実現していく運動に共に加わることもできる。その運動のための意志決定や判断を支える情報を提供する仕事、要するに情報保障の仕事を担うことは喜んでする。情報保障の制度をこの社会に根付かせ、使えるものとして維持することは、私たち要約筆記者の切なる願いだ。
しかし、音声情報のすべてを回復することは、要約筆記者が自らの筆記で実現することではない。音声情報の丸ごとの回復を、要約筆記それ自体の目標にしてはいけない。音声情報のすべてを回復したいという願いを、中失難聴者の身近にあって理解してきた要約筆記者の存在は、中失難聴者の運動にとって、とても大きかったと思う。ただ、その要望を理解することが、要約筆記にできることとできないことの区別を曖昧にした、ということは否めないように思う。
音声情報のすべてを回復したいという要望と、音声情報を利用して何かをすることの意義とを、切り分けていくという作業が、要約筆記にとって、今、最も求められているのではないだろうか。音声情報のすべてを回復したいという要望を正しく理解し、その要望が存在することは認めつつ、音声情報を使って何かをする、自分たちの福祉の運動を進めようとする、学ぼうとする、働こうとする、社会に進出していこうとする、そういう中失難聴者のために、音声情報を使える形で提供する要約筆記を実現する、と考えたい。端的に言えば、「音声情報それ自体を回復するのに要約筆記を使う」のではなく、「自らがやりたいことに取り組むために要約筆記を使う」ということだ。後者の立場を徹底すれば、要約筆記者が何をすべきかは自ずと見えてくると思う。
2007年11月09日
要約筆記サークルと「派遣」
忙しくて、ブログの更新ができない。せめて週1回くらいは更新したいのだが。週末か、出張の列車の中でしか書く時間がない。今日は、研修のために東京を往復。以下は、新幹線の中で書いてきたもの。推敲が足りないところはご容赦願いたい。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以前このブログで、要約筆記サークルと登録要約筆記者の会との関係を巡って、名古屋では、サークルは要約筆記の派遣を引き受けないという整理をした、という話を書いた。これに対して直接という訳ではないが、要約筆記サークルが派遣に関わらないとすることが間違っている、という意見を最近になって聞いた。サークルが派遣に関わることを否定すると、要約筆記の依頼をする側の緊急避難的な依頼の窓口をなくすことになるから、という論旨のようだ。自立支援法ができて、基本的に市町村はコミュニケーション支援のための派遣を行なうことが義務づけられたといえる。したがって、聴覚障害者の人権や命に関わる場合には、原則派遣を受けることができる。まずは、この派遣の仕組みを整えることが第1だろう。
しかし、そうは言っても様々な理由から、制度外の派遣の依頼というものは、残る可能性がある。緊急避難的な依頼とは、どんな場合が考えられ、それについてはどう考えたら良いのだろうか。名古屋でのサークル活動の経過も振り返りつつ、この点を補足したい。

名古屋での要約筆記サークル「まごのて」の活動を振り返ると、1980年代においては、要約筆記者の派遣を含めて、その役割はきわめて大きかった。サークルの設立からの数年間は、要約筆記者の派遣に明け暮れたといっても良い。毎週のように、要約筆記者を探して派遣していたことを思い出す。公的な要約筆記奉仕員派遣制度は、名古屋の場合、厚生省(当時)のメニュー事業より一年早く、1984年に始まったが、サークルによる要約筆記者の派遣は、それ以降も続いた。その内訳を検討すると、派遣規定に乗らない派遣のほか(当初、宗教行事と政治活動は派遣対象外)、有料派遣の派遣費が高額すぎるため、というものが大部分だった。例えば、スクーリングの情報保障。派遣制度を運営する聴覚言語センターは、これは本来は学校側が保障すべきもの、というスタンスであり、有料派遣なら派遣するという。僅か3日間のスクーリングでも、午前午後、それぞれ3名の要約筆記者の派遣を受けると、のべ18名、派遣費用は数万円に達する。学校側が「負担しない」といえば、個人負担になってしまう。そこでサークルに支援の要請がくる、という構図だ。
「まごのて」でも、当初、こうした依頼は引き受けていたが、「安いから」という理由で利用されるのは、どうも腑に落ちないと感じてきた。そこで、当初は、依頼者には「まごのて」に入会してもらい、本来必要な情報保障は、学校側が行なうべきだ、それは校舎の階段にスロープを付けることと何ら変わりがなく、障害の有無にかかわらず、同じ授業を受けるために必要なのだ、ということを学校側に訴えていく運動を共にしよう、という整理をした。そして、要約筆記者をサークルから派遣し、交通費はサークルで負担、依頼者には無料(サークルの年会費を払って頂く)という対応をとってきた。
この時期、要約筆記奉仕員の公的な派遣制度はすでに存在しており、この派遣に乗らない要約筆記の依頼、いわゆる緊急避難的な依頼をサークルが受けている、という関係になっていた、といって良いだろう。なお、「緊急避難的依頼」というと、例えば夜間とか、「どうしても明日」といった依頼のイメージがあるが、こうした緊急性の高い依頼は、むしろ仕事として派遣を担っている公的な派遣制度の方が対応できる範囲は広い。サークルは地域のすべての要約筆記者を把握しているわけではないし、その窓口担当者といつでも連絡が取れるわけではない。公的な派遣制度の方が、時間的な意味での緊急性に対しては強いのではないかと思う。
さて、上記のやり方で、派遣制度に乗らない要約筆記の依頼をサークルで引き受けてきたが、ある時、次の疑問が生まれた。それは、依頼者から見たとき、派遣制度に乗るか乗らないかは、欲しい情報保障の質には無関係ではないか、という疑問だ。要約筆記による情報保障を欲している、ということは、一定以上の質の要約筆記を求めているということであり、「サークル派遣だから情報保障の質については目をつぶる」というのは、本末転倒ではないか。もちろんサークル派遣だから質が低いとは言い切れない。しかし、サークルには、要約筆記をきちんと学んでいない人もいる、講座の中途脱落者だっている、もう長いこと要約筆記の派遣に行っていない人もいる、登録要約筆記奉仕員研修会に出たことのない人もいる、それはサークルの性質上、当然にあり得ることだ。サークルは登録要約筆記者の会ではないのだし、その活動の目的ももっと広いのが普通だからだ。
他方、登録要約筆記者の会はどうか。そこにいるのは、少なくとも要約筆記奉仕員養成講座を受講した人だ。登録後の研修も、本来は受けているはずだ。もしここが、制度外の要約筆記の依頼を引き受けられるなら、それが一番良い。そういう考えを、2006年に結成された登録要約筆記者の会・なごやが、会として認識され、会員の賛同を得た。そして、登要会なごやの中に支援部を作り、公的な派遣制度に乗らないこうした要約筆記の依頼を、引き受けるようになった。要約筆記を依頼する側からみれば、公的な制度に乗った派遣にせよ、乗らない派遣にせよ、情報保障を受けたいという要求に変わりはない。緊急避難だから、情報保障の質がいつもと違ってかまわないという理屈はない。公的な派遣制度を担う要約筆記者(または要約筆記奉仕員)のメンバーが、制度外の派遣であっても情報保障を担うなら、こんなに望ましいことはない。また、登録要約筆記者の会が、そうした制度外の派遣の依頼の件数や内容を蓄積することにより、公的な派遣の範囲を広げる運動にも直接つなげていくことができる。サークルや個人的な対応によって制度外の派遣を処理していたのでは、行政からみれば、「それでまかなえるなら良いではないか」ということになりかねない。
要約筆記による情報保障の場を広げていく活動の初期において、要約筆記サークルが果たした役割は、おそらく日本中のどの地域でも巨大だった。要約筆記サークルができることで、その地域の中途失聴・難聴者の聞こえの保障を押し広げてきたことは間違いがない。しかし、いつまでもサークルの活動に頼ってはいけない、と私は思う。サークル活動の意義は、参加者の自己実現や社会にそれまでなかった支援の萌芽を育てる活動という点ではとても大きい。その活動の中で、障害者が必要とする支援の形が明確になれば、それを公的な領域に移していく、という視点を持たないとサークル活動は硬直化しやすい。サークル員の自己実現が、本来の目的ではないはずなのに、得てしてサークルの存続それ自体や、サークルがそれまでに担ってきた活動への固執、ということなりやすい。「緊急避難」などという言葉が、そうした固執を正当化するために用いられるとすれば、あまりに悲しい。サークルのリーダーは、サークルの役割をきちんと整理し、自分たちが切り開いてきた活動、支援というものが公的な制度に移し替えられていくように努力することが望まれる。自分たちが切り開いてきた活動が公的な枠組みに移されることは、当事者としては少し寂しいが、自分たちには新しい活動が待っている、と受け止めたい。
「聞こえの保障」という広い世界を見渡せば、聞こえが保障されていない場面はまだまだたくさんある。サークルが、取り組むべき先駆的な活動のフィールドはいくらもあるのだから。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以前このブログで、要約筆記サークルと登録要約筆記者の会との関係を巡って、名古屋では、サークルは要約筆記の派遣を引き受けないという整理をした、という話を書いた。これに対して直接という訳ではないが、要約筆記サークルが派遣に関わらないとすることが間違っている、という意見を最近になって聞いた。サークルが派遣に関わることを否定すると、要約筆記の依頼をする側の緊急避難的な依頼の窓口をなくすことになるから、という論旨のようだ。自立支援法ができて、基本的に市町村はコミュニケーション支援のための派遣を行なうことが義務づけられたといえる。したがって、聴覚障害者の人権や命に関わる場合には、原則派遣を受けることができる。まずは、この派遣の仕組みを整えることが第1だろう。
しかし、そうは言っても様々な理由から、制度外の派遣の依頼というものは、残る可能性がある。緊急避難的な依頼とは、どんな場合が考えられ、それについてはどう考えたら良いのだろうか。名古屋でのサークル活動の経過も振り返りつつ、この点を補足したい。

名古屋での要約筆記サークル「まごのて」の活動を振り返ると、1980年代においては、要約筆記者の派遣を含めて、その役割はきわめて大きかった。サークルの設立からの数年間は、要約筆記者の派遣に明け暮れたといっても良い。毎週のように、要約筆記者を探して派遣していたことを思い出す。公的な要約筆記奉仕員派遣制度は、名古屋の場合、厚生省(当時)のメニュー事業より一年早く、1984年に始まったが、サークルによる要約筆記者の派遣は、それ以降も続いた。その内訳を検討すると、派遣規定に乗らない派遣のほか(当初、宗教行事と政治活動は派遣対象外)、有料派遣の派遣費が高額すぎるため、というものが大部分だった。例えば、スクーリングの情報保障。派遣制度を運営する聴覚言語センターは、これは本来は学校側が保障すべきもの、というスタンスであり、有料派遣なら派遣するという。僅か3日間のスクーリングでも、午前午後、それぞれ3名の要約筆記者の派遣を受けると、のべ18名、派遣費用は数万円に達する。学校側が「負担しない」といえば、個人負担になってしまう。そこでサークルに支援の要請がくる、という構図だ。
「まごのて」でも、当初、こうした依頼は引き受けていたが、「安いから」という理由で利用されるのは、どうも腑に落ちないと感じてきた。そこで、当初は、依頼者には「まごのて」に入会してもらい、本来必要な情報保障は、学校側が行なうべきだ、それは校舎の階段にスロープを付けることと何ら変わりがなく、障害の有無にかかわらず、同じ授業を受けるために必要なのだ、ということを学校側に訴えていく運動を共にしよう、という整理をした。そして、要約筆記者をサークルから派遣し、交通費はサークルで負担、依頼者には無料(サークルの年会費を払って頂く)という対応をとってきた。
この時期、要約筆記奉仕員の公的な派遣制度はすでに存在しており、この派遣に乗らない要約筆記の依頼、いわゆる緊急避難的な依頼をサークルが受けている、という関係になっていた、といって良いだろう。なお、「緊急避難的依頼」というと、例えば夜間とか、「どうしても明日」といった依頼のイメージがあるが、こうした緊急性の高い依頼は、むしろ仕事として派遣を担っている公的な派遣制度の方が対応できる範囲は広い。サークルは地域のすべての要約筆記者を把握しているわけではないし、その窓口担当者といつでも連絡が取れるわけではない。公的な派遣制度の方が、時間的な意味での緊急性に対しては強いのではないかと思う。
さて、上記のやり方で、派遣制度に乗らない要約筆記の依頼をサークルで引き受けてきたが、ある時、次の疑問が生まれた。それは、依頼者から見たとき、派遣制度に乗るか乗らないかは、欲しい情報保障の質には無関係ではないか、という疑問だ。要約筆記による情報保障を欲している、ということは、一定以上の質の要約筆記を求めているということであり、「サークル派遣だから情報保障の質については目をつぶる」というのは、本末転倒ではないか。もちろんサークル派遣だから質が低いとは言い切れない。しかし、サークルには、要約筆記をきちんと学んでいない人もいる、講座の中途脱落者だっている、もう長いこと要約筆記の派遣に行っていない人もいる、登録要約筆記奉仕員研修会に出たことのない人もいる、それはサークルの性質上、当然にあり得ることだ。サークルは登録要約筆記者の会ではないのだし、その活動の目的ももっと広いのが普通だからだ。
他方、登録要約筆記者の会はどうか。そこにいるのは、少なくとも要約筆記奉仕員養成講座を受講した人だ。登録後の研修も、本来は受けているはずだ。もしここが、制度外の要約筆記の依頼を引き受けられるなら、それが一番良い。そういう考えを、2006年に結成された登録要約筆記者の会・なごやが、会として認識され、会員の賛同を得た。そして、登要会なごやの中に支援部を作り、公的な派遣制度に乗らないこうした要約筆記の依頼を、引き受けるようになった。要約筆記を依頼する側からみれば、公的な制度に乗った派遣にせよ、乗らない派遣にせよ、情報保障を受けたいという要求に変わりはない。緊急避難だから、情報保障の質がいつもと違ってかまわないという理屈はない。公的な派遣制度を担う要約筆記者(または要約筆記奉仕員)のメンバーが、制度外の派遣であっても情報保障を担うなら、こんなに望ましいことはない。また、登録要約筆記者の会が、そうした制度外の派遣の依頼の件数や内容を蓄積することにより、公的な派遣の範囲を広げる運動にも直接つなげていくことができる。サークルや個人的な対応によって制度外の派遣を処理していたのでは、行政からみれば、「それでまかなえるなら良いではないか」ということになりかねない。

要約筆記による情報保障の場を広げていく活動の初期において、要約筆記サークルが果たした役割は、おそらく日本中のどの地域でも巨大だった。要約筆記サークルができることで、その地域の中途失聴・難聴者の聞こえの保障を押し広げてきたことは間違いがない。しかし、いつまでもサークルの活動に頼ってはいけない、と私は思う。サークル活動の意義は、参加者の自己実現や社会にそれまでなかった支援の萌芽を育てる活動という点ではとても大きい。その活動の中で、障害者が必要とする支援の形が明確になれば、それを公的な領域に移していく、という視点を持たないとサークル活動は硬直化しやすい。サークル員の自己実現が、本来の目的ではないはずなのに、得てしてサークルの存続それ自体や、サークルがそれまでに担ってきた活動への固執、ということなりやすい。「緊急避難」などという言葉が、そうした固執を正当化するために用いられるとすれば、あまりに悲しい。サークルのリーダーは、サークルの役割をきちんと整理し、自分たちが切り開いてきた活動、支援というものが公的な制度に移し替えられていくように努力することが望まれる。自分たちが切り開いてきた活動が公的な枠組みに移されることは、当事者としては少し寂しいが、自分たちには新しい活動が待っている、と受け止めたい。
「聞こえの保障」という広い世界を見渡せば、聞こえが保障されていない場面はまだまだたくさんある。サークルが、取り組むべき先駆的な活動のフィールドはいくらもあるのだから。
2007年10月30日
「聞こえの保障」と支援者
全難聴が、2004年から、要約筆記に関する調査研究事業を開始して、さまざまな成果を上げていることはこのブログでも何度か触れた。その成果は、事業の報告書として発行され、全難聴から入手することができる。その中でも特筆すべきは、要約筆記者の到達目標と養成カリキュラムだが、この成果物は、なかなか公的な認知に至っていない。その最大の理由は、全難聴と全要研の意見の不一致にあると言っていい。これは厚生労働省の担当官が言明していたのだから間違いはない。
いま、細かく、どこに両団体の意見の不一致、いわゆる齟齬があるのか、説明することはしないが、全国的に見て、なかなか理解されないのが、「聞こえの保障」の広さと、その一部を担う「情報保障」の関係だ。更に言えば、その場の情報を保障する「通訳としての要約筆記」の専門性だろう。前者、つまり「聞こえの保障」と「情報保障」との関係は、前々回詳しく書いた。この問題を巡ってもう一つ、うまく認知ができていないのが、要約筆記者と要約筆記奉仕員の関係だろう。この点については、このブログでも何度か書いている。要約筆記奉仕員の必要性は誰しも認めるところだと思うが、要約筆記奉仕員が大切だから、要約筆記者の養成や認定をいつまでも放置したままにしておくという対応については、私は「間違っている」と考える。なぜ奉仕員事業という制度的にも不安定な事業にいつまでも拠ろうとするのだろうか。
制度の問題はさておき、一つ疑問に思うのは、要約筆記奉仕員にこだわる人は、通訳としての要約筆記以外の聞こえの保障の活動をどの程度した上で、奉仕員で良いといっているのだろうか、ということだ。中失難聴者に対する支援は、「通訳だけでない」とよく言われる。しかし、少なくとも必要とされている支援は、聴覚障害者に代わって電車の切符を買ったり、一緒に旅行に行ったり、飲んだりすることではないだろう。それは支援ではなく、付き合いであるとかお世話であるとか、名付けるとすれば友情であったり、親切であったりする、そういうものだろうと思う。もちろん聴覚障害者とつきあえば、聞こえない故の悩みを聞いたりするとはあるだろう。聴覚障害者の悩みを聞くといった支援も想定することはできる。しかしもしそうした支援をするのであれば、やはりカウンセリング技術の習得など、ある種の専門性が必要になる。単に気持ちがあれば支援できるというものではない。鬱病からの回復期にある患者に、励ますつもりで「もっとがんばって」と言い、病状を悪化させることだってある。「支援者である」というなら、それは「知らなかった」で許されることではないだろう。
中途失聴・難聴者を支援するというのであれば、「聞こえの保障」の領域での支援の必要性が見えないはずないと思う。私が属している名古屋の要約筆記サークル「要約筆記等研究連絡会・まごのて」は、そうした支援の必要性が見えたから、さまざまな支援活動に取り組んできた(サークルに中途失聴・難聴者がたくさん加わって共に活動を担っていたということも大きい)。その場の通訳としての要約筆記も、勿論サークル活動の初期においては中心的な課題として取り組んできたが、要約筆記奉仕員の公的な養成に引き続いて派遣が公的に始まると、サークルとしての中心的な活動を、映画の字幕制作と上映、プラネタリウムの字幕付き上演などに移してきた。そんな活動領域の遷移を予め見越した訳ではないのだろうが、「まごのて」は、発足時に、わざわざ「要約筆記等研究連絡会」として、「等」の文字をサークルの名称に含ませている。サークル活動の始まりの時点では、その場の情報保障だけが特別扱いではなかったことの証左と言えるかも知れない。
1978年12月の設立から今日までの「まごのて」の活動の中で、「聞こえの保障」という広い活動領域があることを実感してきたし、それぞれの活動にそれぞれの専門性があることを実感してきた。「通訳としての要約筆記」だけが抜きんでた専門性を持っている訳ではなく、その活動が一番高度な活動だという訳でもない。「聞こえの保障」を求める領域の一部が、専門性を持った明確な活動領域として取り出された、というだけのこと、そう理解してきた。
自慢する訳ではないが、「まごのて」は、おそらく全国の要約筆記サークルの中で、もっとも沢山の映画の字幕を制作してきたサークルだろう。手書きの字幕から数えれば、100本近い映画の字幕を作ってきている。また、「まごのて」は、もっとも沢山の種類の企画に字幕を付けてきたサークルだろうとも思っている。プラネタリウム(写真上)だけでなく、演劇や、電気文化科学館のシアターなど、さまざまな企画に字幕を付けてきた。ハーフミラーに映して投影される字幕、つまり鏡文字の字幕(写真下)さえ作った経験がある。遡れば、「聴覚障害者の文字放送-字幕放送シンポジウム」にリアルタイムで字幕を付けたのも、身体障害者スポーツ大会とその後夜祭にリアルタイム字幕を付けたのも、名古屋が最初だ。これらの企画は、「まごのて」が単独で実施した訳ではなく、全国の要約筆記者や高速日本語入力者との協働作業として実現したものだが、実現に向けて一定以上の役割を負っていたことも間違いがない。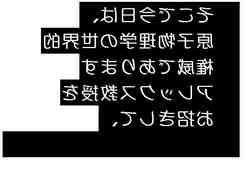
そうした活動の蓄積があったから、逆に、「通訳としての要約筆記」の専門性とその養成カリキュラムの重要性が分かるのかも知れない、と今は思う。「聞こえの保障」のこの広い領域の中で、「通訳としての要約筆記」について、ここまでしっかりした到達目標と養成カリキュラムを作ってこれたのだから、早くこの部分を専門的な活動として認め、社会福祉事業として定着させて欲しいと思わずにはいられない。奉仕員事業が残ることは何の問題もない。しかし、「要約筆記者の派遣事業」は、第2種社会福祉事業として、はっきりと位置づけられ、制度としてこの社会の中に定着されなければならない。どんなに親切なボランティアが身の回りに今いるとしても、あるいは10年後にもいるとしても、そのことと、社会的に利用可能な制度が存在する、ということは、全くその意味が異なる。
「通訳としての要約筆記」の専門性が認められ、その派遣が第2種社会福祉事業として定着する、自立支援法におけるコミュニケーション支援事業として市町村で派遣が必須事業として行なわれる、一日でも早くそうした状況が生まれれば、逆に、残された「聞こえの保障」の領域がもっともっと見えてくるはずだ。私たちにできることは沢山残されている。落語や漫才と言ったエンターテイメントや各種施設でのショー(例えば水族館のイルカショーなど)、あるいは学校教育といった領域で、今なお、沢山の中途失聴・難聴者は、取り残されたままだ。「通訳として要約筆記」を支える制度を「要約筆記者派遣事業」として早く定着させないと、「聞こえの保障」の残された領域は、いつまでも孤立した地域の取り組みとして残されてしまう。それで良いはずはない。
いま、細かく、どこに両団体の意見の不一致、いわゆる齟齬があるのか、説明することはしないが、全国的に見て、なかなか理解されないのが、「聞こえの保障」の広さと、その一部を担う「情報保障」の関係だ。更に言えば、その場の情報を保障する「通訳としての要約筆記」の専門性だろう。前者、つまり「聞こえの保障」と「情報保障」との関係は、前々回詳しく書いた。この問題を巡ってもう一つ、うまく認知ができていないのが、要約筆記者と要約筆記奉仕員の関係だろう。この点については、このブログでも何度か書いている。要約筆記奉仕員の必要性は誰しも認めるところだと思うが、要約筆記奉仕員が大切だから、要約筆記者の養成や認定をいつまでも放置したままにしておくという対応については、私は「間違っている」と考える。なぜ奉仕員事業という制度的にも不安定な事業にいつまでも拠ろうとするのだろうか。
制度の問題はさておき、一つ疑問に思うのは、要約筆記奉仕員にこだわる人は、通訳としての要約筆記以外の聞こえの保障の活動をどの程度した上で、奉仕員で良いといっているのだろうか、ということだ。中失難聴者に対する支援は、「通訳だけでない」とよく言われる。しかし、少なくとも必要とされている支援は、聴覚障害者に代わって電車の切符を買ったり、一緒に旅行に行ったり、飲んだりすることではないだろう。それは支援ではなく、付き合いであるとかお世話であるとか、名付けるとすれば友情であったり、親切であったりする、そういうものだろうと思う。もちろん聴覚障害者とつきあえば、聞こえない故の悩みを聞いたりするとはあるだろう。聴覚障害者の悩みを聞くといった支援も想定することはできる。しかしもしそうした支援をするのであれば、やはりカウンセリング技術の習得など、ある種の専門性が必要になる。単に気持ちがあれば支援できるというものではない。鬱病からの回復期にある患者に、励ますつもりで「もっとがんばって」と言い、病状を悪化させることだってある。「支援者である」というなら、それは「知らなかった」で許されることではないだろう。
中途失聴・難聴者を支援するというのであれば、「聞こえの保障」の領域での支援の必要性が見えないはずないと思う。私が属している名古屋の要約筆記サークル「要約筆記等研究連絡会・まごのて」は、そうした支援の必要性が見えたから、さまざまな支援活動に取り組んできた(サークルに中途失聴・難聴者がたくさん加わって共に活動を担っていたということも大きい)。その場の通訳としての要約筆記も、勿論サークル活動の初期においては中心的な課題として取り組んできたが、要約筆記奉仕員の公的な養成に引き続いて派遣が公的に始まると、サークルとしての中心的な活動を、映画の字幕制作と上映、プラネタリウムの字幕付き上演などに移してきた。そんな活動領域の遷移を予め見越した訳ではないのだろうが、「まごのて」は、発足時に、わざわざ「要約筆記等研究連絡会」として、「等」の文字をサークルの名称に含ませている。サークル活動の始まりの時点では、その場の情報保障だけが特別扱いではなかったことの証左と言えるかも知れない。

1978年12月の設立から今日までの「まごのて」の活動の中で、「聞こえの保障」という広い活動領域があることを実感してきたし、それぞれの活動にそれぞれの専門性があることを実感してきた。「通訳としての要約筆記」だけが抜きんでた専門性を持っている訳ではなく、その活動が一番高度な活動だという訳でもない。「聞こえの保障」を求める領域の一部が、専門性を持った明確な活動領域として取り出された、というだけのこと、そう理解してきた。
自慢する訳ではないが、「まごのて」は、おそらく全国の要約筆記サークルの中で、もっとも沢山の映画の字幕を制作してきたサークルだろう。手書きの字幕から数えれば、100本近い映画の字幕を作ってきている。また、「まごのて」は、もっとも沢山の種類の企画に字幕を付けてきたサークルだろうとも思っている。プラネタリウム(写真上)だけでなく、演劇や、電気文化科学館のシアターなど、さまざまな企画に字幕を付けてきた。ハーフミラーに映して投影される字幕、つまり鏡文字の字幕(写真下)さえ作った経験がある。遡れば、「聴覚障害者の文字放送-字幕放送シンポジウム」にリアルタイムで字幕を付けたのも、身体障害者スポーツ大会とその後夜祭にリアルタイム字幕を付けたのも、名古屋が最初だ。これらの企画は、「まごのて」が単独で実施した訳ではなく、全国の要約筆記者や高速日本語入力者との協働作業として実現したものだが、実現に向けて一定以上の役割を負っていたことも間違いがない。
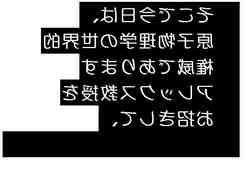
そうした活動の蓄積があったから、逆に、「通訳としての要約筆記」の専門性とその養成カリキュラムの重要性が分かるのかも知れない、と今は思う。「聞こえの保障」のこの広い領域の中で、「通訳としての要約筆記」について、ここまでしっかりした到達目標と養成カリキュラムを作ってこれたのだから、早くこの部分を専門的な活動として認め、社会福祉事業として定着させて欲しいと思わずにはいられない。奉仕員事業が残ることは何の問題もない。しかし、「要約筆記者の派遣事業」は、第2種社会福祉事業として、はっきりと位置づけられ、制度としてこの社会の中に定着されなければならない。どんなに親切なボランティアが身の回りに今いるとしても、あるいは10年後にもいるとしても、そのことと、社会的に利用可能な制度が存在する、ということは、全くその意味が異なる。
「通訳としての要約筆記」の専門性が認められ、その派遣が第2種社会福祉事業として定着する、自立支援法におけるコミュニケーション支援事業として市町村で派遣が必須事業として行なわれる、一日でも早くそうした状況が生まれれば、逆に、残された「聞こえの保障」の領域がもっともっと見えてくるはずだ。私たちにできることは沢山残されている。落語や漫才と言ったエンターテイメントや各種施設でのショー(例えば水族館のイルカショーなど)、あるいは学校教育といった領域で、今なお、沢山の中途失聴・難聴者は、取り残されたままだ。「通訳として要約筆記」を支える制度を「要約筆記者派遣事業」として早く定着させないと、「聞こえの保障」の残された領域は、いつまでも孤立した地域の取り組みとして残されてしまう。それで良いはずはない。
2007年10月29日
洋画の字幕と「要約」
名古屋で要約筆記者養成講座が始まっている(9月5日から)。その講座の中で、先日「日本語の特徴」について教えた。教えるために、日本語と要約筆記の関係をあれこれ検討していて、気づいたことをいくつか。
一つは、これは従来から言ってきたことだが、他人の話を伝達するためには、まずその話を理解することがどうしても必要になる、そして単に理解しただけではまだ伝達にはならず、それを要約筆記者が表現して、初めて伝達行為が完了する、という点に関連している。前者、つまり他人の話を理解するためには消極的知識が必要になる。これは理解するための知識。例えば漢字が読める、言葉の意味が分かる、という知識だ。これに対して後者、つまり理解したものを表現するためには積極的知識が必要になる。これは漢字を例にとれば、要する書けるということ、言葉の意味が分かるだけでなく使える語彙がたくさんあることだ。人の話を伝達するためには、この積極的知識がどうしても必要になる。知識を、「消極的知識」と「積極的知識」に分けるのは、ロシア語通訳者の米原万里さんの著作から私は学んだ。要約筆記者は、通常日本語を母語として育った人だから、消極的知識は十分に持っている。しかし、日本語を母語としている人でも、積極的知識は、意図的に学習しないとなかなか身につかない。これが、要約筆記者が日本語を学ばなければならない第1の理由だ、と講座では話した。
気づいたことの2番目は、要約筆記は第1言語(話しことば)から第2言語(書きことば)に向けて通訳されるということに関連している。その場の情報保障として用いられる要約筆記は通訳行為だと私は思っているが、一般の通訳、要するに異言語間の通訳の場合、通訳者は通常、通訳される対象となっている言語を母語としている人ではなく、通訳されてくる側の言語を母語としている人が行なう。翻訳の方がこの関係はわかりやすいから、翻訳を例にとるが、サリンジャーの英文(第1言語)を日本語(第2言語)に訳すのは日本人(例えば村上春樹氏)だし、源氏物語(日本語=第1言語)を英語(第2言語)に訳すのは、日本人ではなくアメリカ人、例えばサイデンステッカー氏だ。これは最初に挙げた「積極的知識」に関連している。つまり表現するためには積極的知識が豊富であることが要求されるから、通訳(翻訳)される二つの言語のうち、通訳(翻訳)されてくる側の言語(英→日翻訳なら日本語)を母語としている人が担当することになる訳だ。ところが、要約筆記の場合は、通訳されてくる側、つまり書きことばの方が話しことばより得意だという人は少ない。つまり要約筆記者は、通常の異言語間通訳と比べると不利な通訳を強いられている、ということになる。この点からも、要約筆記者を目指す人は、書きことばとしての日本語を学び、書きことばを強化しておかなければならない、ということになる、と話した。
気づいた3番目の内容は、通訳や翻訳においては、「要約」という概念は用いられていないのではないか、ということだ。私たち要約筆記者は、「要約」という言葉を当たり前のよう使う。しかしよく考えてみると、「速く、正しく、読みやすく」という要約筆記の三原則に「要約」という言葉は含まれていない。他方、異言語間の通訳を考えると、そこではどうも「要約」はされていないようなのだ。映画の字幕では、英語の話しことばから日本語の書きことばに向けて翻訳されるが、そこで「要約」をしているという人はいない。仮に話しことばから書きことばへという形で通訳が行なわれる場合に「要約」が必須だというのであれば、英語→日本語であっても、日本語→日本語であっても、そのこと自体は変わりはないはずだ。しかし、前者において、「要約」という意識は見られないし、受け取る我々(例えば、洋画を字幕で楽しむ視聴者)も、そこで行なわれていることが「要約」だとは感じていない、ということだ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
上記の3つの気づきのうち、3番目の話は、「日本語の特徴」とは直接は関係がなかったので、講座では全く触れなかったが、要約筆記という行為の本質を考える上では、かなり重要な示唆ではないかと感じた。そこで以下に少し敷衍してみたい。
日本語字幕の制作者として著名であった清水氏は、ある映画(確か「旅情」)の字幕にふれて、原語にあった「ステーキが食べたくても、ペパロニを出されたらペパロニを食べなさい」という意味の台詞の字幕について悩み、「スパゲティを出されたら、スパゲティを食べなさい」という台詞に訳したという話を書いている。当時(「旅情」の制作は1955年)の日本でのイタリア料理の普及状況を考えると「ペパロニ」では通じない、と考えたからだ。ここで起きていることは、見かけ上は「言い替え」と呼ばれるものだが、実質は、映画鑑賞者(つまり我々)に制作者の意図を伝えるための「通訳(翻訳)行為」だと言えるのではないか。言い換えだけではない。映画の原語に存在する台詞であって字幕化されていない言葉というものも少なくない。しかし、面白いことに、その省略を「要約」ととらえている字幕制作者はどうもいないようなのだ。
 整理すると、洋画の世界では、映画の中の台詞(話しことば)を字幕(書きことば)にしており、そこでは話しことばの逐語訳など行なわれていない。字幕制作者は、映画制作者の意図を映画鑑賞者に伝えるために、省略や言い換えなどを駆使しているが、そのことを「要約」とはとらえていない。字幕制作者は、その行為をおそらく「翻訳の一種」としてとらえているらしい、ということになる。
整理すると、洋画の世界では、映画の中の台詞(話しことば)を字幕(書きことば)にしており、そこでは話しことばの逐語訳など行なわれていない。字幕制作者は、映画制作者の意図を映画鑑賞者に伝えるために、省略や言い換えなどを駆使しているが、そのことを「要約」とはとらえていない。字幕制作者は、その行為をおそらく「翻訳の一種」としてとらえているらしい、ということになる。
映画字幕の翻訳の場合、目指されているものは、次のような行為だと思う。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本語以外の言語の話しことばにより表現された「内容+表現」
↓(時間をかけて作業可能)
「内容+表現」を、日本語の書きことばにより表現
(文字数の制約あり)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これに対して、要約筆記の場合、行なわれているのは(あるいは目指されているのは)、次の行為ではないか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本語の話しことばにより表現された「内容+表現」
↓(その場での作業)
「内容」を中心に、日本語の書きことばにより表現
(文字数の制約あり)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
という関係になる。映画の字幕では、字幕の制作者は、字幕の言語を母語とする人であるのに対して、要約筆記では、書き手は、広い意味では日本語を母語としているものの、書きことばを母語としている訳ではないことを考えると、要約筆記は、やはり相当困難な作業だといえるだろう。私たちは、「日本語の書きことば」を母語として使いこなせるように、相当の研鑽を積まなければならない。
一つは、これは従来から言ってきたことだが、他人の話を伝達するためには、まずその話を理解することがどうしても必要になる、そして単に理解しただけではまだ伝達にはならず、それを要約筆記者が表現して、初めて伝達行為が完了する、という点に関連している。前者、つまり他人の話を理解するためには消極的知識が必要になる。これは理解するための知識。例えば漢字が読める、言葉の意味が分かる、という知識だ。これに対して後者、つまり理解したものを表現するためには積極的知識が必要になる。これは漢字を例にとれば、要する書けるということ、言葉の意味が分かるだけでなく使える語彙がたくさんあることだ。人の話を伝達するためには、この積極的知識がどうしても必要になる。知識を、「消極的知識」と「積極的知識」に分けるのは、ロシア語通訳者の米原万里さんの著作から私は学んだ。要約筆記者は、通常日本語を母語として育った人だから、消極的知識は十分に持っている。しかし、日本語を母語としている人でも、積極的知識は、意図的に学習しないとなかなか身につかない。これが、要約筆記者が日本語を学ばなければならない第1の理由だ、と講座では話した。

気づいたことの2番目は、要約筆記は第1言語(話しことば)から第2言語(書きことば)に向けて通訳されるということに関連している。その場の情報保障として用いられる要約筆記は通訳行為だと私は思っているが、一般の通訳、要するに異言語間の通訳の場合、通訳者は通常、通訳される対象となっている言語を母語としている人ではなく、通訳されてくる側の言語を母語としている人が行なう。翻訳の方がこの関係はわかりやすいから、翻訳を例にとるが、サリンジャーの英文(第1言語)を日本語(第2言語)に訳すのは日本人(例えば村上春樹氏)だし、源氏物語(日本語=第1言語)を英語(第2言語)に訳すのは、日本人ではなくアメリカ人、例えばサイデンステッカー氏だ。これは最初に挙げた「積極的知識」に関連している。つまり表現するためには積極的知識が豊富であることが要求されるから、通訳(翻訳)される二つの言語のうち、通訳(翻訳)されてくる側の言語(英→日翻訳なら日本語)を母語としている人が担当することになる訳だ。ところが、要約筆記の場合は、通訳されてくる側、つまり書きことばの方が話しことばより得意だという人は少ない。つまり要約筆記者は、通常の異言語間通訳と比べると不利な通訳を強いられている、ということになる。この点からも、要約筆記者を目指す人は、書きことばとしての日本語を学び、書きことばを強化しておかなければならない、ということになる、と話した。
気づいた3番目の内容は、通訳や翻訳においては、「要約」という概念は用いられていないのではないか、ということだ。私たち要約筆記者は、「要約」という言葉を当たり前のよう使う。しかしよく考えてみると、「速く、正しく、読みやすく」という要約筆記の三原則に「要約」という言葉は含まれていない。他方、異言語間の通訳を考えると、そこではどうも「要約」はされていないようなのだ。映画の字幕では、英語の話しことばから日本語の書きことばに向けて翻訳されるが、そこで「要約」をしているという人はいない。仮に話しことばから書きことばへという形で通訳が行なわれる場合に「要約」が必須だというのであれば、英語→日本語であっても、日本語→日本語であっても、そのこと自体は変わりはないはずだ。しかし、前者において、「要約」という意識は見られないし、受け取る我々(例えば、洋画を字幕で楽しむ視聴者)も、そこで行なわれていることが「要約」だとは感じていない、ということだ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
上記の3つの気づきのうち、3番目の話は、「日本語の特徴」とは直接は関係がなかったので、講座では全く触れなかったが、要約筆記という行為の本質を考える上では、かなり重要な示唆ではないかと感じた。そこで以下に少し敷衍してみたい。
日本語字幕の制作者として著名であった清水氏は、ある映画(確か「旅情」)の字幕にふれて、原語にあった「ステーキが食べたくても、ペパロニを出されたらペパロニを食べなさい」という意味の台詞の字幕について悩み、「スパゲティを出されたら、スパゲティを食べなさい」という台詞に訳したという話を書いている。当時(「旅情」の制作は1955年)の日本でのイタリア料理の普及状況を考えると「ペパロニ」では通じない、と考えたからだ。ここで起きていることは、見かけ上は「言い替え」と呼ばれるものだが、実質は、映画鑑賞者(つまり我々)に制作者の意図を伝えるための「通訳(翻訳)行為」だと言えるのではないか。言い換えだけではない。映画の原語に存在する台詞であって字幕化されていない言葉というものも少なくない。しかし、面白いことに、その省略を「要約」ととらえている字幕制作者はどうもいないようなのだ。
 整理すると、洋画の世界では、映画の中の台詞(話しことば)を字幕(書きことば)にしており、そこでは話しことばの逐語訳など行なわれていない。字幕制作者は、映画制作者の意図を映画鑑賞者に伝えるために、省略や言い換えなどを駆使しているが、そのことを「要約」とはとらえていない。字幕制作者は、その行為をおそらく「翻訳の一種」としてとらえているらしい、ということになる。
整理すると、洋画の世界では、映画の中の台詞(話しことば)を字幕(書きことば)にしており、そこでは話しことばの逐語訳など行なわれていない。字幕制作者は、映画制作者の意図を映画鑑賞者に伝えるために、省略や言い換えなどを駆使しているが、そのことを「要約」とはとらえていない。字幕制作者は、その行為をおそらく「翻訳の一種」としてとらえているらしい、ということになる。映画字幕の翻訳の場合、目指されているものは、次のような行為だと思う。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本語以外の言語の話しことばにより表現された「内容+表現」
↓(時間をかけて作業可能)
「内容+表現」を、日本語の書きことばにより表現
(文字数の制約あり)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これに対して、要約筆記の場合、行なわれているのは(あるいは目指されているのは)、次の行為ではないか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本語の話しことばにより表現された「内容+表現」
↓(その場での作業)
「内容」を中心に、日本語の書きことばにより表現
(文字数の制約あり)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
という関係になる。映画の字幕では、字幕の制作者は、字幕の言語を母語とする人であるのに対して、要約筆記では、書き手は、広い意味では日本語を母語としているものの、書きことばを母語としている訳ではないことを考えると、要約筆記は、やはり相当困難な作業だといえるだろう。私たちは、「日本語の書きことば」を母語として使いこなせるように、相当の研鑽を積まなければならない。
2007年10月28日
「聞こえの保障」と「情報保障」
このブログでしばしば「聞こえの保障」という言い方をしてきた。これに対して、最近は「情報保障」ということが多い。「聞こえの保障」と「情報保障」とは何が違うのだろうか。このことを考えるためには、まず「情報」とは何か、ということを明確にする必要がある。
「情報」という言葉は便利なので気軽に使うが、よく考えるとなかなか定義することが難しい。人間が五感で感じるもの(知覚や感覚)であっても、広く「情報」と呼べないことはない。しかし、「情報保障」という場合の「情報」は、人の判断や行動の意志決定をするために役立つものを意味している。では、人の判断や行動の意志決定をするにめに役立つものがすべて「情報」かというと、必ずしもそうは言えない。「情報」とは、人の判断や行動の意志決定をするにめに役立つもののうち、その場でもたらされ、その場で必要になるものを意味していることが多い。時間が経てば、判断や行動の意志決定に役立たなくなることも多いからだ。台風で大雨が降り、河川が決壊しそうだというとき、自宅近くの川の水位や地域の降雨量などは重要な情報になる。避難するかどうかの判断の材料になるからだ。しかし、数日前のその川の水位や、あるいは今日の水位であっても遠く離れた河川の水位は、情報としてはあまり意味を持たない。この場での自らの判断や行動の意志決定のために使えないからだ。
 では時間に関係なく、いつでも役に立つというものはないのだろうか。もちろんある。通常そうしたものは「知識」と呼ばれるのではないだろうか。「この辺りは去年の台風でも水に浸かった」という知識があり、「今日の降雨量は、去年の台風並」という情報が入ってきて、「では、早めに避難所に避難しよう」という判断が生まれる。避難所の場所も、広域避難所として予め知らされている場合は「知識」として役立つし、町内会の組長さんが「今日は○○に避難して」と教えにきてくれれば、「貴重な情報をありがとう」ということになる。
では時間に関係なく、いつでも役に立つというものはないのだろうか。もちろんある。通常そうしたものは「知識」と呼ばれるのではないだろうか。「この辺りは去年の台風でも水に浸かった」という知識があり、「今日の降雨量は、去年の台風並」という情報が入ってきて、「では、早めに避難所に避難しよう」という判断が生まれる。避難所の場所も、広域避難所として予め知らされている場合は「知識」として役立つし、町内会の組長さんが「今日は○○に避難して」と教えにきてくれれば、「貴重な情報をありがとう」ということになる。
まとめると、「情報」とは、人の判断や行動の意志決定に役立つものであり、その場でもたらされ、その場で役立つもの、ということができる。
こう考えれば、「情報保障」とは、人が判断したり行動の意志決定をしたりするために、その場でもたらされるべきものを保障すること、を意味していることが分かる。ちなみに「保障」とは、本来あるべきものが守られている状態を指している。これが一度失われたものをつぐなうという意味の「補償」との差異だ(したがって、「安全保障条約」は安全な状態を守るためであり、「戦時補償」は戦時の損失を補うため、と理解できる)。
「聞こえの保障」は、聞こえることすべてを、本来あるように守りたいという意味になる。聞こえることすべてが「情報」として、人の判断や行動の意志決定のために用いられる訳ではない。私たちは、音楽も聴くし落語も楽しむ。それらは、私たちの聞こえの世界を形作ってはいるが、通常は「情報」としては扱われていない。したがって、聴覚障害者にとって聞こえの保障を求めるとは、「情報」も「情報でないもの」も等しく、つまり音声として聞こえているものを、聞こえる人が感じ、理解できるように、同じように感じ、理解したい、という要求だと言うことだ。その要求は、基本的人権の上に立つものであり、人として当然のものだということができる。しかし、現実には、すべてを直ちに保障することは難しい。技術的に難しいという場合もあるし、財政的に困難ということもある。テレビ放送の字幕を例にとれば、生中継などは、字幕の作成が困難として、2007年までの字幕化の対象とはなっていない。
いずれにせよ、この社会にあって、本来実現されるべきことであっても、優先順位を付けて取り組まざるを得ないことは多い。何十年も前に建造され、現在の耐震基準を満たさない建物であっても、直ちに使用中止とされたり取り壊されたりするわけではなく、一定の猶予期間のうちに耐震工事がなされるように義務づけられるにとどまっている。もっと言えば、「人命は地球より重い」と言いながら、交通事故で年間数千人が死亡するという事態は何十年も完全には解決されないままだ。そこには、現在の社会のあり方を前提として、優先順位を付けて取り組むという対応がある。社会的に「そうすべきだ」という強い合意ができないものは、後回しにされてしまう。
テレビ放送の完全字幕化などは、すでに技術的な問題は解決可能な状況にあるから、最後は予算の問題だと言って良いだろう。中途失聴・難聴者の運動が力強いものになって初めて、完全字幕化は、この社会での優先順位が上がることになる。
では、「聞こえの保障」の全体ではどう考えたらよいのだろうか。本来は、そのすべてが早期に保障されるべきものであるとしても、現実には優先順位を付けざるを得ない。とすれば、「聞こえの保障」の全領域のなかで、優先されるべきは「情報保障」の部分だろう。なぜなら、それは、聴覚障害者が、自ら判断し自らの行動の意志決定するために必要な情報を保障することだからだ。ここが支えられなければ、聴覚障害者は自ら判断し、自らの行動の意志決定を十全に行なうことが困難になる。いくらスポーツ中継や落語番組に字幕を付けたところで、聴覚障害者の判断や、その行動の意志決定を支えることはできない。逆に言えば、情報保障があれば、聴覚障害者は自らの行動の意志決定を行ない、それこそ、テレビ放送の完全字幕化の運動に立ち上がることもできるのだ。
これが、手話通訳や要約筆記が、第二種社会福祉事業として位置づけられている(社会福祉法第2条第3項第5号)理由であり、聴覚障害者のコミュニケーション支援事業が、市町村の必須事業とされている(障害者自立支援法第77条第1項第2号)理由だと私は思う。スポーツや文化の享受がないがしろにされて良い訳ではない。しかし、現在の日本の社会は、そこに優先順位を付け、「情報保障」を含む「コミュニケーション支援」については、規制と助成を通じて(社会福祉事業)、必ず実現すべきものとして(必須事業)、法律に規定したということができる。
では、「聞こえの保障」のうち、「情報保障」以外の部分、もっと広く言えば「コミュニケーション支援」以外の部分は、どのように扱われているのだろうか。この点は、また別にまとめることにしよう。
「情報」という言葉は便利なので気軽に使うが、よく考えるとなかなか定義することが難しい。人間が五感で感じるもの(知覚や感覚)であっても、広く「情報」と呼べないことはない。しかし、「情報保障」という場合の「情報」は、人の判断や行動の意志決定をするために役立つものを意味している。では、人の判断や行動の意志決定をするにめに役立つものがすべて「情報」かというと、必ずしもそうは言えない。「情報」とは、人の判断や行動の意志決定をするにめに役立つもののうち、その場でもたらされ、その場で必要になるものを意味していることが多い。時間が経てば、判断や行動の意志決定に役立たなくなることも多いからだ。台風で大雨が降り、河川が決壊しそうだというとき、自宅近くの川の水位や地域の降雨量などは重要な情報になる。避難するかどうかの判断の材料になるからだ。しかし、数日前のその川の水位や、あるいは今日の水位であっても遠く離れた河川の水位は、情報としてはあまり意味を持たない。この場での自らの判断や行動の意志決定のために使えないからだ。
 では時間に関係なく、いつでも役に立つというものはないのだろうか。もちろんある。通常そうしたものは「知識」と呼ばれるのではないだろうか。「この辺りは去年の台風でも水に浸かった」という知識があり、「今日の降雨量は、去年の台風並」という情報が入ってきて、「では、早めに避難所に避難しよう」という判断が生まれる。避難所の場所も、広域避難所として予め知らされている場合は「知識」として役立つし、町内会の組長さんが「今日は○○に避難して」と教えにきてくれれば、「貴重な情報をありがとう」ということになる。
では時間に関係なく、いつでも役に立つというものはないのだろうか。もちろんある。通常そうしたものは「知識」と呼ばれるのではないだろうか。「この辺りは去年の台風でも水に浸かった」という知識があり、「今日の降雨量は、去年の台風並」という情報が入ってきて、「では、早めに避難所に避難しよう」という判断が生まれる。避難所の場所も、広域避難所として予め知らされている場合は「知識」として役立つし、町内会の組長さんが「今日は○○に避難して」と教えにきてくれれば、「貴重な情報をありがとう」ということになる。まとめると、「情報」とは、人の判断や行動の意志決定に役立つものであり、その場でもたらされ、その場で役立つもの、ということができる。
こう考えれば、「情報保障」とは、人が判断したり行動の意志決定をしたりするために、その場でもたらされるべきものを保障すること、を意味していることが分かる。ちなみに「保障」とは、本来あるべきものが守られている状態を指している。これが一度失われたものをつぐなうという意味の「補償」との差異だ(したがって、「安全保障条約」は安全な状態を守るためであり、「戦時補償」は戦時の損失を補うため、と理解できる)。
「聞こえの保障」は、聞こえることすべてを、本来あるように守りたいという意味になる。聞こえることすべてが「情報」として、人の判断や行動の意志決定のために用いられる訳ではない。私たちは、音楽も聴くし落語も楽しむ。それらは、私たちの聞こえの世界を形作ってはいるが、通常は「情報」としては扱われていない。したがって、聴覚障害者にとって聞こえの保障を求めるとは、「情報」も「情報でないもの」も等しく、つまり音声として聞こえているものを、聞こえる人が感じ、理解できるように、同じように感じ、理解したい、という要求だと言うことだ。その要求は、基本的人権の上に立つものであり、人として当然のものだということができる。しかし、現実には、すべてを直ちに保障することは難しい。技術的に難しいという場合もあるし、財政的に困難ということもある。テレビ放送の字幕を例にとれば、生中継などは、字幕の作成が困難として、2007年までの字幕化の対象とはなっていない。
いずれにせよ、この社会にあって、本来実現されるべきことであっても、優先順位を付けて取り組まざるを得ないことは多い。何十年も前に建造され、現在の耐震基準を満たさない建物であっても、直ちに使用中止とされたり取り壊されたりするわけではなく、一定の猶予期間のうちに耐震工事がなされるように義務づけられるにとどまっている。もっと言えば、「人命は地球より重い」と言いながら、交通事故で年間数千人が死亡するという事態は何十年も完全には解決されないままだ。そこには、現在の社会のあり方を前提として、優先順位を付けて取り組むという対応がある。社会的に「そうすべきだ」という強い合意ができないものは、後回しにされてしまう。
テレビ放送の完全字幕化などは、すでに技術的な問題は解決可能な状況にあるから、最後は予算の問題だと言って良いだろう。中途失聴・難聴者の運動が力強いものになって初めて、完全字幕化は、この社会での優先順位が上がることになる。

では、「聞こえの保障」の全体ではどう考えたらよいのだろうか。本来は、そのすべてが早期に保障されるべきものであるとしても、現実には優先順位を付けざるを得ない。とすれば、「聞こえの保障」の全領域のなかで、優先されるべきは「情報保障」の部分だろう。なぜなら、それは、聴覚障害者が、自ら判断し自らの行動の意志決定するために必要な情報を保障することだからだ。ここが支えられなければ、聴覚障害者は自ら判断し、自らの行動の意志決定を十全に行なうことが困難になる。いくらスポーツ中継や落語番組に字幕を付けたところで、聴覚障害者の判断や、その行動の意志決定を支えることはできない。逆に言えば、情報保障があれば、聴覚障害者は自らの行動の意志決定を行ない、それこそ、テレビ放送の完全字幕化の運動に立ち上がることもできるのだ。
これが、手話通訳や要約筆記が、第二種社会福祉事業として位置づけられている(社会福祉法第2条第3項第5号)理由であり、聴覚障害者のコミュニケーション支援事業が、市町村の必須事業とされている(障害者自立支援法第77条第1項第2号)理由だと私は思う。スポーツや文化の享受がないがしろにされて良い訳ではない。しかし、現在の日本の社会は、そこに優先順位を付け、「情報保障」を含む「コミュニケーション支援」については、規制と助成を通じて(社会福祉事業)、必ず実現すべきものとして(必須事業)、法律に規定したということができる。
では、「聞こえの保障」のうち、「情報保障」以外の部分、もっと広く言えば「コミュニケーション支援」以外の部分は、どのように扱われているのだろうか。この点は、また別にまとめることにしよう。
2007年10月12日
通訳としての要約筆記−承前
 前回、要約筆記が通訳として機能させることを困難にした理由について、私の考えるところを書いた。では、なぜ要約筆記は通訳として機能しなければならないのか、そのためには何が必要なのか、について考えるところを書いてみたい。
前回、要約筆記が通訳として機能させることを困難にした理由について、私の考えるところを書いた。では、なぜ要約筆記は通訳として機能しなければならないのか、そのためには何が必要なのか、について考えるところを書いてみたい。前者については、すでに何度かこのブログに書いてきたが、要するに、要約筆記の目的をその場の情報保障に求めたからだ。9月20日付けのブログ「聞こえの保障と要約筆記」に表として示したものを再掲する。
横軸:前もって準備できるものか、その場で対応するしかないものか
縦軸:話の内容が重要か、どんな風には話されたかといった表現が重要か
内容が重要
☆ ↑ ★ 会議
事 | 講演
前 ◆映画 プラネタリウム
に←————————┼——————→その場で発言
準 芝居 |
備 |
落語 ↓
表現が重要
(等幅フォントで表示してください)
要約筆記が用いられる対象を、その場で話されるものであり、内容を重視するもの、と考えると、伝えるべきは内容であって、どのような話されたか、といった側面は後回しにせざる得ない。これも繰り返しになるが、聴覚障害者に対する情報保障のすべての領域に対して、私は「通訳として」の行為が必要になると言っているのではない。この表の中で言えば、「通訳としての要約筆記」が求められる領域は右上のわずかな部分だ。それ以外の領域、例えば映画の情報保障は、「通訳として」の行為ではない。また、内容よりもその表現を重視する領域(図の下方)でも、「通訳として」の行為だけでは対応できない。
しかし、この図の右上の領域については、逆に通訳としての要約筆記でなければ対応できないと考えている。というか、この領域で、聴覚障害者を本当の意味で支援するためになされている行為を、「通訳として要約筆記」と呼んでいるということなのだ。その場で話されている内容をその場の参加者に伝え、その場の参加者が、伝えられたものによって自らの考えをまとめ、判断し、参加できる、そのための情報保障の姿はどのようなものか、それが問われているのだ。
このとき、伝えるべきは、まずなにより内容だ。話題となっている事項に対する話し手の意見や、話し手の立場、つまり賛成か反対かが問われているのであって、大阪弁で意見を言ったか、あるいは賛成したか名古屋弁で反対したかが問われている訳ではない。次に、伝達行為の遅れには許容限度があることも大きい。要約筆記を使う聴覚障害者の、その場への参加を保障しようとすれば、遅れは、話し終わりから、10秒程度までしか許容されないことが多いだろう。これらの条件を満たそうとすれば、要約筆記者が行なう行為は、話し手の言葉ではなく、話し手が自らの話で伝えようと願った意図を、できる限り短い書きことばで、再現しようとする行為以外考えられない。にもかかわらず、要約筆記者が、話し手の使った言葉を大切にしようとする理由は何だろうか。畢竟、話し手の言葉は、話し手が自らの言葉で伝えようと願ったものをよく表わしているという理解ではないか。しかし、言葉を丸ごと再現できない限り、話し手の言葉それ自体が、話し手の伝えようとした意図を最もよく伝えることにならないのだ。
相手との関係を配慮して、例えば「あまりお引き留めして、後のご予定に差し支えては、と心配しておりますが。」と話したとき、その配慮の気持ちは、そこで用いられた言葉のすべてを、百歩ゆずっても大部分を再現しない限り、十全には再現されないし、伝えられない。書き取れる文字数の制約があるとき、話し手の言葉を使って、「お引き留めしては?」とか、「心配しておりますが?」とだけ要約筆記の画面に書かれたとすれば、話し手の意図は、伝わらない可能性が高い。まして「あまりお引き留めして」まで書いて後が書けなければ、なにも伝わらない。この例で言えば、「退席されては?」と書いた方が、話し手の意図は少なくとも伝わるはずだ。
その場の情報をその場で保障する、しかも内容を重視して伝える、という場面に限れば、要約筆記は、話し手の意図の伝達をその使命とすることは明らかではないだろうか。話し手の意図の伝達という目的、そのために、第一の言語形態(ここでは話しことば)によって語られた話し手の意図を、第二の言語形態(ここでは書きことば)によって伝えようとする、と考えれば、これは言語間の通訳が目指すものとなんら変わりはない。第一の言語形態に例えば英語を、第二の言語形態に例えば日本語を、それぞれ入れてみれば、これは明らかだろう。要約筆記は、この意味で、「通訳」と呼んで差し替えない。

では、第一の言語形態(ここでは話しことば)によって語られた話し手の意図を、第二の言語形態(ここでは書きことば)によって伝えること、結果的に、話し手の意図を伝達するという目的は、どのようにして達成されるのか。その問いに対する回答として、全難聴が2005年度の要約筆記に関する調査研究事業でまとめた「要約筆記者養成カリキュラム」とそのテキスト以上のものを、現時点では私は知らない。このカリキュラムの背後には、十分とは言えないが、それまで誰も取り組まなかった話しことばに対する実証的な検討がある。日本語の話しことばの運用に対して、その話され方がどのような意図に基づくのかという検討がある、同じ内容をより短く表現する場合の原則と例外を類型化しようとした取り組みがある。そこを見て取らなければ、この「要約筆記者養成カリキュラム」を理解したことにはならない。
2000年以降に、主に東京で、個人名をあげれば、東京の要約筆記者である三宅初穂氏によって行なわれたこの実証的な検討は、それまで誰も取り組まなかった類のものだ。おそらくは、話しことばの録音と、実際に書かれた要約筆記のシートを使ってなされたその考証は、日本語を普通に使っている人の気づきや思いつきのレベルを越えて、話しことばによる意図の伝達の仕組みに迫る初めての取り組みになった。
通訳としての要約筆記、つまり聞こえない人、聞こえにくい人の権利擁護のために役立つ要約筆記を実現しようとする私たちに求められているのは、この実証的な検討を押し進めることだ。三宅氏は、その検討の成果を「話しことばの要約」(発行:杉並要約筆記者の会「さくらんぽ」)など何冊かの本にまとめて上梓されているが、実証的な検討それ自体はほとんど明らかにしていない。しかし、実際に行なわれたその実証的検討の内容と意味を知り、その道を、要約筆記者を養成しようとする者が通らないと、「通訳としての要約筆記」は、本当の意味では成熟しないのではないか。三宅氏の取り組みの成果だけを学ぶのではなく、その取り組みの課程を学ばなければ、本当のところで、話し手の意図を、手書きの書きことばによって通訳する道は、拓けない。
2007年10月09日
要約筆記と通訳行為(補遺)
 先に、要約筆記が通訳として認められにくかった理由として3つの観点から整理した。その2番目、3番目として、
先に、要約筆記が通訳として認められにくかった理由として3つの観点から整理した。その2番目、3番目として、[2]要約筆記を利用する人の要望
[3]話しことばと書きことばの速さのギャップの前で
の二つを挙げた。しかし私はここで、誰かの責任を問おうとしている訳ではない。中途失聴者・難聴者が、音から隔てられていると感じ、要約筆記に対して、言葉それ自体の回復を求めたとしても、それは自然なことだと思う。その要望それ自体か間違っているとは全く思わない。ろう者は手話を母語にしている。私たち、日本語を母語として育った者が日本語を誤らないように、手話を母語として育った人は手話を誤らない。しかし、中途失聴者・難聴者は、要約筆記を母語として育つ訳ではない。ここに、手話と要約筆記の決定的な違いがある。
中途失聴者・難聴者の要望は、要望として存在するし、それはいつか、技術の発展と支援の形の充実によって、満たされる日が来ると私は思う。現在のパソコン要約筆記では、まだその要求に十分に応えることはできないが、いずれその要望に応える機械か活動が生まれるだろう。しかし、手書きの要約筆記は、その要望に応えられるものではない。どんなにがんばっても、話すように書くことはできない。それだけのことだ。
しかし、中途失聴者・難聴者の聞こえの保障を求める要求のうち、ある部分は、手書き要約筆記以外にこれを支援する方法はなかったのだ。そして現在でも、手書き要約筆記が対応しなければならない領域はまだまだ広い。その要望に応える方法は、隔てられた音をそのまま回復することではなく、話し手の意図したもの、話し手が伝えようと願った内容(概念)を、書き取ることができる文字数の中で、明快に伝えていく、そういう方法だったということだと思う。中途失聴者・難聴者の要望を聞き届け、しかし現実に可能な支援を構築していく、そういうことが試みられたのだ。良い悪いの問題ではなく、その支援の形が、なかなか「通訳行為」として整理できなかった、ということに過ぎない。
また、要約筆記奉仕員養成講座で養成された要約筆記奉仕員が、話しことばと格闘して、話しことばの性質を十分には検討できなかったとしても、それは要約筆記奉仕員の責任ではない。もともと奉仕員に、そうした責務が課されていた訳では全くなかったのだから。
むしろ課題は、要約筆記奉仕員という形にいつまでもとどまって、話しことばと本気で格闘する人を育てなかった点にある。要約筆記の専門性、というのであれば、ただ単に、50時間程度の講座を受けたことをもって「専門性」と呼ぶのではない。訓練しないかぎりできないことをする、というのが専門性の最初の意味のはずだ。そしてその次に、通訳行為への意図的な取り組みがくる。全難聴の要約筆記に関する調査研究事業が、「要約筆記者」の到達目標として掲げた「「通訳」という行為に対する自覚的な理解をしていること」とは、まさにこのことを伝えようとしている。
要約筆記奉仕員が育つ中、先を見通して、話しことばと格闘する人を育てる必要があったと言えるだろう。
繰り返しになるが、犯人捜しは全く本意ではない。要約筆記の短からぬ歴史の中で、できたこと、できなかったことを整理しておきたい。整理して、見通しを作ることで、次のステップに進める。そう思っている。
2007年10月09日
要約筆記と通訳行為−その2
このブログを始めて間もない頃に、「どうして要約筆記は通訳として認められにくいのか」という問いを立ててそのままにしている(8月26日付け、「要約筆記の現状」参照)。今日は少しこの点を整理してみたい。要約筆記が通訳として認められにくかったのは、大きく分けて三つの理由があったと私は考えている。
一つは、要約筆記が日本語間のやりとりを媒介しているために、通訳としての側面が見にくかったということ。もう一つは、要約筆記を利用する中途失聴・難聴者の要望。そして最後が、要約筆記者自身が、話し言葉の速さにどうしても目を奪われて、他人の話を媒介するという作業の本質に対して十分に迫れなかったこと、だ。順を追って説明したい。
[1]日本語間のやりとりである、ということ
まず要約筆記が日本語間のやりとりを媒介するから、という点だが、これは異言語間の通訳と比較するとわかりやすい。もともと異言語間通訳は、いわゆる逐語訳ではつとまらない。このことは異なる二つ以上の言語を少し扱った経験のある人ならすぐに了解される。分からない単語のすべてについて辞書を引いて、単語の意味が分かったとしても、文を正しく訳すことはできない。まして達意の言葉にして通訳することはできない。
例として、言語学者の鈴木孝夫氏がその著書「日本語と外国語」(岩波新書)で挙げたフランス語における「オレンジ色の封筒」という表現を取り上げてみよう。鈴木孝夫氏は、この表現に接して、あるとき、フランス人にとって「オレンジ」という色は、我々日本人にとっての「茶色」を含むのだと気づく。つまり「オレンジ色の封筒」とは「茶封筒」のことだったのだ。日本では虹は七色だが、世界中で虹を七色と数えている国は少ない。ヨーロッパでは、「リンゴのような頬の女の子」とは青白い病弱なイメージを喚起する。したがって、異言語間の翻訳や通訳は、言葉に沿って訳す逐語訳ではなく、話し手が言おうとしたことを理解して伝えるという作業が絶対に必要になる。言葉のままに訳したのでは、意味が伝わらず、場合によっては誤解や行き違いを生じるからだ。実際、「オレンジ色の車でお迎えに参ります」と言われた鈴木孝夫氏は、いつまでたったも現われないオレンジ色の車を、茶色の車の傍らで待ち続けたという。異言語間の通訳は、こうした文化的な読み替え、言い替えの上に成り立っている。「言い替え」と書いたが、それは「替える」のではなく、本当は、話し手が伝えたいと願ったことを、通訳者が理解し、理解したものを、聞き手(読み手)が使う言語の世界で表現する行為なのだ。
これに対して、要約筆記は同じ日本語間で話を媒介するものだ。話し手が、頬の紅い健康的な女の子をイメージして「リンゴのような頬の女の子」と言えば、聞き手にも同じイメージが喚起されると期待することができる。話し手が「オレンジ色の車」と言えば、確かにオレンジ色の車がお迎えに来るだろう。であれば、話し手の言葉をそのまま使えばよい、話し手の言葉と異なる言葉を使うべきではない、と要約筆記者が考えたとして不思議はない。話し手の言葉をできるだけ生かして話を伝えるとは、この間の消息を伝えるものだ。

[2]要約筆記を利用する人の要望
第二の理由、要約筆記を利用する中途失聴者・難聴者の要望はどうだろうか。これには更に二つの側面がある、と私は考えている。一つは、音から隔てられた中途失聴者・難聴者の心情、もう一つは、話し手としての中途失聴者・難聴者の心情、だ。中途失聴者は、人生の途中で聴力を失ったから、それまでは音声が聞こえていたことになる。したがって、音は最初から失われていた訳ではなく、音はあり、そこから隔てられていると感じているのではないだろうか。難聴者の受けとめ方も似ているのでないだろうか。1975年に岩波新書の一冊として発行された「音から隔てられて」(編集・入谷仙介、林瓢介)という書籍の書名は、この中途失聴者・難聴者の心情を端的に表わしていると、と私は感じてきた。中途失聴者・難聴者にとって、隔てられている音声を回復したい、という要望は当然のことだ。補聴器が、隔てられている音声を、音声のまま少しでも取り戻そうとする装置である考えられるとすれば、音声を文字化することで、これを取り戻そうという利用の仕方を要約筆記に求めるということがあったのではないか。聞き取りにくい言葉を時に補聴器が明確にするように、聞き取りにくい言葉を要約筆記のスクリーンに求めて明確にしようする、そういう利用の立場から言えば、話し手の使った言葉はそのままスクリーンに現われて欲しいはずだ。
もう一つ、話し手もまた中途失聴者・難聴者だったとはどういうことだろうか。要約筆記が当初使われた場面は、中途失聴者・難聴者の会合、例えば典型的には、中途失聴者難聴者協会の例会などだった。そうすると要約筆記の利用者は、同時に、要約筆記における話し手でもあったのだ。したがって、要約筆記の現場では、話し手も中途失聴・難聴者、それを見ているのも中途失聴・難聴者だった。話し手からすれば、自分の使った言葉が使われない、というのは不満になる。話し手には、その言葉を使って物事を伝えたいという気持ちがある。その気持ちがあるからその言葉が選択されたのだといえる。例えば、相手に対して十分な気遣いをして、「あまりお引き留めして、後のご予定に差し支えては、と心配しておりますが」と話したとき、要約筆記の画面に例えば「退席されては?」と書かれると、「自分はこんな言い方はしなかった、こんな直接的な言い方では失礼に当たらないか」と感じてしまう、ということは、話すことに対して意識的な話し手であればあるほど、起きるはずだ。自分の話したままに書いて欲しい、と話し手である中途失聴者・難聴者が感じ、そのように要望したとしても不思議ではない。
要約筆記者は、聴覚障害者、とりわけ中途失聴者・難聴者を支援しようという気持ちで活動をしている立場だから、中途失聴者・難聴者の要望に耳を傾け、その要望を尊重したいと考えるだろう。「音から隔てられて」いる気持ちに立って、音声それ自体を取り戻したいという要望、話し手である中途失聴・難聴者の、言葉に託した自らの心情をそのまま伝えるために、託した言葉自体を書いて欲しいという要望、要約筆記者は、それらに応えようとしてきたのだと言える。それが、話し手の話の内容を伝える、つまり通訳としての要約筆記ではなく、話し手の言葉を生かした要約筆記という目標を掲げる理由につながったのではなかったか。
[3]話しことばと書きことばの速さのギャップの前で
最後に、話しことばと書きことばの速さの違いという問題がある。一般に話しことばの速度は1分間に300字程度とされ、他方、手書きの速度は1分間にせいぜ60字程度だとされる。書き取ることができる文字数は話しことばの約20パーセントでしかない。私たち要約筆記者はその速度のあまりに大きな違いの前で、どのようにこの差異を乗り越えるかという点について、十分な検討ができなかったように私は思う。もちろん、全要研集会では毎年のように「技術」の分科会がもたれ、その主要なテーマは「要約」の技術であり、研究誌にも要約をめぐるたくさんの論考が掲載されてきた。はやく1994年発行の研究誌第5号、翌年の第6号には、ユニークな要約の技術的な考察が掲載されている。しかし、それらの研究が、その後の要約筆記における要約の研究の発展には、うまく結びつかなかった。それはなぜか。
思うに、私たち要約筆記者は、話しことばと十分な格闘をしなかったのだ。要約筆記者、当時の要約筆記奉仕員は、一般の人がボランティアである奉仕員の養成講座を受けることで養成される。当然、日本語の研究者ではないから、「要約」について関心をもっても、なかなか実証的な検討をするところまで至らない。いわゆる素人の思いつきの域をでることが難しいのだ。
日本語の普通の使い手として、日本語に関してものを言うことは難しくない。例えば、「○○しないこともない。」という二重否定文に出会えば、これを「○○する。」と言い得る、ということは気づくだろう。しかし、日本語の中で二重否定文が使われる理由、その場合のあるうべき類型の発見、肯定文に変形できる原則と例外の整理、といったところまで、普通の要約筆記者にできる訳ではない。日本語の専門家によるこうした仕事は、確かに行なわれてはいるが、私たちが毎日使っている日本語の豊かな表現と比べると、その研究はきわめて限定的なものだ。日本語は、他の多くの言語同様、文法(言語の運用規則)の決定や語彙の選定が先にあって、それに基づいて運用されている言語ではない。私たち日本人が、おそらく何千年も昔から自然に使い始め、様々な外来の文化と共に受け入れた言葉を消化しつつ、日本の社会のあり方を反映させて、分化と統合を繰り返しながら作り上げられてきた言語、すなわち自然言語の一つだ。したがって、ある言葉の運用が正しいかどうか、同じ意味を伝える別の、より短い表現はどうのようなものか、という問いに直ちに答えることは、日本語の研究者にとってもきわめて難しい。研究されている領域は決して広くはない。しかも、そのほとんどは、書きことばを対象としており、話しことばに対して行なわれた研究というものはほとんどない。
このため、他人に伝達することを目的として話しことばを書きとる際、日本語のどのような性質が利用できるのか、という点について、要約筆記者はほとんど徒手空拳だったと言わざるを得ない。自然言語としての日本語は、そのとき巨大な壁となって、要約筆記者の前にあった。

以上の3つが、要約筆記を通訳として機能させることに対して、これを阻害する要因として働いてきたのではないか、私は、現時点ではそんなふうに整理している。もちろんこれ以外の理由もあったかも知れない。が、主な理由は、この3つではなかっただろうか。
一つは、要約筆記が日本語間のやりとりを媒介しているために、通訳としての側面が見にくかったということ。もう一つは、要約筆記を利用する中途失聴・難聴者の要望。そして最後が、要約筆記者自身が、話し言葉の速さにどうしても目を奪われて、他人の話を媒介するという作業の本質に対して十分に迫れなかったこと、だ。順を追って説明したい。
[1]日本語間のやりとりである、ということ
まず要約筆記が日本語間のやりとりを媒介するから、という点だが、これは異言語間の通訳と比較するとわかりやすい。もともと異言語間通訳は、いわゆる逐語訳ではつとまらない。このことは異なる二つ以上の言語を少し扱った経験のある人ならすぐに了解される。分からない単語のすべてについて辞書を引いて、単語の意味が分かったとしても、文を正しく訳すことはできない。まして達意の言葉にして通訳することはできない。
例として、言語学者の鈴木孝夫氏がその著書「日本語と外国語」(岩波新書)で挙げたフランス語における「オレンジ色の封筒」という表現を取り上げてみよう。鈴木孝夫氏は、この表現に接して、あるとき、フランス人にとって「オレンジ」という色は、我々日本人にとっての「茶色」を含むのだと気づく。つまり「オレンジ色の封筒」とは「茶封筒」のことだったのだ。日本では虹は七色だが、世界中で虹を七色と数えている国は少ない。ヨーロッパでは、「リンゴのような頬の女の子」とは青白い病弱なイメージを喚起する。したがって、異言語間の翻訳や通訳は、言葉に沿って訳す逐語訳ではなく、話し手が言おうとしたことを理解して伝えるという作業が絶対に必要になる。言葉のままに訳したのでは、意味が伝わらず、場合によっては誤解や行き違いを生じるからだ。実際、「オレンジ色の車でお迎えに参ります」と言われた鈴木孝夫氏は、いつまでたったも現われないオレンジ色の車を、茶色の車の傍らで待ち続けたという。異言語間の通訳は、こうした文化的な読み替え、言い替えの上に成り立っている。「言い替え」と書いたが、それは「替える」のではなく、本当は、話し手が伝えたいと願ったことを、通訳者が理解し、理解したものを、聞き手(読み手)が使う言語の世界で表現する行為なのだ。
これに対して、要約筆記は同じ日本語間で話を媒介するものだ。話し手が、頬の紅い健康的な女の子をイメージして「リンゴのような頬の女の子」と言えば、聞き手にも同じイメージが喚起されると期待することができる。話し手が「オレンジ色の車」と言えば、確かにオレンジ色の車がお迎えに来るだろう。であれば、話し手の言葉をそのまま使えばよい、話し手の言葉と異なる言葉を使うべきではない、と要約筆記者が考えたとして不思議はない。話し手の言葉をできるだけ生かして話を伝えるとは、この間の消息を伝えるものだ。

[2]要約筆記を利用する人の要望
第二の理由、要約筆記を利用する中途失聴者・難聴者の要望はどうだろうか。これには更に二つの側面がある、と私は考えている。一つは、音から隔てられた中途失聴者・難聴者の心情、もう一つは、話し手としての中途失聴者・難聴者の心情、だ。中途失聴者は、人生の途中で聴力を失ったから、それまでは音声が聞こえていたことになる。したがって、音は最初から失われていた訳ではなく、音はあり、そこから隔てられていると感じているのではないだろうか。難聴者の受けとめ方も似ているのでないだろうか。1975年に岩波新書の一冊として発行された「音から隔てられて」(編集・入谷仙介、林瓢介)という書籍の書名は、この中途失聴者・難聴者の心情を端的に表わしていると、と私は感じてきた。中途失聴者・難聴者にとって、隔てられている音声を回復したい、という要望は当然のことだ。補聴器が、隔てられている音声を、音声のまま少しでも取り戻そうとする装置である考えられるとすれば、音声を文字化することで、これを取り戻そうという利用の仕方を要約筆記に求めるということがあったのではないか。聞き取りにくい言葉を時に補聴器が明確にするように、聞き取りにくい言葉を要約筆記のスクリーンに求めて明確にしようする、そういう利用の立場から言えば、話し手の使った言葉はそのままスクリーンに現われて欲しいはずだ。
もう一つ、話し手もまた中途失聴者・難聴者だったとはどういうことだろうか。要約筆記が当初使われた場面は、中途失聴者・難聴者の会合、例えば典型的には、中途失聴者難聴者協会の例会などだった。そうすると要約筆記の利用者は、同時に、要約筆記における話し手でもあったのだ。したがって、要約筆記の現場では、話し手も中途失聴・難聴者、それを見ているのも中途失聴・難聴者だった。話し手からすれば、自分の使った言葉が使われない、というのは不満になる。話し手には、その言葉を使って物事を伝えたいという気持ちがある。その気持ちがあるからその言葉が選択されたのだといえる。例えば、相手に対して十分な気遣いをして、「あまりお引き留めして、後のご予定に差し支えては、と心配しておりますが」と話したとき、要約筆記の画面に例えば「退席されては?」と書かれると、「自分はこんな言い方はしなかった、こんな直接的な言い方では失礼に当たらないか」と感じてしまう、ということは、話すことに対して意識的な話し手であればあるほど、起きるはずだ。自分の話したままに書いて欲しい、と話し手である中途失聴者・難聴者が感じ、そのように要望したとしても不思議ではない。
要約筆記者は、聴覚障害者、とりわけ中途失聴者・難聴者を支援しようという気持ちで活動をしている立場だから、中途失聴者・難聴者の要望に耳を傾け、その要望を尊重したいと考えるだろう。「音から隔てられて」いる気持ちに立って、音声それ自体を取り戻したいという要望、話し手である中途失聴・難聴者の、言葉に託した自らの心情をそのまま伝えるために、託した言葉自体を書いて欲しいという要望、要約筆記者は、それらに応えようとしてきたのだと言える。それが、話し手の話の内容を伝える、つまり通訳としての要約筆記ではなく、話し手の言葉を生かした要約筆記という目標を掲げる理由につながったのではなかったか。
[3]話しことばと書きことばの速さのギャップの前で
最後に、話しことばと書きことばの速さの違いという問題がある。一般に話しことばの速度は1分間に300字程度とされ、他方、手書きの速度は1分間にせいぜ60字程度だとされる。書き取ることができる文字数は話しことばの約20パーセントでしかない。私たち要約筆記者はその速度のあまりに大きな違いの前で、どのようにこの差異を乗り越えるかという点について、十分な検討ができなかったように私は思う。もちろん、全要研集会では毎年のように「技術」の分科会がもたれ、その主要なテーマは「要約」の技術であり、研究誌にも要約をめぐるたくさんの論考が掲載されてきた。はやく1994年発行の研究誌第5号、翌年の第6号には、ユニークな要約の技術的な考察が掲載されている。しかし、それらの研究が、その後の要約筆記における要約の研究の発展には、うまく結びつかなかった。それはなぜか。
思うに、私たち要約筆記者は、話しことばと十分な格闘をしなかったのだ。要約筆記者、当時の要約筆記奉仕員は、一般の人がボランティアである奉仕員の養成講座を受けることで養成される。当然、日本語の研究者ではないから、「要約」について関心をもっても、なかなか実証的な検討をするところまで至らない。いわゆる素人の思いつきの域をでることが難しいのだ。
日本語の普通の使い手として、日本語に関してものを言うことは難しくない。例えば、「○○しないこともない。」という二重否定文に出会えば、これを「○○する。」と言い得る、ということは気づくだろう。しかし、日本語の中で二重否定文が使われる理由、その場合のあるうべき類型の発見、肯定文に変形できる原則と例外の整理、といったところまで、普通の要約筆記者にできる訳ではない。日本語の専門家によるこうした仕事は、確かに行なわれてはいるが、私たちが毎日使っている日本語の豊かな表現と比べると、その研究はきわめて限定的なものだ。日本語は、他の多くの言語同様、文法(言語の運用規則)の決定や語彙の選定が先にあって、それに基づいて運用されている言語ではない。私たち日本人が、おそらく何千年も昔から自然に使い始め、様々な外来の文化と共に受け入れた言葉を消化しつつ、日本の社会のあり方を反映させて、分化と統合を繰り返しながら作り上げられてきた言語、すなわち自然言語の一つだ。したがって、ある言葉の運用が正しいかどうか、同じ意味を伝える別の、より短い表現はどうのようなものか、という問いに直ちに答えることは、日本語の研究者にとってもきわめて難しい。研究されている領域は決して広くはない。しかも、そのほとんどは、書きことばを対象としており、話しことばに対して行なわれた研究というものはほとんどない。
このため、他人に伝達することを目的として話しことばを書きとる際、日本語のどのような性質が利用できるのか、という点について、要約筆記者はほとんど徒手空拳だったと言わざるを得ない。自然言語としての日本語は、そのとき巨大な壁となって、要約筆記者の前にあった。

以上の3つが、要約筆記を通訳として機能させることに対して、これを阻害する要因として働いてきたのではないか、私は、現時点ではそんなふうに整理している。もちろんこれ以外の理由もあったかも知れない。が、主な理由は、この3つではなかっただろうか。
2007年09月29日
「要約筆記」と通訳行為−その1
私は現在、「要約筆記」は通訳行為であると考えているが、「要約筆記」という言葉は重層的で、混乱がある。通訳行為でないものも「要約筆記」と呼ばれることが実際あるのだ。少しこの点を整理してみたい。混乱の第一の理由は、従来、要約筆記に関わってきた人は、自らの行為の全てを「要約筆記」と呼んでいたというところにある。前に書いた「聞こえの保障」が求められている広い領域の中で、「通訳としての要約筆記」がカバーしている部分以外、例えば映画の字幕制作なども、要約筆記者の活動としてとらえられていた。
この時期は、「要約筆記者の活動」=「聞こえの保障の全運動」と考えられており、「聞こえの保障の全運動」の一部に「通訳行為としての要約筆記」(その場の情報保障を支える要約筆記)というものがあった。そしてよく見ると、「要約筆記者」というのは、「要約筆記奉仕員」のことだった。
何度も書くが2004年から始まった全難聴の要約筆記に関する調査研究事業は、このうちの「通訳行為としての要約筆記」に強く着目した。その場の情報保障を支援することが、聴覚障害者の権利擁護、つまり聴覚障害者がその場の情報を得て、その場に参加し、自ら判断し、行動するという聴覚障害者の当然の権利を、直接擁護するものになると考えたのだ。折からの社会福祉基礎構造改革の中、公的な支援により実現すべきものはなにか、と考えたとき、障害者の権利擁護のためにまず必要になるものを明確にしようとしたのだと言っても良い。
2004年度の事業を担った委員会の中では、「要約筆記は必ず通訳としての側面を持つ」という意見と、「通訳行為でない要約筆記もあり得る」という意見とが、対立した。前者の立場は、要約筆記を手話と対比することにより明確になる。手話は、自らがろう者とコミュニケーションするために身につける、という側面と、他人のコミュニケーションを支援するために用いる、という側面とがあることは、容易に理解される。ところが要約筆記は、自らが中途失聴・難聴者とコミュニケーションするために用いるという側面は想定しにくい。本人が書くことは、要約筆記ではなく、通常「筆談」と呼ばれる。つまり、手話と違って、要約筆記は、必ず通訳行為を含む、ととらえたのだ。
他方、音声情報から隔てられている人に、その聞こえを保障しようとすれば、その場の情報保障としての要約筆記だけでは不十分なのだ、という点から要約筆記を見たのが後者の視点だ。字幕制作、字幕付き上映、テープ起こし、筆録などの取り組みは、では誰がするのか。それらの活動を支えていたのは、伝統的に、要約筆記者だったはずだ。とすれば、要約筆記者が行なってきた、現に行なっている活動を「要約筆記」ととらえられるはずだ、要約筆記には必ずしも通訳行為を想定する必要はない、ととらえたのだ。
両方の議論を一つに止揚する方法が一つだけあったと私は考えている。それは、前者の立場を「要約筆記通訳」と命名することだった。そしてそのような通訳行為をする人を「要約筆記通訳者」と呼ぶ。従来からの聞こえの保障の広い活動領域全体は、要約筆記ととらえる、ということだ。こうすれば、二つの議論は共に生かされる。
しかし、全難聴の2005年の事業では、最終的には、「要約筆記通訳」「要約筆記通訳者」という名称は採用されなかった。途中まで、「要約筆記通訳」という言葉は使われていたのだ。しかし、最終的な報告書として出された「通訳としての要約筆記者への展望」では、そこで提案されたカリキュラム案を含めて「要約筆記通訳」という名称は使われていない。
その最大の理由は、同じ時期に法案が国会に上程され、紆余曲折を経て、2005年10月に成立した障害者自立支援法の地域支援事業の要綱の中で、「要約筆記者」という呼称を用いていたという点にあった。法律とその実施要綱で使われている言葉を使うべきではないか、おそらく、要約筆記通訳者と要約筆記奉仕員との関係は、様々に議論される。であれば、最初から自立支援法に合わせて「要約筆記者」とした方が良いのではないか。確かにそれは一理も二里もある考え方だった。
こうして、報告書とカリキュラムの記載は「要約筆記」「要約筆記者」に統一された。このため、本来なら「要約筆記通訳は通訳行為である」(当たり前)とされるべきところが、「要約筆記は通訳行為である」と読まれてしまうことになった。おそれていた混乱はやはり生じた、というべきかも知れない。
そして更にこの障害者自立支援法の地域支援事業の要綱の記載が、別の混乱を招くことになった。この点は、次回。
この時期は、「要約筆記者の活動」=「聞こえの保障の全運動」と考えられており、「聞こえの保障の全運動」の一部に「通訳行為としての要約筆記」(その場の情報保障を支える要約筆記)というものがあった。そしてよく見ると、「要約筆記者」というのは、「要約筆記奉仕員」のことだった。
何度も書くが2004年から始まった全難聴の要約筆記に関する調査研究事業は、このうちの「通訳行為としての要約筆記」に強く着目した。その場の情報保障を支援することが、聴覚障害者の権利擁護、つまり聴覚障害者がその場の情報を得て、その場に参加し、自ら判断し、行動するという聴覚障害者の当然の権利を、直接擁護するものになると考えたのだ。折からの社会福祉基礎構造改革の中、公的な支援により実現すべきものはなにか、と考えたとき、障害者の権利擁護のためにまず必要になるものを明確にしようとしたのだと言っても良い。
2004年度の事業を担った委員会の中では、「要約筆記は必ず通訳としての側面を持つ」という意見と、「通訳行為でない要約筆記もあり得る」という意見とが、対立した。前者の立場は、要約筆記を手話と対比することにより明確になる。手話は、自らがろう者とコミュニケーションするために身につける、という側面と、他人のコミュニケーションを支援するために用いる、という側面とがあることは、容易に理解される。ところが要約筆記は、自らが中途失聴・難聴者とコミュニケーションするために用いるという側面は想定しにくい。本人が書くことは、要約筆記ではなく、通常「筆談」と呼ばれる。つまり、手話と違って、要約筆記は、必ず通訳行為を含む、ととらえたのだ。

他方、音声情報から隔てられている人に、その聞こえを保障しようとすれば、その場の情報保障としての要約筆記だけでは不十分なのだ、という点から要約筆記を見たのが後者の視点だ。字幕制作、字幕付き上映、テープ起こし、筆録などの取り組みは、では誰がするのか。それらの活動を支えていたのは、伝統的に、要約筆記者だったはずだ。とすれば、要約筆記者が行なってきた、現に行なっている活動を「要約筆記」ととらえられるはずだ、要約筆記には必ずしも通訳行為を想定する必要はない、ととらえたのだ。
両方の議論を一つに止揚する方法が一つだけあったと私は考えている。それは、前者の立場を「要約筆記通訳」と命名することだった。そしてそのような通訳行為をする人を「要約筆記通訳者」と呼ぶ。従来からの聞こえの保障の広い活動領域全体は、要約筆記ととらえる、ということだ。こうすれば、二つの議論は共に生かされる。
しかし、全難聴の2005年の事業では、最終的には、「要約筆記通訳」「要約筆記通訳者」という名称は採用されなかった。途中まで、「要約筆記通訳」という言葉は使われていたのだ。しかし、最終的な報告書として出された「通訳としての要約筆記者への展望」では、そこで提案されたカリキュラム案を含めて「要約筆記通訳」という名称は使われていない。
その最大の理由は、同じ時期に法案が国会に上程され、紆余曲折を経て、2005年10月に成立した障害者自立支援法の地域支援事業の要綱の中で、「要約筆記者」という呼称を用いていたという点にあった。法律とその実施要綱で使われている言葉を使うべきではないか、おそらく、要約筆記通訳者と要約筆記奉仕員との関係は、様々に議論される。であれば、最初から自立支援法に合わせて「要約筆記者」とした方が良いのではないか。確かにそれは一理も二里もある考え方だった。
こうして、報告書とカリキュラムの記載は「要約筆記」「要約筆記者」に統一された。このため、本来なら「要約筆記通訳は通訳行為である」(当たり前)とされるべきところが、「要約筆記は通訳行為である」と読まれてしまうことになった。おそれていた混乱はやはり生じた、というべきかも知れない。
そして更にこの障害者自立支援法の地域支援事業の要綱の記載が、別の混乱を招くことになった。この点は、次回。
2007年09月25日
「通訳」行為と要約筆記者
聞こえない人のためのその場の情報保障ということを明確にするために、「通訳としての要約筆記」という言い方をするのだが、この「通訳」という言葉について、様々な誤解がある。その誤解の一つに、通訳が要約筆記者の理解を通じて行なわれる、ということに対して、それでは要約筆記を利用する人は、要約筆記者の理解を聞かされることになってしまう、というものがある。
人が、他人の話を媒介する場合、理解なしには、伝達行為そのものが成り立たないことはおそらく了解されている。しかし、その要約筆記者の理解というものが、なにかその要約筆記者個人の理解、というものだと誤解されているらしい。もちろんある意味でそれは要約筆記者個人の理解なのだといえる。そう言うと、要約筆記による通訳では、例えば十人の要約筆記者がいて、要約筆記をすると、十通りの理解があり、十通りの要約筆記者の意見に彩られた筆記が画面に現われる、というふうに受け取るのだろうか。
私は全くそうは思っていない。訓練していない人がメモを取る、という場合は、確かにそれに近いことが起きるだろう。要約筆記者が何十時間、あるいは百時間を越える講座を受講し、訓練を受けるということは、十人の要約筆記者が同じように書く、言葉のいくつかは異なるとしても、意味全体では同じ内容を通訳できるようになるためなのだ。それが要約筆記が誰にでもできるわけではない、という意味で、要約筆記には高い専門性がある、といわれる理由だ。
「速く書く 講義・講演筆記の技法」(斉藤喜門著、蒼丘書林、1987年)という本によれば、中学生に一年間添削指導をしたら、書き取る内容がほとんど同じになったという。著者は、授業のノート録りを中学生に指導する実験をしたという。最初は、全くバラバラだった40人の中学生のノートの内容が、一年間、添削指導をし続けると、一年後には見事に一致したという。これが訓練ということなのだ。
ある人が何かを伝えようとして話をする、文章を書く。その順序は、「言いたい何か」がまず先にあり、その後で言葉が選ばれる。あるいは話しながら、書きながら、言いたい何かがはっきりしてくる。その言いたいこと、伝えたいことを、話し手なり、書き手が選択した言葉を通して、受け取った人が理解する。訓練された要約筆記者による理解は、受け取った要約筆記者の意見ではなく、話し手が意図した「伝えたいこと」の理解そのものになる、そういうもの目指しているのだ。実際、いわゆる上手い要約筆記者を集めてデモテープを使って筆記してもらうと、その要約筆記は驚くほど似ている。個々の要約筆記者は確かにそれぞれの意見を持っているだろう。しかし要約筆記の作業とは、そうした要約筆記者の持っている意見とは何の関係もないもの、個々の要約筆記者の個性や違いを越えて、客観的に話し手の意図を再現するものを目指しているのだ。
では、どうすればそうした理解、理解に基づく筆記が可能になるのか。2005年に全難聴により実施された「要約筆記通訳者養成等に関する調査研究事業」で検討され提案された「要約筆記者」の到達目標とカリキュラムをみてほしい。それまでの「要約筆記奉仕員」の到達目標が「聴覚障害(および聴覚障害者)の理解」と「要約筆記の技術および知識」の二つに括られるのに対して、「要約筆記者」の到達目標は5つある。その到達目標に至るためのカリキュラムの内容もかなりのボリュームになっている。それは、要約筆記者に幅広い知識を身につけてもらい、より客観性の高い要約筆記を実現するためだと言っていいだろう。全難聴の上記事業で提案された「要約筆記者の到達目標」を掲げておく(全難聴のホームページになぜか到達目標それ自体は見あたらない。掲載して欲しいな)。
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
要約筆記通訳者の5つの到達目標
・社会福祉の理念を理解していること
・「通訳」という行為に対する自覚的な理解をしていること
・要約筆記技術をもって通訳作業を実践できること
・対人支援に関わる者としての自己育成ができること
・聴覚障害者の権利擁護の観点から通訳できること
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
社会福祉の理念を理解し、自らの行為(通訳としての要約筆記による支援行為)に対して自覚な理解をする、あるいは対人支援の観点から自己育成ができる、そういう要約筆記者とは、単に聞こえない人が困っているからなんとしたい、せめて少しでも情報を手渡したいとペンを握るという人のことではない。人が何かを伝えたいと考えて言葉を選択する、言葉を組み立てて伝えようとする、その行為がどのようになされるか、というところまで遡って学んでいる人、使われている日本語がどのような言語であり、どのような特徴を持っているのか、だから表現はこのようになされ、それを伝えるためにはどのような言葉の選択と組立が必要になるかを知っている人。障害者への支援とは、障害者の権利擁護のためであり、その権利擁護がこの国ではどのような制度的枠組みで行なわれているかを理解している人、そして障害者一人一人を支援することの意味、支援に関わる要約筆記者のあり方について自省と向上の気持ちを持ち続けられる人。そういう人を目指して、「要約筆記者」を定義しようとしたのが、要約筆記者の到達目標であり、その養成カリキュラムだと思っている。
それは高い理想かも知れない。しかし高い理想を掲げない運動に実りは小さい。私たち、「要約筆記者」を目指す者は、要約筆記が、自分たちの理解に基づいて行なわれることを知っている。だからこそ、その自分の理解が、より客観的で、共通の理解に近づくように研鑽を惜しまない。その力が一定のレベルに達しないのであれば、いくら中途失聴・難聴者に対する暖かい心があったとしても、通訳行為に関わってはいけない。そのためには、公的な支援に携わる要約筆記者であれば、認定試験はさけて通れないだろう。「要約筆記奉仕員」という存在が不要な訳ではない。中途失聴・難聴者の社会参加を促進する支援という点から、たくさんの要約筆記奉仕員が育つことは必要だ。しかし、「奉仕員」という枠組みは、支援しようとする気持ちを大切にし、身につけた技術でそれなりの支援をする人なのだ。認定試験は、奉仕員にはなじまない。
いずれ、話し手のことばをそのまま伝える技術が作られるかも知れない。その前に、音声を、より自然に聴神経の信号に変換して、聞こえるようにする医療が実現するかも知れない。それはもちろん望ましいことだ。早くそうなってほしい。しかし今現在、全文を伝える技術も完全な人工内耳もないのだから、誰かが、他人の言葉を、いや、言いたいこと(意図)を伝達しなければならない。最も小規模な機材でそれを可能にする手書き要約筆記の果たすべき仕事は、まだまだ大きいと私は思う。それが、2年の訓練期間を想定した「要約筆記者」の養成が早く始められなければならないと考える理由だ。
人が、他人の話を媒介する場合、理解なしには、伝達行為そのものが成り立たないことはおそらく了解されている。しかし、その要約筆記者の理解というものが、なにかその要約筆記者個人の理解、というものだと誤解されているらしい。もちろんある意味でそれは要約筆記者個人の理解なのだといえる。そう言うと、要約筆記による通訳では、例えば十人の要約筆記者がいて、要約筆記をすると、十通りの理解があり、十通りの要約筆記者の意見に彩られた筆記が画面に現われる、というふうに受け取るのだろうか。
私は全くそうは思っていない。訓練していない人がメモを取る、という場合は、確かにそれに近いことが起きるだろう。要約筆記者が何十時間、あるいは百時間を越える講座を受講し、訓練を受けるということは、十人の要約筆記者が同じように書く、言葉のいくつかは異なるとしても、意味全体では同じ内容を通訳できるようになるためなのだ。それが要約筆記が誰にでもできるわけではない、という意味で、要約筆記には高い専門性がある、といわれる理由だ。
「速く書く 講義・講演筆記の技法」(斉藤喜門著、蒼丘書林、1987年)という本によれば、中学生に一年間添削指導をしたら、書き取る内容がほとんど同じになったという。著者は、授業のノート録りを中学生に指導する実験をしたという。最初は、全くバラバラだった40人の中学生のノートの内容が、一年間、添削指導をし続けると、一年後には見事に一致したという。これが訓練ということなのだ。
ある人が何かを伝えようとして話をする、文章を書く。その順序は、「言いたい何か」がまず先にあり、その後で言葉が選ばれる。あるいは話しながら、書きながら、言いたい何かがはっきりしてくる。その言いたいこと、伝えたいことを、話し手なり、書き手が選択した言葉を通して、受け取った人が理解する。訓練された要約筆記者による理解は、受け取った要約筆記者の意見ではなく、話し手が意図した「伝えたいこと」の理解そのものになる、そういうもの目指しているのだ。実際、いわゆる上手い要約筆記者を集めてデモテープを使って筆記してもらうと、その要約筆記は驚くほど似ている。個々の要約筆記者は確かにそれぞれの意見を持っているだろう。しかし要約筆記の作業とは、そうした要約筆記者の持っている意見とは何の関係もないもの、個々の要約筆記者の個性や違いを越えて、客観的に話し手の意図を再現するものを目指しているのだ。
では、どうすればそうした理解、理解に基づく筆記が可能になるのか。2005年に全難聴により実施された「要約筆記通訳者養成等に関する調査研究事業」で検討され提案された「要約筆記者」の到達目標とカリキュラムをみてほしい。それまでの「要約筆記奉仕員」の到達目標が「聴覚障害(および聴覚障害者)の理解」と「要約筆記の技術および知識」の二つに括られるのに対して、「要約筆記者」の到達目標は5つある。その到達目標に至るためのカリキュラムの内容もかなりのボリュームになっている。それは、要約筆記者に幅広い知識を身につけてもらい、より客観性の高い要約筆記を実現するためだと言っていいだろう。全難聴の上記事業で提案された「要約筆記者の到達目標」を掲げておく(全難聴のホームページになぜか到達目標それ自体は見あたらない。掲載して欲しいな)。
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−要約筆記通訳者の5つの到達目標
・社会福祉の理念を理解していること
・「通訳」という行為に対する自覚的な理解をしていること
・要約筆記技術をもって通訳作業を実践できること
・対人支援に関わる者としての自己育成ができること
・聴覚障害者の権利擁護の観点から通訳できること
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
社会福祉の理念を理解し、自らの行為(通訳としての要約筆記による支援行為)に対して自覚な理解をする、あるいは対人支援の観点から自己育成ができる、そういう要約筆記者とは、単に聞こえない人が困っているからなんとしたい、せめて少しでも情報を手渡したいとペンを握るという人のことではない。人が何かを伝えたいと考えて言葉を選択する、言葉を組み立てて伝えようとする、その行為がどのようになされるか、というところまで遡って学んでいる人、使われている日本語がどのような言語であり、どのような特徴を持っているのか、だから表現はこのようになされ、それを伝えるためにはどのような言葉の選択と組立が必要になるかを知っている人。障害者への支援とは、障害者の権利擁護のためであり、その権利擁護がこの国ではどのような制度的枠組みで行なわれているかを理解している人、そして障害者一人一人を支援することの意味、支援に関わる要約筆記者のあり方について自省と向上の気持ちを持ち続けられる人。そういう人を目指して、「要約筆記者」を定義しようとしたのが、要約筆記者の到達目標であり、その養成カリキュラムだと思っている。
それは高い理想かも知れない。しかし高い理想を掲げない運動に実りは小さい。私たち、「要約筆記者」を目指す者は、要約筆記が、自分たちの理解に基づいて行なわれることを知っている。だからこそ、その自分の理解が、より客観的で、共通の理解に近づくように研鑽を惜しまない。その力が一定のレベルに達しないのであれば、いくら中途失聴・難聴者に対する暖かい心があったとしても、通訳行為に関わってはいけない。そのためには、公的な支援に携わる要約筆記者であれば、認定試験はさけて通れないだろう。「要約筆記奉仕員」という存在が不要な訳ではない。中途失聴・難聴者の社会参加を促進する支援という点から、たくさんの要約筆記奉仕員が育つことは必要だ。しかし、「奉仕員」という枠組みは、支援しようとする気持ちを大切にし、身につけた技術でそれなりの支援をする人なのだ。認定試験は、奉仕員にはなじまない。
いずれ、話し手のことばをそのまま伝える技術が作られるかも知れない。その前に、音声を、より自然に聴神経の信号に変換して、聞こえるようにする医療が実現するかも知れない。それはもちろん望ましいことだ。早くそうなってほしい。しかし今現在、全文を伝える技術も完全な人工内耳もないのだから、誰かが、他人の言葉を、いや、言いたいこと(意図)を伝達しなければならない。最も小規模な機材でそれを可能にする手書き要約筆記の果たすべき仕事は、まだまだ大きいと私は思う。それが、2年の訓練期間を想定した「要約筆記者」の養成が早く始められなければならないと考える理由だ。
2007年09月17日
聞こえの保障と要約筆記
私が要約筆記に関わりを持ち始めた約30年前。中途失聴者・難聴者が求めていたものは、「聞こえの保障」だった。中途失聴、難聴であることによって、社会で、いや社会だけではなく、家庭で、教育の場で、職場で、つまりあらゆる場所で、中途失聴者、難聴者は、音声情報から隔てられていた。中途失聴者・難聴者に音声情報を保障しようとする動きはきわめて弱かった。手話は、少しずつ認知され始めていたが、聴覚障害者ならば手話が使えるはず、という誤解もまた拡がり始めていた。
聞こえないが手話を使わない、あるいは使えない聴覚障害者の存在にいち早く気づき支援を始めたのは、手話通訳者の一部の方々だったが、手話に代えて、話しことばを文字にして伝えようとする活動は、やがて「要約筆記者」に引き継がれて行った。中途失聴者・難聴者が求めたのは「聞こえの保障」であって、単に会議の通訳ではなかった。要約筆記者もその要求の切実なことを知り、聞こえの保障を求める運動に積極的に関わってきた。聞こえないことで隔てられた音声情報を取り戻すために音声を文字化して伝える試みは、OHPの上に透明なシートをおいて油性ペンで書き、その場の情報を伝えることだけではなく、日本映画に字幕を付けること、講演などの録音をテープ起こしして提供するなど、様々な取り組みとして行なわれた。そして現在も続いている。
様々な分類が可能だが、音声情報をたとえば次の二つの軸を使って整理してみることができる。
横軸:前もって準備できるものか、その場で対応するしかないものか
縦軸:話の内容が重要か、どんな風には話されたかといった表現が重要か
内容が重要
☆ ↑ ★ 会議
事 | 講演
前 ◆映画 プラネタリウム
に←————————┼——————→その場で発言
準 芝居 |
備 |
落語 ↓
表現が重要
(等幅フォントで表示してください)
例えば映画の音声は、事前に字幕として準備しておき、映画の上映に合わせて、映画スクリーンの横に投影する事ができる。したがって、こうした事前に準備できるものは横軸の一番左端に位置する。会議などで出席者が話すことはその場での発言だから、事前に準備することは難しい。これは横軸だと一番右側にくる。名古屋市科学館での上演は、学芸員の話す内容がある程度分かっているが、毎回同じではない、という意味では、横軸の真ん中くらいか。落語なども、話す内容はだいたい同じだが、事前に字幕をすべて用意できる訳ではないという点で似ている。
他方、議論しているときの誰かの意見は、その内容が一番重要だ。提案に賛成なのか反対なのか、その理由は何か、ということが重要であって、名古屋弁で賛成したか関西弁で反対したかは問題には(普通は)ならない。これは縦軸の一番上に来る。他方、落語であれば、話す内容はほぼ決まっているが、どう話すかが重要になる。同じ話を二つ目が演るのと、名人が演ずるのではまるで違う。芸術は、つまるところ表現に宿るのだ。縦軸上では、一番下に位置づけられるだろう。
こうやって様々な音声情報を、この二つの軸を使って分類してみる。そうすると、例えば駅など交通機関の案内放送でも、次の駅名の案内なら事前に準備しておけるし、内容(駅名)が重要だから、左の上(☆印のところ)。一方、事故などで止まったときは、事前に準備しておけず、内容重視だから、右上(★印のところ)、となる。
この広い音声情報の世界のどこが現時点である程度保障され、どこが保障されていないだろうか。その検討をする前に、まず誰がこの音声情報の世界を聞こえない人に伝えたいと考えたかを思ってみてほしい。まず家族が何とかしようと考えたことは間違いない。それは、聴覚障害児の体験談を伺うとよく分かる。学校の授業を子どもにすべて録音させ、夜っぴて家族で(大部分は母親が)テープ起こししてきたという話を聞くことがある。しかしあらゆる場所に家族だけで対応できないことははっきりしている。次第に社会的な支援の必要性が理解され、ボランティアによる対応が始まる。とはいえ、初期の頃のボランティアには、「聞こえない家族がいて」とか「聞こえない友人に頼まれて」とか、何らかの係累を持っているケースが多かったように思う。それはある程度当然だと思う。なぜなら、中途失聴者・難聴者がどういう支援を必要としているか、という整理はされておらず、その要求がある程度分かっているのは関係者だけだったのだから。
ボランティアによる対応が始まって、どのような支援が必要であり、可能なのかが分かってきて初めて行政による公的な支援が始まる。この関係は、後になるとなかなかわかりにくくなる。手話通訳が必要だとか、要約筆記が必要だ、公的な派遣は当然だ、と現時点では考えるけれど、支援の始まりにおいては、そのことは分かっていない。第一、手話通訳や要約筆記という方法で音声情報を伝えることが可能かどうか、誰も知らなかったのだから。
名古屋の場合、要約筆記者の派遣は、厚生省(当時)のいわゆるメニュー事業に要約筆記者派遣事業が入る一年前(1984年)から始まっている(メニュー事業に入ったのは1985年)。それは、1978年に名古屋に生まれた「まごのて」というサークルが毎年多数の要約筆記派遣を引き受け、そのデータを年度ごとに名古屋市に提出してきたということ、そしてその派遣依頼の過半を占めていた名難聴(当時は名聴連のB部)が、苦しい財政をやりくりしながら、その派遣の謝礼を負担し、行政に対して、自分たちには要約筆記が必要だ、そしてそのためにはこれだけの費用がかかるのだ、と要求し続けてきた、ということ、この二つの事実が大きい。上述した情報保障の広い領域の中で、この部分(★印のあたり)、つまり難聴者の会議などの情報保障を、要約筆記という方法でカバーできることを実践的に示し、そのデータをもって行政に要望していくことで初めて公的な支援が実現した。それなしにはどのような支援も公的な支援として取り出されることはないのだ。
名古屋市が要約筆記の派遣事業を始めると同時に「まごのて」は要約筆記の派遣から手を引き、公的な派遣に乗らない要約筆記の依頼には対応し続けたものの、要約筆記者の派遣から、映画の字幕作りへとサークル活動の方向を変えた。ちなみに、公的な派遣制度に乗らない派遣依頼については、すでに別に書いたように、名古屋市登録要約筆記者の会ができたことで、すべてを移管し、サークルでの派遣には終止符を打った。
映画の字幕作りは、派遣制度の開始ときびすを返すようにして始まり、今日に及んでいる。一番活動が盛んだったときには年間6,7本の日本映画に字幕を付けていた。その活動で特筆すべきは、一般映画館で字幕を付けてきたということだ。確かに最初の頃は、字幕作りのノウハウを蓄積するために、自主映画祭などで字幕を付けたが、シネマスコーレという名古屋駅前の小さな映画館を振り出しに、松竹座、東映劇場、エルンゼル東宝、名宝スカラ座、国際劇場など、名古屋市内の多くの一般映画館で、字幕を付けてきた。要するに、普通の封切り映画館での通常の上映に字幕を持ち込んでいたのだ。「まごのて」では、こうした字幕付けの案内を名古屋市の民生局にいつも送っていたが、ある年、突然呼ばれ、今年から助成金を付ける、と言われた。したがって、その年から今日まで、「まごのて」の日本映画に字幕を付ける活動は、公的な助成の元で行なわれていることになる。また映画会社が、配給する映画に自ら字幕を付けることも増えた。上述したマップの左側の映画の領域(◆の領域)は、かなりの程度社会的にカバーされているといえるかも知れない。日本映画に字幕を付ける活動に公的な助成が付いている地域はたぶん他にはないと思うけれど、上記のマップで言えば、右上のその場の情報保障としての要約筆記者の派遣(★)と、左側の映画の字幕(◆)については、名古屋ではいずれも公的な支援の元で行なわれていることになる。
現在、「まごのて」はプラネタリウムの字幕に取り組んでいるが、これはマップで言えば、だいたい真ん中あたりの活動。まだ公的な助成の対象にはなっていないが、この活動が継続されていけばいずれ何らかの形で公的な支援が得られるはずだ。あるいは公的な取り組みになっていくはずだ。
上記の例は、要するに、そこにニーズがあるかどうか分からないとき、公的な支援は当然にない、そしてボランティアが先進的な取り組みを始め、そこにニーズがあることが明確になり、支援の形が整ってくると、それは社会的な支援の対象になる、ということだ。要求すれば叶うのではない。要求があるかどうかまだはっきりしない段階から、ほとんどの活動はスタートする。そのとき、社会福祉に関する活動としてのボランティア活動が果たす役割は大きい。そして、ボランティア活動を継続するとともに、その活動の専門性を明確にし、障害者団体とともに、その活動を定義し、社会的な要求として位置づけていく、そこまでできて、初めて公的な支援の対象となり、社会福祉事業として助成の対象となる、という関係だろう。
要約筆記者が中途失聴者・難聴者の要望を受けて、その聞こえの保障の広い活動領域に足を踏み込んだとき、公的な支援は何もなかった。そこから、ボランティア活動を通して蓄積したてきものが、一つずつ取り出され、専門性を持った取り組みとして、公的な支援の対象になっていく。その場の情報保障としての要約筆記は、その一つの例証だ。公的な裏付けのなかったサークル派遣から、奉仕員派遣事業として公的な支援の対象となり、更に奉仕員事業から社会福祉事業へと進もうとしている。そのことも重要だが、それよりも強く指摘しなければならないことは、「聞こえの保障」を実現すべき領域はまだまだ広く、その過半は手つかずのままだと言うことだ。
全難聴が提案した要約筆記者養成カリキュラムによる要約筆記者の養成と派遣とが速やか全国で始まって欲しい。要約筆記者の養成と派遣が、それが可能な地域で始まったとしても、それは単に★印の領域が、社会福祉事業として実施されるようになることに過ぎない。要約筆記に関わってきたボランティア(要約筆記奉仕員を含めて)が、取り組むべき聞こえの保障の領域はまだまだ広い。要約筆記者養成カリキュラムに関わる問題を早く整理して、次に進まなければならない。違うだろうか。
聞こえないが手話を使わない、あるいは使えない聴覚障害者の存在にいち早く気づき支援を始めたのは、手話通訳者の一部の方々だったが、手話に代えて、話しことばを文字にして伝えようとする活動は、やがて「要約筆記者」に引き継がれて行った。中途失聴者・難聴者が求めたのは「聞こえの保障」であって、単に会議の通訳ではなかった。要約筆記者もその要求の切実なことを知り、聞こえの保障を求める運動に積極的に関わってきた。聞こえないことで隔てられた音声情報を取り戻すために音声を文字化して伝える試みは、OHPの上に透明なシートをおいて油性ペンで書き、その場の情報を伝えることだけではなく、日本映画に字幕を付けること、講演などの録音をテープ起こしして提供するなど、様々な取り組みとして行なわれた。そして現在も続いている。
様々な分類が可能だが、音声情報をたとえば次の二つの軸を使って整理してみることができる。
横軸:前もって準備できるものか、その場で対応するしかないものか
縦軸:話の内容が重要か、どんな風には話されたかといった表現が重要か
内容が重要
☆ ↑ ★ 会議
事 | 講演
前 ◆映画 プラネタリウム
に←————————┼——————→その場で発言
準 芝居 |
備 |
落語 ↓
表現が重要
(等幅フォントで表示してください)
例えば映画の音声は、事前に字幕として準備しておき、映画の上映に合わせて、映画スクリーンの横に投影する事ができる。したがって、こうした事前に準備できるものは横軸の一番左端に位置する。会議などで出席者が話すことはその場での発言だから、事前に準備することは難しい。これは横軸だと一番右側にくる。名古屋市科学館での上演は、学芸員の話す内容がある程度分かっているが、毎回同じではない、という意味では、横軸の真ん中くらいか。落語なども、話す内容はだいたい同じだが、事前に字幕をすべて用意できる訳ではないという点で似ている。
他方、議論しているときの誰かの意見は、その内容が一番重要だ。提案に賛成なのか反対なのか、その理由は何か、ということが重要であって、名古屋弁で賛成したか関西弁で反対したかは問題には(普通は)ならない。これは縦軸の一番上に来る。他方、落語であれば、話す内容はほぼ決まっているが、どう話すかが重要になる。同じ話を二つ目が演るのと、名人が演ずるのではまるで違う。芸術は、つまるところ表現に宿るのだ。縦軸上では、一番下に位置づけられるだろう。
こうやって様々な音声情報を、この二つの軸を使って分類してみる。そうすると、例えば駅など交通機関の案内放送でも、次の駅名の案内なら事前に準備しておけるし、内容(駅名)が重要だから、左の上(☆印のところ)。一方、事故などで止まったときは、事前に準備しておけず、内容重視だから、右上(★印のところ)、となる。
この広い音声情報の世界のどこが現時点である程度保障され、どこが保障されていないだろうか。その検討をする前に、まず誰がこの音声情報の世界を聞こえない人に伝えたいと考えたかを思ってみてほしい。まず家族が何とかしようと考えたことは間違いない。それは、聴覚障害児の体験談を伺うとよく分かる。学校の授業を子どもにすべて録音させ、夜っぴて家族で(大部分は母親が)テープ起こししてきたという話を聞くことがある。しかしあらゆる場所に家族だけで対応できないことははっきりしている。次第に社会的な支援の必要性が理解され、ボランティアによる対応が始まる。とはいえ、初期の頃のボランティアには、「聞こえない家族がいて」とか「聞こえない友人に頼まれて」とか、何らかの係累を持っているケースが多かったように思う。それはある程度当然だと思う。なぜなら、中途失聴者・難聴者がどういう支援を必要としているか、という整理はされておらず、その要求がある程度分かっているのは関係者だけだったのだから。
ボランティアによる対応が始まって、どのような支援が必要であり、可能なのかが分かってきて初めて行政による公的な支援が始まる。この関係は、後になるとなかなかわかりにくくなる。手話通訳が必要だとか、要約筆記が必要だ、公的な派遣は当然だ、と現時点では考えるけれど、支援の始まりにおいては、そのことは分かっていない。第一、手話通訳や要約筆記という方法で音声情報を伝えることが可能かどうか、誰も知らなかったのだから。
名古屋の場合、要約筆記者の派遣は、厚生省(当時)のいわゆるメニュー事業に要約筆記者派遣事業が入る一年前(1984年)から始まっている(メニュー事業に入ったのは1985年)。それは、1978年に名古屋に生まれた「まごのて」というサークルが毎年多数の要約筆記派遣を引き受け、そのデータを年度ごとに名古屋市に提出してきたということ、そしてその派遣依頼の過半を占めていた名難聴(当時は名聴連のB部)が、苦しい財政をやりくりしながら、その派遣の謝礼を負担し、行政に対して、自分たちには要約筆記が必要だ、そしてそのためにはこれだけの費用がかかるのだ、と要求し続けてきた、ということ、この二つの事実が大きい。上述した情報保障の広い領域の中で、この部分(★印のあたり)、つまり難聴者の会議などの情報保障を、要約筆記という方法でカバーできることを実践的に示し、そのデータをもって行政に要望していくことで初めて公的な支援が実現した。それなしにはどのような支援も公的な支援として取り出されることはないのだ。
名古屋市が要約筆記の派遣事業を始めると同時に「まごのて」は要約筆記の派遣から手を引き、公的な派遣に乗らない要約筆記の依頼には対応し続けたものの、要約筆記者の派遣から、映画の字幕作りへとサークル活動の方向を変えた。ちなみに、公的な派遣制度に乗らない派遣依頼については、すでに別に書いたように、名古屋市登録要約筆記者の会ができたことで、すべてを移管し、サークルでの派遣には終止符を打った。
映画の字幕作りは、派遣制度の開始ときびすを返すようにして始まり、今日に及んでいる。一番活動が盛んだったときには年間6,7本の日本映画に字幕を付けていた。その活動で特筆すべきは、一般映画館で字幕を付けてきたということだ。確かに最初の頃は、字幕作りのノウハウを蓄積するために、自主映画祭などで字幕を付けたが、シネマスコーレという名古屋駅前の小さな映画館を振り出しに、松竹座、東映劇場、エルンゼル東宝、名宝スカラ座、国際劇場など、名古屋市内の多くの一般映画館で、字幕を付けてきた。要するに、普通の封切り映画館での通常の上映に字幕を持ち込んでいたのだ。「まごのて」では、こうした字幕付けの案内を名古屋市の民生局にいつも送っていたが、ある年、突然呼ばれ、今年から助成金を付ける、と言われた。したがって、その年から今日まで、「まごのて」の日本映画に字幕を付ける活動は、公的な助成の元で行なわれていることになる。また映画会社が、配給する映画に自ら字幕を付けることも増えた。上述したマップの左側の映画の領域(◆の領域)は、かなりの程度社会的にカバーされているといえるかも知れない。日本映画に字幕を付ける活動に公的な助成が付いている地域はたぶん他にはないと思うけれど、上記のマップで言えば、右上のその場の情報保障としての要約筆記者の派遣(★)と、左側の映画の字幕(◆)については、名古屋ではいずれも公的な支援の元で行なわれていることになる。
現在、「まごのて」はプラネタリウムの字幕に取り組んでいるが、これはマップで言えば、だいたい真ん中あたりの活動。まだ公的な助成の対象にはなっていないが、この活動が継続されていけばいずれ何らかの形で公的な支援が得られるはずだ。あるいは公的な取り組みになっていくはずだ。
上記の例は、要するに、そこにニーズがあるかどうか分からないとき、公的な支援は当然にない、そしてボランティアが先進的な取り組みを始め、そこにニーズがあることが明確になり、支援の形が整ってくると、それは社会的な支援の対象になる、ということだ。要求すれば叶うのではない。要求があるかどうかまだはっきりしない段階から、ほとんどの活動はスタートする。そのとき、社会福祉に関する活動としてのボランティア活動が果たす役割は大きい。そして、ボランティア活動を継続するとともに、その活動の専門性を明確にし、障害者団体とともに、その活動を定義し、社会的な要求として位置づけていく、そこまでできて、初めて公的な支援の対象となり、社会福祉事業として助成の対象となる、という関係だろう。
要約筆記者が中途失聴者・難聴者の要望を受けて、その聞こえの保障の広い活動領域に足を踏み込んだとき、公的な支援は何もなかった。そこから、ボランティア活動を通して蓄積したてきものが、一つずつ取り出され、専門性を持った取り組みとして、公的な支援の対象になっていく。その場の情報保障としての要約筆記は、その一つの例証だ。公的な裏付けのなかったサークル派遣から、奉仕員派遣事業として公的な支援の対象となり、更に奉仕員事業から社会福祉事業へと進もうとしている。そのことも重要だが、それよりも強く指摘しなければならないことは、「聞こえの保障」を実現すべき領域はまだまだ広く、その過半は手つかずのままだと言うことだ。
全難聴が提案した要約筆記者養成カリキュラムによる要約筆記者の養成と派遣とが速やか全国で始まって欲しい。要約筆記者の養成と派遣が、それが可能な地域で始まったとしても、それは単に★印の領域が、社会福祉事業として実施されるようになることに過ぎない。要約筆記に関わってきたボランティア(要約筆記奉仕員を含めて)が、取り組むべき聞こえの保障の領域はまだまだ広い。要約筆記者養成カリキュラムに関わる問題を早く整理して、次に進まなければならない。違うだろうか。
2007年09月02日
指導者養成講習会終了
名古屋では、7月から9月1日まで、要約筆記指導者養成講習会が開かれていた。私も受講していたのだが、とても良い講習会だった。要約筆記者養成講座で、受講生を指導する、受講生に要約筆記を教えるとはどういうことなのか、原点に戻り、しかも方法論がしっかりした内容だった。(写真は養成講習会の一コマ)

しかし、それより何よりうれしかったのは、名古屋の要約筆記の養成・指導が、新しいフェーズに入ったと感じられたことだった。名古屋の要約筆記の歴史はかなり古い。要約筆記奉仕員養成が、厚生省のメニューに事業に入った年(1981年)から講座は開かれている。毎年の講座で、講師を担当してこられた方は、本当に一生懸命教えてこられた。けれども、それは個人個人の工夫に支えられたものだった。個人の工夫はもとより尊い。だが、組織だった対応、ということを考えると、個人個人の対応では、限界があった。
話を少し前に戻して、地域の要約筆記事業がどうあるべきかということをおさらいしてみよう。私が考える要約筆記事業のあるべき姿は、次のようものだ。
(1)要約筆記の派遣が公的に行なわれている。派遣窓口、派遣される要約筆記者の手配などは、公的機関もしくはこれに準ずる機関が行なう。
(2)派遣される要約筆記者は、ボランティアではなく、公的な制度に組み込まれた要約筆記者である。それは、要約筆記が必要な人が、今日も、明日も、来年も、10年後も、必要なときに必要なコミュニケーション支援が受けられる、ということだ。ボランティアとしての対応では、制度的に安定な支援は得られない可能性があるからだ。ボランティアももちろん必要だし、社会全体が、聞こえない人に対して理解を深めることも大切だが、支援が必要な人に必要な支援を提供できる、という点を考えると、要約筆記者の身分保障も含めて、公的な制度の構築は、どうしても必要だ。
(3)要約筆記者養成についての一貫した指導体制がある。上記の通り、個人個人の工夫も大切だが、それを超えて、地域の指導体制が確立していることが望ましい。でないと、この年は良い講座だったが、翌年は不十分だった、という可能性がある。また同じ年の講座でも、○○講師の内容は良かったが、××講師の話は分からなかった、などと言うことになりかねない。養成カリキュラムについての理解、指導案の作成技術、講座での指導方法、などを講師が共有し、一貫した内容を、質の揃った指導で、教えられる体制があることは、受講生にとっても、またやがてその受講生を受け入れて派遣をする派遣元にとっても、その派遣を受けてコミュニケーション支援として活用する聴覚障害者にとっても、望ましい。
(4)地域の要約筆記サークルと登録要約筆記者の会が、互いの役割を理解して棲み分けている。要約筆記サークルは、多くの地域で要約筆記活動の母体となっている。名古屋とて例外ではない。しかしサークルがいくらガンバつても、登録要約筆記者の会の代替はできない。そもそも制度上の役割が全く違うからだ。サークルには、様々な人がいる。守秘義務もない。要約筆記の技術もまちまちだろう。と同時にボランティアサークルは、要約筆記通訳だけを目的とした集まりではないから、様々な活動に対して開かれている。先駆的な活動は、サークルがまず取り組み、次第にその専門性が明らかになっていくことで、新しい制度が生まれ、社会に定着していくということは多い。サークルと登録要約筆記者の会が、ごちゃごちゃに活動しているのではなく、お互いの役割と責任を理解して、活動を棲み分けている、ということは重要だが、意外に整理されていない点だと思う。
こうした点を考えると、名古屋の場合、要約筆記奉仕員養成・派遣は、一貫して(社)名身連が行なってきたので、(1)の条件は一応満足している。また、昨年、「名古屋市登録要約筆記者の会(登要会なごや)」が生まれ、従来からあった要約筆記サークル・まごのてとの間で、役割分担についてはうまく整理ができた。例えば、公的な派遣制度にのらない要約筆記の依頼があった場合、まごのては、サークルへの依頼があっても引き受けず、登要会なごやが対応する(要約筆記通訳が必要な場面ではサークル員ではなく要約筆記者が対応するのが原則)、といったことを双方が確認してきた。まごのては、プラネタリウムの字幕付き上演など、ボランティアサークルとして先駆的な活動に取り組むなど。これは、上記の(4)の条件がある程度満たされているということだ。
そして今回の要約筆記指導者養成講習会。上記の(3)の条件が整ったことになる。
残された課題は(2)。これは、要約筆記奉仕員から要約筆記者へということだ。前にも書いたが、要約筆記奉仕員がまるごと要約筆記者に変わるという話ではない。公的な派遣制度の担い手は「要約筆記者」になるべきだ、ということだ。要約筆記奉仕員には、障害者自立支援法の要綱(別記6)にも記載されているように、「スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする」事業がある。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/bukyoku/syougai/j01a.html
(これは、とても重要な事業だと思うが、この点についてはまた別に書きたい)
要約筆記の公的な派遣は、奉仕員制度によってではなく、社会福祉事業として行なわれるべきだと思う。この点が名古屋の場合、まだ未解決の問題として残っているが、(1)(4)の条件に加えて、(3)の条件が整ったことを、私は、心から喜んでいる。私自身、名古屋市の要約筆記者養成講座には講師として何年も関わってきたが、こうした指導体制を作ることはできなかった。それが、登要会なこやができ、その主導の下で、30時間の指導者養成講座を開き、指導方法について、一から共通理解を作り上げる、ということができた。これは、今後の10年、20年の活動の礎になる。講習会の実現に尽力された登要会会長と事務局長、受講料を払って参加し熱心に学んだ受講生、そしてそれを支えた登要会のメンバーに、心からお礼を言いたい。
本当にありがとう。

しかし、それより何よりうれしかったのは、名古屋の要約筆記の養成・指導が、新しいフェーズに入ったと感じられたことだった。名古屋の要約筆記の歴史はかなり古い。要約筆記奉仕員養成が、厚生省のメニューに事業に入った年(1981年)から講座は開かれている。毎年の講座で、講師を担当してこられた方は、本当に一生懸命教えてこられた。けれども、それは個人個人の工夫に支えられたものだった。個人の工夫はもとより尊い。だが、組織だった対応、ということを考えると、個人個人の対応では、限界があった。
話を少し前に戻して、地域の要約筆記事業がどうあるべきかということをおさらいしてみよう。私が考える要約筆記事業のあるべき姿は、次のようものだ。
(1)要約筆記の派遣が公的に行なわれている。派遣窓口、派遣される要約筆記者の手配などは、公的機関もしくはこれに準ずる機関が行なう。
(2)派遣される要約筆記者は、ボランティアではなく、公的な制度に組み込まれた要約筆記者である。それは、要約筆記が必要な人が、今日も、明日も、来年も、10年後も、必要なときに必要なコミュニケーション支援が受けられる、ということだ。ボランティアとしての対応では、制度的に安定な支援は得られない可能性があるからだ。ボランティアももちろん必要だし、社会全体が、聞こえない人に対して理解を深めることも大切だが、支援が必要な人に必要な支援を提供できる、という点を考えると、要約筆記者の身分保障も含めて、公的な制度の構築は、どうしても必要だ。
(3)要約筆記者養成についての一貫した指導体制がある。上記の通り、個人個人の工夫も大切だが、それを超えて、地域の指導体制が確立していることが望ましい。でないと、この年は良い講座だったが、翌年は不十分だった、という可能性がある。また同じ年の講座でも、○○講師の内容は良かったが、××講師の話は分からなかった、などと言うことになりかねない。養成カリキュラムについての理解、指導案の作成技術、講座での指導方法、などを講師が共有し、一貫した内容を、質の揃った指導で、教えられる体制があることは、受講生にとっても、またやがてその受講生を受け入れて派遣をする派遣元にとっても、その派遣を受けてコミュニケーション支援として活用する聴覚障害者にとっても、望ましい。
(4)地域の要約筆記サークルと登録要約筆記者の会が、互いの役割を理解して棲み分けている。要約筆記サークルは、多くの地域で要約筆記活動の母体となっている。名古屋とて例外ではない。しかしサークルがいくらガンバつても、登録要約筆記者の会の代替はできない。そもそも制度上の役割が全く違うからだ。サークルには、様々な人がいる。守秘義務もない。要約筆記の技術もまちまちだろう。と同時にボランティアサークルは、要約筆記通訳だけを目的とした集まりではないから、様々な活動に対して開かれている。先駆的な活動は、サークルがまず取り組み、次第にその専門性が明らかになっていくことで、新しい制度が生まれ、社会に定着していくということは多い。サークルと登録要約筆記者の会が、ごちゃごちゃに活動しているのではなく、お互いの役割と責任を理解して、活動を棲み分けている、ということは重要だが、意外に整理されていない点だと思う。
こうした点を考えると、名古屋の場合、要約筆記奉仕員養成・派遣は、一貫して(社)名身連が行なってきたので、(1)の条件は一応満足している。また、昨年、「名古屋市登録要約筆記者の会(登要会なごや)」が生まれ、従来からあった要約筆記サークル・まごのてとの間で、役割分担についてはうまく整理ができた。例えば、公的な派遣制度にのらない要約筆記の依頼があった場合、まごのては、サークルへの依頼があっても引き受けず、登要会なごやが対応する(要約筆記通訳が必要な場面ではサークル員ではなく要約筆記者が対応するのが原則)、といったことを双方が確認してきた。まごのては、プラネタリウムの字幕付き上演など、ボランティアサークルとして先駆的な活動に取り組むなど。これは、上記の(4)の条件がある程度満たされているということだ。
そして今回の要約筆記指導者養成講習会。上記の(3)の条件が整ったことになる。
残された課題は(2)。これは、要約筆記奉仕員から要約筆記者へということだ。前にも書いたが、要約筆記奉仕員がまるごと要約筆記者に変わるという話ではない。公的な派遣制度の担い手は「要約筆記者」になるべきだ、ということだ。要約筆記奉仕員には、障害者自立支援法の要綱(別記6)にも記載されているように、「スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする」事業がある。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/bukyoku/syougai/j01a.html
(これは、とても重要な事業だと思うが、この点についてはまた別に書きたい)
要約筆記の公的な派遣は、奉仕員制度によってではなく、社会福祉事業として行なわれるべきだと思う。この点が名古屋の場合、まだ未解決の問題として残っているが、(1)(4)の条件に加えて、(3)の条件が整ったことを、私は、心から喜んでいる。私自身、名古屋市の要約筆記者養成講座には講師として何年も関わってきたが、こうした指導体制を作ることはできなかった。それが、登要会なこやができ、その主導の下で、30時間の指導者養成講座を開き、指導方法について、一から共通理解を作り上げる、ということができた。これは、今後の10年、20年の活動の礎になる。講習会の実現に尽力された登要会会長と事務局長、受講料を払って参加し熱心に学んだ受講生、そしてそれを支えた登要会のメンバーに、心からお礼を言いたい。
本当にありがとう。
2007年08月27日
要約筆記の現状−2
 要約筆記が通訳行為、あるいはきわめて通訳行為に近い作業だということかなかなか理解されないでいる理由について触れる前に、現在の要約筆記を巡る状況をおさらいしておきたい。
要約筆記が通訳行為、あるいはきわめて通訳行為に近い作業だということかなかなか理解されないでいる理由について触れる前に、現在の要約筆記を巡る状況をおさらいしておきたい。1981年(昭和56年)に、要約筆記奉仕員養成事業が、厚生省(当時)の社会参加促進事業(いわゆるメニュー事業)に加えられてから、要約筆記は奉仕員事業として発展してきた。たくさんの心ある要約筆記者が、中途失聴・難聴者の聞こえの保障を少しでも実現しようと、本当にがんばってきた。当時を振り返ると、OHPの前に座って書くだけが要約筆記ではなかった。それこそ中途失聴者・難聴者の団体(難聴協会)の例会に参加すること、磁気誘導ループを設置したり、機関誌の印刷を手伝ったり、映画の字幕を作ったり、時には一緒に街頭をデモ行進したり(写真は1978年11月2日の名古屋・栄で行なわれた「聞こえの保障」を求めるデモ)、など様々な活動に参加してきた。そこには、ただ中途失聴・難聴者の聞こえの世界を少しでも広げたいという気持ちだけがあり、通訳だとか字幕だとか、何か区別をたてて考えるということはほとんど無かった。音声情報を文字化することで、聞こえの保障が実現できるのだという、ある意味できわめて楽観的な気持ちで取り組んでいたのだと思う。
1985年(昭和60年)には、要約筆記奉仕員派遣事業がメニュー事業に加わった。そして各地で要約筆記奉仕員の派遣が始まる。要約筆記者の養成と派遣が、要約筆記の活動の中で大きな割合を占めるようになってくる。全国要約筆記問題研究会(全要研)と全日本難聴者・中途失聴者団体連合会(全難聴)は、要約筆記指導者養成講座を開いて、人の話を聞いて書く、という作業をする人、つまり要約筆記する人の養成や、要約筆記を教えられる人の養成に力を入れてきた。他方、日本映画に字幕を付ける活動も、次第に広がりを持ち、全要研では全要研集会に字幕専門分科会を持つようにもなった。
そして、1998年。厚生省の呼びかけで、要約筆記奉仕員の新しいカリキュラムが策定される。私見によれば、このとき作成された要約筆記奉仕員養成カリキュラムは、いわゆる通訳行為に向けてかなり踏み込んだものとなっている。たとえば守秘義務や越権行為の禁止などが明確にうたわれ、このカリキュラムに沿った養成を行なうために作られたテキストには、「要約筆記は通訳行為です」という記載が見られるからだ。また、このカリキュラム策定の記録をひもとくと、中途失聴・難聴者の側から、もっと使える要約筆記、会議などの情報保障をしっかりと支える要約筆記に対する強い要望があり、それまでの多くの地域での養成時間から見れば、倍近い52時間という養成時間が設定されたことがわかる。

更に、全難聴が中心となって、2004年度から、要約筆記に関する調査研究事業が開始された。これは、要約筆記が手話通訳事業とともに、2000年に第二種社会福祉事業に位置づけられたことを受け、社会福祉事業としての要約筆記事業を明確にしようとするものだったと思う。2年にわたる調査研究事業の結果、「通訳として要約筆記」「権利擁護のための要約筆記」という整理がなされ、要約筆記奉仕員とは別の、「要約筆記(通訳)者」の到達目標とその養成カリキュラムが提案された。
ここまでが、ものすごく駆け足で見た要約筆記活動の流れだ。そして現状、要約筆記奉仕員と要約筆記者との関係は、なぜか混迷している。第二種社会福祉事業としての要約筆記を奉仕員事業のままではなく、要約筆記者事業として制度化したいという考え方に対して、要約筆記奉仕員事業がこれまであり、障害者自立支援法の下でも同じように要約筆記奉仕員事業で対応できるのだという考え方が主張されている。実際「要約筆記者養成カリキュラム」が厚生労働省から通達されないでいることも、後者の考え方に力を与えているように見える。
この問題を考えてきて思うのだが、「通訳としての要約筆記」「権利擁護のための要約筆記」という主張は、本来、要約筆記奉仕員による活動全体を置き換えようとするものではなかったのに、あたかも「要約筆記者」の養成・派遣事業が始まれば、要約筆記奉仕員はもはや不要だと受け取られたのではないか。要約筆記が始まったときの原点に戻って考えてみれば、中途失聴・難聴者の聞こえの保障を目指したたくさんの活動があり、そこから中途失聴・難聴者のコミュニケーションを支援する活動や日本映画に字幕を付ける活動などが、少しずつ専門性を持った活動として固まり、一つ一つ固有の活動領域を形成してきたのではないか。図解するとすれば、
「現在の要約筆記の活動」まるごと→要約筆記事業に移行
ということはあり得ない。
現実に、要約筆記奉仕員がこれまで取り組んできた活動を考えれば、
「現在の要約筆記活動」├の一部→「要約筆記(通訳)事業」
─┬──────────┘ として明確化
└の別の一部→「要約筆記奉仕員や字幕の活動」として明確化
という関係のはずだ。要約筆記奉仕員がこれまでしてきた活動を考えれば、要約筆記者事業が始まっても、要約筆記奉仕員の活動のすべてが移行できるはずがないことははっきりしている。
この関係をきちんと整理し、理解しないと、現在の混迷からは抜け出せないのではないか。逆に言えば、ここがきちんと理解されれば、両者の関係が対立的なものではなく、相互補完的なものであることが明確になるのではないか。
2007年08月26日
要約筆記の現状
「要約筆記」という活動にすでに30年近く関わっている。初めてそのボランティア活動を知ったのが1978年の夏。難聴だった友人に頼まれて、「要約筆記」(当時は「OHP」と呼ばれていた)をしたのが最初だ。当時は、要約筆記奉仕員養成講座といったものはなく、見よう見まねで始めた。
「要約筆記」とは、手話を使わない、使えない聴覚障害者、一般には難聴者、中途失聴者のために、人の話を聞いて、書き取ることで通訳することを言う。広辞苑にも最新版には収録されている。書き取るのは、OHP(オーバーベッドプロジェクタ)の上、ということが多い。透明のフィルムにマジックで書いている文字は、書かれているその様子のままスクリーンに投影される。
話し言葉は、ふつうに話して、300字/分といわれている。速い人だと400字以上の人もいる(久米宏さんとか、黒柳徹子さんとか)。一方、手書きで書き取れる文字数は、60字くらい。速くかければもう少し文字数は増えるが、読み取るのが困難な文字になりやすい(要するに、書き殴った文字になり、乱れる)。そうすると、人の話の内容を伝えるためには、何か工夫がいる。30年くらい前に要約筆記が始まったとき、最初に工夫されたのは、略号、略語だ。当時は速記に似せていろんな記号が発明された。しかし、あまり記号が増えると、実は要約筆記は意味を失う。なぜなら、記号を覚えるなら、手話を覚えてもいいはずだからだ。要約筆記は、中途失聴者のように、人生の中途で突然聴覚を失った人が、それでも自分にはこのコミュニケーション手段がある、という形で利用されることが多いからだ。そのとき、画面に見知らぬ記号が飛び交っていては、コミュニケーションとしてすぐに使えない。
そこで全国標準として、略号は9つ、略語は4つが定められた。その後、要約筆記は、話し言葉をいかに要約するか、要約して短い書き言葉にしていくか、という方向と、手書きの文字数を増やすために、「二人書き」という二人で書く工夫をする方向と、大きく言えばこの二つの方向で発展してきた。
後者の二人書きは、主筆者が「口で書く」という感覚で使う。話し言葉を要約して書いてきて、行末近くまできたら口で書くのだ。そうすると補助者がその「口で書かれた言葉」を実際に行末に書き足していく。一行を二人で完成させることになる。この方法で、書き取れる文字数は10−25%くらい増える。そうすると、70文字〜80文字/分くらいはかけることになる。それでも、話し言葉全体からみれば、30%にはなかなか達しない。もとより、難聴者が中心の会合などでは、話し手が配慮してゆっくり目に話すので、二人書きをうまく駆使すると、かなりの部分がかけているように感じることがある。もともと人の話は冗長な場合も少なくないからだ。
しかしそれでも必ず要約することは必要になる。当初、「要約」は、
(1)不要な言葉を、単語レベルで捨てる。
(2)分かり切った言葉を省略する。
(3)例示を減らす、抽象化する。
といったレベルでとらえられてきた。日本語の話し言葉の要約という学問は、基本的にほとんどない。日本で、話し言葉(談話)の要約を研究している人は、早稲田大学の佐久間まゆみさんくらいだろうか。
従って、話し言葉の要約(しかも書き言葉にできる程度の要約)というものは、学問的な追究はされておらず、ほぼ素人の「あーでもない」「こーでもない」というレベルからスタートした。二重否定(例「なくもない」)は肯定文(「ある」)にできる、とか、例示が3つ以上あれば、2つ以下にするとか、様々なパターンが提案されてはいたが、なかなか「学んで使える」というものにはならなかった。
その一番大きな理由は、話し言葉の速さ(約300字)と書き言葉の遅さ(約60字)にとらわれて、そこでおこなわれていることが、「通訳」行為に近いものであり、伝えるべきは概念なのだという理解がなかったことなのだ。要約筆記で行なわれていることが、いったい何なのかをしっかり追求し、そもそもコミュニケーションにおいて渡されているものは何なのか、をもう少し考える必要があった。
ではなぜ、要約筆記を通訳行為としてとらえることができなかったのか。これにはいくつもの理由があっが、この点は、また次回。
「要約筆記」とは、手話を使わない、使えない聴覚障害者、一般には難聴者、中途失聴者のために、人の話を聞いて、書き取ることで通訳することを言う。広辞苑にも最新版には収録されている。書き取るのは、OHP(オーバーベッドプロジェクタ)の上、ということが多い。透明のフィルムにマジックで書いている文字は、書かれているその様子のままスクリーンに投影される。
話し言葉は、ふつうに話して、300字/分といわれている。速い人だと400字以上の人もいる(久米宏さんとか、黒柳徹子さんとか)。一方、手書きで書き取れる文字数は、60字くらい。速くかければもう少し文字数は増えるが、読み取るのが困難な文字になりやすい(要するに、書き殴った文字になり、乱れる)。そうすると、人の話の内容を伝えるためには、何か工夫がいる。30年くらい前に要約筆記が始まったとき、最初に工夫されたのは、略号、略語だ。当時は速記に似せていろんな記号が発明された。しかし、あまり記号が増えると、実は要約筆記は意味を失う。なぜなら、記号を覚えるなら、手話を覚えてもいいはずだからだ。要約筆記は、中途失聴者のように、人生の中途で突然聴覚を失った人が、それでも自分にはこのコミュニケーション手段がある、という形で利用されることが多いからだ。そのとき、画面に見知らぬ記号が飛び交っていては、コミュニケーションとしてすぐに使えない。

そこで全国標準として、略号は9つ、略語は4つが定められた。その後、要約筆記は、話し言葉をいかに要約するか、要約して短い書き言葉にしていくか、という方向と、手書きの文字数を増やすために、「二人書き」という二人で書く工夫をする方向と、大きく言えばこの二つの方向で発展してきた。
後者の二人書きは、主筆者が「口で書く」という感覚で使う。話し言葉を要約して書いてきて、行末近くまできたら口で書くのだ。そうすると補助者がその「口で書かれた言葉」を実際に行末に書き足していく。一行を二人で完成させることになる。この方法で、書き取れる文字数は10−25%くらい増える。そうすると、70文字〜80文字/分くらいはかけることになる。それでも、話し言葉全体からみれば、30%にはなかなか達しない。もとより、難聴者が中心の会合などでは、話し手が配慮してゆっくり目に話すので、二人書きをうまく駆使すると、かなりの部分がかけているように感じることがある。もともと人の話は冗長な場合も少なくないからだ。
しかしそれでも必ず要約することは必要になる。当初、「要約」は、
(1)不要な言葉を、単語レベルで捨てる。
(2)分かり切った言葉を省略する。
(3)例示を減らす、抽象化する。
といったレベルでとらえられてきた。日本語の話し言葉の要約という学問は、基本的にほとんどない。日本で、話し言葉(談話)の要約を研究している人は、早稲田大学の佐久間まゆみさんくらいだろうか。
従って、話し言葉の要約(しかも書き言葉にできる程度の要約)というものは、学問的な追究はされておらず、ほぼ素人の「あーでもない」「こーでもない」というレベルからスタートした。二重否定(例「なくもない」)は肯定文(「ある」)にできる、とか、例示が3つ以上あれば、2つ以下にするとか、様々なパターンが提案されてはいたが、なかなか「学んで使える」というものにはならなかった。
その一番大きな理由は、話し言葉の速さ(約300字)と書き言葉の遅さ(約60字)にとらわれて、そこでおこなわれていることが、「通訳」行為に近いものであり、伝えるべきは概念なのだという理解がなかったことなのだ。要約筆記で行なわれていることが、いったい何なのかをしっかり追求し、そもそもコミュニケーションにおいて渡されているものは何なのか、をもう少し考える必要があった。
ではなぜ、要約筆記を通訳行為としてとらえることができなかったのか。これにはいくつもの理由があっが、この点は、また次回。

