2007年10月30日
「聞こえの保障」と支援者
全難聴が、2004年から、要約筆記に関する調査研究事業を開始して、さまざまな成果を上げていることはこのブログでも何度か触れた。その成果は、事業の報告書として発行され、全難聴から入手することができる。その中でも特筆すべきは、要約筆記者の到達目標と養成カリキュラムだが、この成果物は、なかなか公的な認知に至っていない。その最大の理由は、全難聴と全要研の意見の不一致にあると言っていい。これは厚生労働省の担当官が言明していたのだから間違いはない。
いま、細かく、どこに両団体の意見の不一致、いわゆる齟齬があるのか、説明することはしないが、全国的に見て、なかなか理解されないのが、「聞こえの保障」の広さと、その一部を担う「情報保障」の関係だ。更に言えば、その場の情報を保障する「通訳としての要約筆記」の専門性だろう。前者、つまり「聞こえの保障」と「情報保障」との関係は、前々回詳しく書いた。この問題を巡ってもう一つ、うまく認知ができていないのが、要約筆記者と要約筆記奉仕員の関係だろう。この点については、このブログでも何度か書いている。要約筆記奉仕員の必要性は誰しも認めるところだと思うが、要約筆記奉仕員が大切だから、要約筆記者の養成や認定をいつまでも放置したままにしておくという対応については、私は「間違っている」と考える。なぜ奉仕員事業という制度的にも不安定な事業にいつまでも拠ろうとするのだろうか。
制度の問題はさておき、一つ疑問に思うのは、要約筆記奉仕員にこだわる人は、通訳としての要約筆記以外の聞こえの保障の活動をどの程度した上で、奉仕員で良いといっているのだろうか、ということだ。中失難聴者に対する支援は、「通訳だけでない」とよく言われる。しかし、少なくとも必要とされている支援は、聴覚障害者に代わって電車の切符を買ったり、一緒に旅行に行ったり、飲んだりすることではないだろう。それは支援ではなく、付き合いであるとかお世話であるとか、名付けるとすれば友情であったり、親切であったりする、そういうものだろうと思う。もちろん聴覚障害者とつきあえば、聞こえない故の悩みを聞いたりするとはあるだろう。聴覚障害者の悩みを聞くといった支援も想定することはできる。しかしもしそうした支援をするのであれば、やはりカウンセリング技術の習得など、ある種の専門性が必要になる。単に気持ちがあれば支援できるというものではない。鬱病からの回復期にある患者に、励ますつもりで「もっとがんばって」と言い、病状を悪化させることだってある。「支援者である」というなら、それは「知らなかった」で許されることではないだろう。
中途失聴・難聴者を支援するというのであれば、「聞こえの保障」の領域での支援の必要性が見えないはずないと思う。私が属している名古屋の要約筆記サークル「要約筆記等研究連絡会・まごのて」は、そうした支援の必要性が見えたから、さまざまな支援活動に取り組んできた(サークルに中途失聴・難聴者がたくさん加わって共に活動を担っていたということも大きい)。その場の通訳としての要約筆記も、勿論サークル活動の初期においては中心的な課題として取り組んできたが、要約筆記奉仕員の公的な養成に引き続いて派遣が公的に始まると、サークルとしての中心的な活動を、映画の字幕制作と上映、プラネタリウムの字幕付き上演などに移してきた。そんな活動領域の遷移を予め見越した訳ではないのだろうが、「まごのて」は、発足時に、わざわざ「要約筆記等研究連絡会」として、「等」の文字をサークルの名称に含ませている。サークル活動の始まりの時点では、その場の情報保障だけが特別扱いではなかったことの証左と言えるかも知れない。
1978年12月の設立から今日までの「まごのて」の活動の中で、「聞こえの保障」という広い活動領域があることを実感してきたし、それぞれの活動にそれぞれの専門性があることを実感してきた。「通訳としての要約筆記」だけが抜きんでた専門性を持っている訳ではなく、その活動が一番高度な活動だという訳でもない。「聞こえの保障」を求める領域の一部が、専門性を持った明確な活動領域として取り出された、というだけのこと、そう理解してきた。
自慢する訳ではないが、「まごのて」は、おそらく全国の要約筆記サークルの中で、もっとも沢山の映画の字幕を制作してきたサークルだろう。手書きの字幕から数えれば、100本近い映画の字幕を作ってきている。また、「まごのて」は、もっとも沢山の種類の企画に字幕を付けてきたサークルだろうとも思っている。プラネタリウム(写真上)だけでなく、演劇や、電気文化科学館のシアターなど、さまざまな企画に字幕を付けてきた。ハーフミラーに映して投影される字幕、つまり鏡文字の字幕(写真下)さえ作った経験がある。遡れば、「聴覚障害者の文字放送-字幕放送シンポジウム」にリアルタイムで字幕を付けたのも、身体障害者スポーツ大会とその後夜祭にリアルタイム字幕を付けたのも、名古屋が最初だ。これらの企画は、「まごのて」が単独で実施した訳ではなく、全国の要約筆記者や高速日本語入力者との協働作業として実現したものだが、実現に向けて一定以上の役割を負っていたことも間違いがない。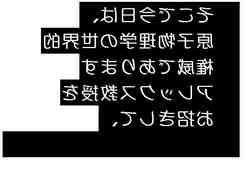
そうした活動の蓄積があったから、逆に、「通訳としての要約筆記」の専門性とその養成カリキュラムの重要性が分かるのかも知れない、と今は思う。「聞こえの保障」のこの広い領域の中で、「通訳としての要約筆記」について、ここまでしっかりした到達目標と養成カリキュラムを作ってこれたのだから、早くこの部分を専門的な活動として認め、社会福祉事業として定着させて欲しいと思わずにはいられない。奉仕員事業が残ることは何の問題もない。しかし、「要約筆記者の派遣事業」は、第2種社会福祉事業として、はっきりと位置づけられ、制度としてこの社会の中に定着されなければならない。どんなに親切なボランティアが身の回りに今いるとしても、あるいは10年後にもいるとしても、そのことと、社会的に利用可能な制度が存在する、ということは、全くその意味が異なる。
「通訳としての要約筆記」の専門性が認められ、その派遣が第2種社会福祉事業として定着する、自立支援法におけるコミュニケーション支援事業として市町村で派遣が必須事業として行なわれる、一日でも早くそうした状況が生まれれば、逆に、残された「聞こえの保障」の領域がもっともっと見えてくるはずだ。私たちにできることは沢山残されている。落語や漫才と言ったエンターテイメントや各種施設でのショー(例えば水族館のイルカショーなど)、あるいは学校教育といった領域で、今なお、沢山の中途失聴・難聴者は、取り残されたままだ。「通訳として要約筆記」を支える制度を「要約筆記者派遣事業」として早く定着させないと、「聞こえの保障」の残された領域は、いつまでも孤立した地域の取り組みとして残されてしまう。それで良いはずはない。
いま、細かく、どこに両団体の意見の不一致、いわゆる齟齬があるのか、説明することはしないが、全国的に見て、なかなか理解されないのが、「聞こえの保障」の広さと、その一部を担う「情報保障」の関係だ。更に言えば、その場の情報を保障する「通訳としての要約筆記」の専門性だろう。前者、つまり「聞こえの保障」と「情報保障」との関係は、前々回詳しく書いた。この問題を巡ってもう一つ、うまく認知ができていないのが、要約筆記者と要約筆記奉仕員の関係だろう。この点については、このブログでも何度か書いている。要約筆記奉仕員の必要性は誰しも認めるところだと思うが、要約筆記奉仕員が大切だから、要約筆記者の養成や認定をいつまでも放置したままにしておくという対応については、私は「間違っている」と考える。なぜ奉仕員事業という制度的にも不安定な事業にいつまでも拠ろうとするのだろうか。
制度の問題はさておき、一つ疑問に思うのは、要約筆記奉仕員にこだわる人は、通訳としての要約筆記以外の聞こえの保障の活動をどの程度した上で、奉仕員で良いといっているのだろうか、ということだ。中失難聴者に対する支援は、「通訳だけでない」とよく言われる。しかし、少なくとも必要とされている支援は、聴覚障害者に代わって電車の切符を買ったり、一緒に旅行に行ったり、飲んだりすることではないだろう。それは支援ではなく、付き合いであるとかお世話であるとか、名付けるとすれば友情であったり、親切であったりする、そういうものだろうと思う。もちろん聴覚障害者とつきあえば、聞こえない故の悩みを聞いたりするとはあるだろう。聴覚障害者の悩みを聞くといった支援も想定することはできる。しかしもしそうした支援をするのであれば、やはりカウンセリング技術の習得など、ある種の専門性が必要になる。単に気持ちがあれば支援できるというものではない。鬱病からの回復期にある患者に、励ますつもりで「もっとがんばって」と言い、病状を悪化させることだってある。「支援者である」というなら、それは「知らなかった」で許されることではないだろう。
中途失聴・難聴者を支援するというのであれば、「聞こえの保障」の領域での支援の必要性が見えないはずないと思う。私が属している名古屋の要約筆記サークル「要約筆記等研究連絡会・まごのて」は、そうした支援の必要性が見えたから、さまざまな支援活動に取り組んできた(サークルに中途失聴・難聴者がたくさん加わって共に活動を担っていたということも大きい)。その場の通訳としての要約筆記も、勿論サークル活動の初期においては中心的な課題として取り組んできたが、要約筆記奉仕員の公的な養成に引き続いて派遣が公的に始まると、サークルとしての中心的な活動を、映画の字幕制作と上映、プラネタリウムの字幕付き上演などに移してきた。そんな活動領域の遷移を予め見越した訳ではないのだろうが、「まごのて」は、発足時に、わざわざ「要約筆記等研究連絡会」として、「等」の文字をサークルの名称に含ませている。サークル活動の始まりの時点では、その場の情報保障だけが特別扱いではなかったことの証左と言えるかも知れない。

1978年12月の設立から今日までの「まごのて」の活動の中で、「聞こえの保障」という広い活動領域があることを実感してきたし、それぞれの活動にそれぞれの専門性があることを実感してきた。「通訳としての要約筆記」だけが抜きんでた専門性を持っている訳ではなく、その活動が一番高度な活動だという訳でもない。「聞こえの保障」を求める領域の一部が、専門性を持った明確な活動領域として取り出された、というだけのこと、そう理解してきた。
自慢する訳ではないが、「まごのて」は、おそらく全国の要約筆記サークルの中で、もっとも沢山の映画の字幕を制作してきたサークルだろう。手書きの字幕から数えれば、100本近い映画の字幕を作ってきている。また、「まごのて」は、もっとも沢山の種類の企画に字幕を付けてきたサークルだろうとも思っている。プラネタリウム(写真上)だけでなく、演劇や、電気文化科学館のシアターなど、さまざまな企画に字幕を付けてきた。ハーフミラーに映して投影される字幕、つまり鏡文字の字幕(写真下)さえ作った経験がある。遡れば、「聴覚障害者の文字放送-字幕放送シンポジウム」にリアルタイムで字幕を付けたのも、身体障害者スポーツ大会とその後夜祭にリアルタイム字幕を付けたのも、名古屋が最初だ。これらの企画は、「まごのて」が単独で実施した訳ではなく、全国の要約筆記者や高速日本語入力者との協働作業として実現したものだが、実現に向けて一定以上の役割を負っていたことも間違いがない。
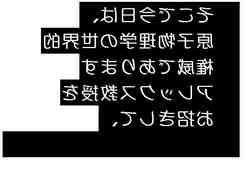
そうした活動の蓄積があったから、逆に、「通訳としての要約筆記」の専門性とその養成カリキュラムの重要性が分かるのかも知れない、と今は思う。「聞こえの保障」のこの広い領域の中で、「通訳としての要約筆記」について、ここまでしっかりした到達目標と養成カリキュラムを作ってこれたのだから、早くこの部分を専門的な活動として認め、社会福祉事業として定着させて欲しいと思わずにはいられない。奉仕員事業が残ることは何の問題もない。しかし、「要約筆記者の派遣事業」は、第2種社会福祉事業として、はっきりと位置づけられ、制度としてこの社会の中に定着されなければならない。どんなに親切なボランティアが身の回りに今いるとしても、あるいは10年後にもいるとしても、そのことと、社会的に利用可能な制度が存在する、ということは、全くその意味が異なる。
「通訳としての要約筆記」の専門性が認められ、その派遣が第2種社会福祉事業として定着する、自立支援法におけるコミュニケーション支援事業として市町村で派遣が必須事業として行なわれる、一日でも早くそうした状況が生まれれば、逆に、残された「聞こえの保障」の領域がもっともっと見えてくるはずだ。私たちにできることは沢山残されている。落語や漫才と言ったエンターテイメントや各種施設でのショー(例えば水族館のイルカショーなど)、あるいは学校教育といった領域で、今なお、沢山の中途失聴・難聴者は、取り残されたままだ。「通訳として要約筆記」を支える制度を「要約筆記者派遣事業」として早く定着させないと、「聞こえの保障」の残された領域は、いつまでも孤立した地域の取り組みとして残されてしまう。それで良いはずはない。
2007年10月29日
洋画の字幕と「要約」
名古屋で要約筆記者養成講座が始まっている(9月5日から)。その講座の中で、先日「日本語の特徴」について教えた。教えるために、日本語と要約筆記の関係をあれこれ検討していて、気づいたことをいくつか。
一つは、これは従来から言ってきたことだが、他人の話を伝達するためには、まずその話を理解することがどうしても必要になる、そして単に理解しただけではまだ伝達にはならず、それを要約筆記者が表現して、初めて伝達行為が完了する、という点に関連している。前者、つまり他人の話を理解するためには消極的知識が必要になる。これは理解するための知識。例えば漢字が読める、言葉の意味が分かる、という知識だ。これに対して後者、つまり理解したものを表現するためには積極的知識が必要になる。これは漢字を例にとれば、要する書けるということ、言葉の意味が分かるだけでなく使える語彙がたくさんあることだ。人の話を伝達するためには、この積極的知識がどうしても必要になる。知識を、「消極的知識」と「積極的知識」に分けるのは、ロシア語通訳者の米原万里さんの著作から私は学んだ。要約筆記者は、通常日本語を母語として育った人だから、消極的知識は十分に持っている。しかし、日本語を母語としている人でも、積極的知識は、意図的に学習しないとなかなか身につかない。これが、要約筆記者が日本語を学ばなければならない第1の理由だ、と講座では話した。
気づいたことの2番目は、要約筆記は第1言語(話しことば)から第2言語(書きことば)に向けて通訳されるということに関連している。その場の情報保障として用いられる要約筆記は通訳行為だと私は思っているが、一般の通訳、要するに異言語間の通訳の場合、通訳者は通常、通訳される対象となっている言語を母語としている人ではなく、通訳されてくる側の言語を母語としている人が行なう。翻訳の方がこの関係はわかりやすいから、翻訳を例にとるが、サリンジャーの英文(第1言語)を日本語(第2言語)に訳すのは日本人(例えば村上春樹氏)だし、源氏物語(日本語=第1言語)を英語(第2言語)に訳すのは、日本人ではなくアメリカ人、例えばサイデンステッカー氏だ。これは最初に挙げた「積極的知識」に関連している。つまり表現するためには積極的知識が豊富であることが要求されるから、通訳(翻訳)される二つの言語のうち、通訳(翻訳)されてくる側の言語(英→日翻訳なら日本語)を母語としている人が担当することになる訳だ。ところが、要約筆記の場合は、通訳されてくる側、つまり書きことばの方が話しことばより得意だという人は少ない。つまり要約筆記者は、通常の異言語間通訳と比べると不利な通訳を強いられている、ということになる。この点からも、要約筆記者を目指す人は、書きことばとしての日本語を学び、書きことばを強化しておかなければならない、ということになる、と話した。
気づいた3番目の内容は、通訳や翻訳においては、「要約」という概念は用いられていないのではないか、ということだ。私たち要約筆記者は、「要約」という言葉を当たり前のよう使う。しかしよく考えてみると、「速く、正しく、読みやすく」という要約筆記の三原則に「要約」という言葉は含まれていない。他方、異言語間の通訳を考えると、そこではどうも「要約」はされていないようなのだ。映画の字幕では、英語の話しことばから日本語の書きことばに向けて翻訳されるが、そこで「要約」をしているという人はいない。仮に話しことばから書きことばへという形で通訳が行なわれる場合に「要約」が必須だというのであれば、英語→日本語であっても、日本語→日本語であっても、そのこと自体は変わりはないはずだ。しかし、前者において、「要約」という意識は見られないし、受け取る我々(例えば、洋画を字幕で楽しむ視聴者)も、そこで行なわれていることが「要約」だとは感じていない、ということだ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
上記の3つの気づきのうち、3番目の話は、「日本語の特徴」とは直接は関係がなかったので、講座では全く触れなかったが、要約筆記という行為の本質を考える上では、かなり重要な示唆ではないかと感じた。そこで以下に少し敷衍してみたい。
日本語字幕の制作者として著名であった清水氏は、ある映画(確か「旅情」)の字幕にふれて、原語にあった「ステーキが食べたくても、ペパロニを出されたらペパロニを食べなさい」という意味の台詞の字幕について悩み、「スパゲティを出されたら、スパゲティを食べなさい」という台詞に訳したという話を書いている。当時(「旅情」の制作は1955年)の日本でのイタリア料理の普及状況を考えると「ペパロニ」では通じない、と考えたからだ。ここで起きていることは、見かけ上は「言い替え」と呼ばれるものだが、実質は、映画鑑賞者(つまり我々)に制作者の意図を伝えるための「通訳(翻訳)行為」だと言えるのではないか。言い換えだけではない。映画の原語に存在する台詞であって字幕化されていない言葉というものも少なくない。しかし、面白いことに、その省略を「要約」ととらえている字幕制作者はどうもいないようなのだ。
 整理すると、洋画の世界では、映画の中の台詞(話しことば)を字幕(書きことば)にしており、そこでは話しことばの逐語訳など行なわれていない。字幕制作者は、映画制作者の意図を映画鑑賞者に伝えるために、省略や言い換えなどを駆使しているが、そのことを「要約」とはとらえていない。字幕制作者は、その行為をおそらく「翻訳の一種」としてとらえているらしい、ということになる。
整理すると、洋画の世界では、映画の中の台詞(話しことば)を字幕(書きことば)にしており、そこでは話しことばの逐語訳など行なわれていない。字幕制作者は、映画制作者の意図を映画鑑賞者に伝えるために、省略や言い換えなどを駆使しているが、そのことを「要約」とはとらえていない。字幕制作者は、その行為をおそらく「翻訳の一種」としてとらえているらしい、ということになる。
映画字幕の翻訳の場合、目指されているものは、次のような行為だと思う。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本語以外の言語の話しことばにより表現された「内容+表現」
↓(時間をかけて作業可能)
「内容+表現」を、日本語の書きことばにより表現
(文字数の制約あり)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これに対して、要約筆記の場合、行なわれているのは(あるいは目指されているのは)、次の行為ではないか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本語の話しことばにより表現された「内容+表現」
↓(その場での作業)
「内容」を中心に、日本語の書きことばにより表現
(文字数の制約あり)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
という関係になる。映画の字幕では、字幕の制作者は、字幕の言語を母語とする人であるのに対して、要約筆記では、書き手は、広い意味では日本語を母語としているものの、書きことばを母語としている訳ではないことを考えると、要約筆記は、やはり相当困難な作業だといえるだろう。私たちは、「日本語の書きことば」を母語として使いこなせるように、相当の研鑽を積まなければならない。
一つは、これは従来から言ってきたことだが、他人の話を伝達するためには、まずその話を理解することがどうしても必要になる、そして単に理解しただけではまだ伝達にはならず、それを要約筆記者が表現して、初めて伝達行為が完了する、という点に関連している。前者、つまり他人の話を理解するためには消極的知識が必要になる。これは理解するための知識。例えば漢字が読める、言葉の意味が分かる、という知識だ。これに対して後者、つまり理解したものを表現するためには積極的知識が必要になる。これは漢字を例にとれば、要する書けるということ、言葉の意味が分かるだけでなく使える語彙がたくさんあることだ。人の話を伝達するためには、この積極的知識がどうしても必要になる。知識を、「消極的知識」と「積極的知識」に分けるのは、ロシア語通訳者の米原万里さんの著作から私は学んだ。要約筆記者は、通常日本語を母語として育った人だから、消極的知識は十分に持っている。しかし、日本語を母語としている人でも、積極的知識は、意図的に学習しないとなかなか身につかない。これが、要約筆記者が日本語を学ばなければならない第1の理由だ、と講座では話した。

気づいたことの2番目は、要約筆記は第1言語(話しことば)から第2言語(書きことば)に向けて通訳されるということに関連している。その場の情報保障として用いられる要約筆記は通訳行為だと私は思っているが、一般の通訳、要するに異言語間の通訳の場合、通訳者は通常、通訳される対象となっている言語を母語としている人ではなく、通訳されてくる側の言語を母語としている人が行なう。翻訳の方がこの関係はわかりやすいから、翻訳を例にとるが、サリンジャーの英文(第1言語)を日本語(第2言語)に訳すのは日本人(例えば村上春樹氏)だし、源氏物語(日本語=第1言語)を英語(第2言語)に訳すのは、日本人ではなくアメリカ人、例えばサイデンステッカー氏だ。これは最初に挙げた「積極的知識」に関連している。つまり表現するためには積極的知識が豊富であることが要求されるから、通訳(翻訳)される二つの言語のうち、通訳(翻訳)されてくる側の言語(英→日翻訳なら日本語)を母語としている人が担当することになる訳だ。ところが、要約筆記の場合は、通訳されてくる側、つまり書きことばの方が話しことばより得意だという人は少ない。つまり要約筆記者は、通常の異言語間通訳と比べると不利な通訳を強いられている、ということになる。この点からも、要約筆記者を目指す人は、書きことばとしての日本語を学び、書きことばを強化しておかなければならない、ということになる、と話した。
気づいた3番目の内容は、通訳や翻訳においては、「要約」という概念は用いられていないのではないか、ということだ。私たち要約筆記者は、「要約」という言葉を当たり前のよう使う。しかしよく考えてみると、「速く、正しく、読みやすく」という要約筆記の三原則に「要約」という言葉は含まれていない。他方、異言語間の通訳を考えると、そこではどうも「要約」はされていないようなのだ。映画の字幕では、英語の話しことばから日本語の書きことばに向けて翻訳されるが、そこで「要約」をしているという人はいない。仮に話しことばから書きことばへという形で通訳が行なわれる場合に「要約」が必須だというのであれば、英語→日本語であっても、日本語→日本語であっても、そのこと自体は変わりはないはずだ。しかし、前者において、「要約」という意識は見られないし、受け取る我々(例えば、洋画を字幕で楽しむ視聴者)も、そこで行なわれていることが「要約」だとは感じていない、ということだ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
上記の3つの気づきのうち、3番目の話は、「日本語の特徴」とは直接は関係がなかったので、講座では全く触れなかったが、要約筆記という行為の本質を考える上では、かなり重要な示唆ではないかと感じた。そこで以下に少し敷衍してみたい。
日本語字幕の制作者として著名であった清水氏は、ある映画(確か「旅情」)の字幕にふれて、原語にあった「ステーキが食べたくても、ペパロニを出されたらペパロニを食べなさい」という意味の台詞の字幕について悩み、「スパゲティを出されたら、スパゲティを食べなさい」という台詞に訳したという話を書いている。当時(「旅情」の制作は1955年)の日本でのイタリア料理の普及状況を考えると「ペパロニ」では通じない、と考えたからだ。ここで起きていることは、見かけ上は「言い替え」と呼ばれるものだが、実質は、映画鑑賞者(つまり我々)に制作者の意図を伝えるための「通訳(翻訳)行為」だと言えるのではないか。言い換えだけではない。映画の原語に存在する台詞であって字幕化されていない言葉というものも少なくない。しかし、面白いことに、その省略を「要約」ととらえている字幕制作者はどうもいないようなのだ。
 整理すると、洋画の世界では、映画の中の台詞(話しことば)を字幕(書きことば)にしており、そこでは話しことばの逐語訳など行なわれていない。字幕制作者は、映画制作者の意図を映画鑑賞者に伝えるために、省略や言い換えなどを駆使しているが、そのことを「要約」とはとらえていない。字幕制作者は、その行為をおそらく「翻訳の一種」としてとらえているらしい、ということになる。
整理すると、洋画の世界では、映画の中の台詞(話しことば)を字幕(書きことば)にしており、そこでは話しことばの逐語訳など行なわれていない。字幕制作者は、映画制作者の意図を映画鑑賞者に伝えるために、省略や言い換えなどを駆使しているが、そのことを「要約」とはとらえていない。字幕制作者は、その行為をおそらく「翻訳の一種」としてとらえているらしい、ということになる。映画字幕の翻訳の場合、目指されているものは、次のような行為だと思う。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本語以外の言語の話しことばにより表現された「内容+表現」
↓(時間をかけて作業可能)
「内容+表現」を、日本語の書きことばにより表現
(文字数の制約あり)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これに対して、要約筆記の場合、行なわれているのは(あるいは目指されているのは)、次の行為ではないか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
日本語の話しことばにより表現された「内容+表現」
↓(その場での作業)
「内容」を中心に、日本語の書きことばにより表現
(文字数の制約あり)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
という関係になる。映画の字幕では、字幕の制作者は、字幕の言語を母語とする人であるのに対して、要約筆記では、書き手は、広い意味では日本語を母語としているものの、書きことばを母語としている訳ではないことを考えると、要約筆記は、やはり相当困難な作業だといえるだろう。私たちは、「日本語の書きことば」を母語として使いこなせるように、相当の研鑽を積まなければならない。
2007年10月28日
「聞こえの保障」と「情報保障」
このブログでしばしば「聞こえの保障」という言い方をしてきた。これに対して、最近は「情報保障」ということが多い。「聞こえの保障」と「情報保障」とは何が違うのだろうか。このことを考えるためには、まず「情報」とは何か、ということを明確にする必要がある。
「情報」という言葉は便利なので気軽に使うが、よく考えるとなかなか定義することが難しい。人間が五感で感じるもの(知覚や感覚)であっても、広く「情報」と呼べないことはない。しかし、「情報保障」という場合の「情報」は、人の判断や行動の意志決定をするために役立つものを意味している。では、人の判断や行動の意志決定をするにめに役立つものがすべて「情報」かというと、必ずしもそうは言えない。「情報」とは、人の判断や行動の意志決定をするにめに役立つもののうち、その場でもたらされ、その場で必要になるものを意味していることが多い。時間が経てば、判断や行動の意志決定に役立たなくなることも多いからだ。台風で大雨が降り、河川が決壊しそうだというとき、自宅近くの川の水位や地域の降雨量などは重要な情報になる。避難するかどうかの判断の材料になるからだ。しかし、数日前のその川の水位や、あるいは今日の水位であっても遠く離れた河川の水位は、情報としてはあまり意味を持たない。この場での自らの判断や行動の意志決定のために使えないからだ。
 では時間に関係なく、いつでも役に立つというものはないのだろうか。もちろんある。通常そうしたものは「知識」と呼ばれるのではないだろうか。「この辺りは去年の台風でも水に浸かった」という知識があり、「今日の降雨量は、去年の台風並」という情報が入ってきて、「では、早めに避難所に避難しよう」という判断が生まれる。避難所の場所も、広域避難所として予め知らされている場合は「知識」として役立つし、町内会の組長さんが「今日は○○に避難して」と教えにきてくれれば、「貴重な情報をありがとう」ということになる。
では時間に関係なく、いつでも役に立つというものはないのだろうか。もちろんある。通常そうしたものは「知識」と呼ばれるのではないだろうか。「この辺りは去年の台風でも水に浸かった」という知識があり、「今日の降雨量は、去年の台風並」という情報が入ってきて、「では、早めに避難所に避難しよう」という判断が生まれる。避難所の場所も、広域避難所として予め知らされている場合は「知識」として役立つし、町内会の組長さんが「今日は○○に避難して」と教えにきてくれれば、「貴重な情報をありがとう」ということになる。
まとめると、「情報」とは、人の判断や行動の意志決定に役立つものであり、その場でもたらされ、その場で役立つもの、ということができる。
こう考えれば、「情報保障」とは、人が判断したり行動の意志決定をしたりするために、その場でもたらされるべきものを保障すること、を意味していることが分かる。ちなみに「保障」とは、本来あるべきものが守られている状態を指している。これが一度失われたものをつぐなうという意味の「補償」との差異だ(したがって、「安全保障条約」は安全な状態を守るためであり、「戦時補償」は戦時の損失を補うため、と理解できる)。
「聞こえの保障」は、聞こえることすべてを、本来あるように守りたいという意味になる。聞こえることすべてが「情報」として、人の判断や行動の意志決定のために用いられる訳ではない。私たちは、音楽も聴くし落語も楽しむ。それらは、私たちの聞こえの世界を形作ってはいるが、通常は「情報」としては扱われていない。したがって、聴覚障害者にとって聞こえの保障を求めるとは、「情報」も「情報でないもの」も等しく、つまり音声として聞こえているものを、聞こえる人が感じ、理解できるように、同じように感じ、理解したい、という要求だと言うことだ。その要求は、基本的人権の上に立つものであり、人として当然のものだということができる。しかし、現実には、すべてを直ちに保障することは難しい。技術的に難しいという場合もあるし、財政的に困難ということもある。テレビ放送の字幕を例にとれば、生中継などは、字幕の作成が困難として、2007年までの字幕化の対象とはなっていない。
いずれにせよ、この社会にあって、本来実現されるべきことであっても、優先順位を付けて取り組まざるを得ないことは多い。何十年も前に建造され、現在の耐震基準を満たさない建物であっても、直ちに使用中止とされたり取り壊されたりするわけではなく、一定の猶予期間のうちに耐震工事がなされるように義務づけられるにとどまっている。もっと言えば、「人命は地球より重い」と言いながら、交通事故で年間数千人が死亡するという事態は何十年も完全には解決されないままだ。そこには、現在の社会のあり方を前提として、優先順位を付けて取り組むという対応がある。社会的に「そうすべきだ」という強い合意ができないものは、後回しにされてしまう。
テレビ放送の完全字幕化などは、すでに技術的な問題は解決可能な状況にあるから、最後は予算の問題だと言って良いだろう。中途失聴・難聴者の運動が力強いものになって初めて、完全字幕化は、この社会での優先順位が上がることになる。
では、「聞こえの保障」の全体ではどう考えたらよいのだろうか。本来は、そのすべてが早期に保障されるべきものであるとしても、現実には優先順位を付けざるを得ない。とすれば、「聞こえの保障」の全領域のなかで、優先されるべきは「情報保障」の部分だろう。なぜなら、それは、聴覚障害者が、自ら判断し自らの行動の意志決定するために必要な情報を保障することだからだ。ここが支えられなければ、聴覚障害者は自ら判断し、自らの行動の意志決定を十全に行なうことが困難になる。いくらスポーツ中継や落語番組に字幕を付けたところで、聴覚障害者の判断や、その行動の意志決定を支えることはできない。逆に言えば、情報保障があれば、聴覚障害者は自らの行動の意志決定を行ない、それこそ、テレビ放送の完全字幕化の運動に立ち上がることもできるのだ。
これが、手話通訳や要約筆記が、第二種社会福祉事業として位置づけられている(社会福祉法第2条第3項第5号)理由であり、聴覚障害者のコミュニケーション支援事業が、市町村の必須事業とされている(障害者自立支援法第77条第1項第2号)理由だと私は思う。スポーツや文化の享受がないがしろにされて良い訳ではない。しかし、現在の日本の社会は、そこに優先順位を付け、「情報保障」を含む「コミュニケーション支援」については、規制と助成を通じて(社会福祉事業)、必ず実現すべきものとして(必須事業)、法律に規定したということができる。
では、「聞こえの保障」のうち、「情報保障」以外の部分、もっと広く言えば「コミュニケーション支援」以外の部分は、どのように扱われているのだろうか。この点は、また別にまとめることにしよう。
「情報」という言葉は便利なので気軽に使うが、よく考えるとなかなか定義することが難しい。人間が五感で感じるもの(知覚や感覚)であっても、広く「情報」と呼べないことはない。しかし、「情報保障」という場合の「情報」は、人の判断や行動の意志決定をするために役立つものを意味している。では、人の判断や行動の意志決定をするにめに役立つものがすべて「情報」かというと、必ずしもそうは言えない。「情報」とは、人の判断や行動の意志決定をするにめに役立つもののうち、その場でもたらされ、その場で必要になるものを意味していることが多い。時間が経てば、判断や行動の意志決定に役立たなくなることも多いからだ。台風で大雨が降り、河川が決壊しそうだというとき、自宅近くの川の水位や地域の降雨量などは重要な情報になる。避難するかどうかの判断の材料になるからだ。しかし、数日前のその川の水位や、あるいは今日の水位であっても遠く離れた河川の水位は、情報としてはあまり意味を持たない。この場での自らの判断や行動の意志決定のために使えないからだ。
 では時間に関係なく、いつでも役に立つというものはないのだろうか。もちろんある。通常そうしたものは「知識」と呼ばれるのではないだろうか。「この辺りは去年の台風でも水に浸かった」という知識があり、「今日の降雨量は、去年の台風並」という情報が入ってきて、「では、早めに避難所に避難しよう」という判断が生まれる。避難所の場所も、広域避難所として予め知らされている場合は「知識」として役立つし、町内会の組長さんが「今日は○○に避難して」と教えにきてくれれば、「貴重な情報をありがとう」ということになる。
では時間に関係なく、いつでも役に立つというものはないのだろうか。もちろんある。通常そうしたものは「知識」と呼ばれるのではないだろうか。「この辺りは去年の台風でも水に浸かった」という知識があり、「今日の降雨量は、去年の台風並」という情報が入ってきて、「では、早めに避難所に避難しよう」という判断が生まれる。避難所の場所も、広域避難所として予め知らされている場合は「知識」として役立つし、町内会の組長さんが「今日は○○に避難して」と教えにきてくれれば、「貴重な情報をありがとう」ということになる。まとめると、「情報」とは、人の判断や行動の意志決定に役立つものであり、その場でもたらされ、その場で役立つもの、ということができる。
こう考えれば、「情報保障」とは、人が判断したり行動の意志決定をしたりするために、その場でもたらされるべきものを保障すること、を意味していることが分かる。ちなみに「保障」とは、本来あるべきものが守られている状態を指している。これが一度失われたものをつぐなうという意味の「補償」との差異だ(したがって、「安全保障条約」は安全な状態を守るためであり、「戦時補償」は戦時の損失を補うため、と理解できる)。
「聞こえの保障」は、聞こえることすべてを、本来あるように守りたいという意味になる。聞こえることすべてが「情報」として、人の判断や行動の意志決定のために用いられる訳ではない。私たちは、音楽も聴くし落語も楽しむ。それらは、私たちの聞こえの世界を形作ってはいるが、通常は「情報」としては扱われていない。したがって、聴覚障害者にとって聞こえの保障を求めるとは、「情報」も「情報でないもの」も等しく、つまり音声として聞こえているものを、聞こえる人が感じ、理解できるように、同じように感じ、理解したい、という要求だと言うことだ。その要求は、基本的人権の上に立つものであり、人として当然のものだということができる。しかし、現実には、すべてを直ちに保障することは難しい。技術的に難しいという場合もあるし、財政的に困難ということもある。テレビ放送の字幕を例にとれば、生中継などは、字幕の作成が困難として、2007年までの字幕化の対象とはなっていない。
いずれにせよ、この社会にあって、本来実現されるべきことであっても、優先順位を付けて取り組まざるを得ないことは多い。何十年も前に建造され、現在の耐震基準を満たさない建物であっても、直ちに使用中止とされたり取り壊されたりするわけではなく、一定の猶予期間のうちに耐震工事がなされるように義務づけられるにとどまっている。もっと言えば、「人命は地球より重い」と言いながら、交通事故で年間数千人が死亡するという事態は何十年も完全には解決されないままだ。そこには、現在の社会のあり方を前提として、優先順位を付けて取り組むという対応がある。社会的に「そうすべきだ」という強い合意ができないものは、後回しにされてしまう。
テレビ放送の完全字幕化などは、すでに技術的な問題は解決可能な状況にあるから、最後は予算の問題だと言って良いだろう。中途失聴・難聴者の運動が力強いものになって初めて、完全字幕化は、この社会での優先順位が上がることになる。

では、「聞こえの保障」の全体ではどう考えたらよいのだろうか。本来は、そのすべてが早期に保障されるべきものであるとしても、現実には優先順位を付けざるを得ない。とすれば、「聞こえの保障」の全領域のなかで、優先されるべきは「情報保障」の部分だろう。なぜなら、それは、聴覚障害者が、自ら判断し自らの行動の意志決定するために必要な情報を保障することだからだ。ここが支えられなければ、聴覚障害者は自ら判断し、自らの行動の意志決定を十全に行なうことが困難になる。いくらスポーツ中継や落語番組に字幕を付けたところで、聴覚障害者の判断や、その行動の意志決定を支えることはできない。逆に言えば、情報保障があれば、聴覚障害者は自らの行動の意志決定を行ない、それこそ、テレビ放送の完全字幕化の運動に立ち上がることもできるのだ。
これが、手話通訳や要約筆記が、第二種社会福祉事業として位置づけられている(社会福祉法第2条第3項第5号)理由であり、聴覚障害者のコミュニケーション支援事業が、市町村の必須事業とされている(障害者自立支援法第77条第1項第2号)理由だと私は思う。スポーツや文化の享受がないがしろにされて良い訳ではない。しかし、現在の日本の社会は、そこに優先順位を付け、「情報保障」を含む「コミュニケーション支援」については、規制と助成を通じて(社会福祉事業)、必ず実現すべきものとして(必須事業)、法律に規定したということができる。
では、「聞こえの保障」のうち、「情報保障」以外の部分、もっと広く言えば「コミュニケーション支援」以外の部分は、どのように扱われているのだろうか。この点は、また別にまとめることにしよう。
2007年10月21日
不自由さの自由
以前に「時代小説は窮屈な小説だ」と書いた。窮屈な小説の対極にあるのが、コミックだなーと思っていた。何しろ非現実的なことでも自由に起こして良いのがコミックだから。四次元ポケットとかどこでもドアなんてものが、平気で描ける。コミックは、一人で監督から俳優から大道具までできる。だから、1970年代以降、日本の映画会社が、助監督制度を廃して監督の養成をやめてしまった後、本来なら映画監督になった才能は、コミック(漫画)に流れた、という説があるくらいだ。例えば、「童夢」や「AKIRA」の大友克洋などは、映画監督の道があれば、きっと監督になっていたのではないか。コミックなら、自分一人で何でもできる、自由にできる。
 しかし本当にそうだろうか。「地平線でダンス」という奇妙なコミックがある。あらすじを書いたら、読んだ人は、何が面白いんだろうと不思議になるかも知れない。でも面白い。どうしてこの作品が面白いのか、と考えているうちに、面白いコミックに存在するある種の共通点に気づいた。それはコミックにおける不自由さ、ということだ。
しかし本当にそうだろうか。「地平線でダンス」という奇妙なコミックがある。あらすじを書いたら、読んだ人は、何が面白いんだろうと不思議になるかも知れない。でも面白い。どうしてこの作品が面白いのか、と考えているうちに、面白いコミックに存在するある種の共通点に気づいた。それはコミックにおける不自由さ、ということだ。
コミック(漫画)は、確かにきわめて自由なメディアだ。実写ではないから、どんな世界でも描ける。月世界の宇宙基地もリアルに描けるし、火の鳥だって描ける。潜水艦の中でも、登場人物の内面のつぶやきだって、書ける。そういう自由なメディアだからこそ、おそらく面白いコミックを作るためには、作品の中に、不自由さがなければならない。
「地平線でダンス」では、タイムトラベルを試みる機械に誤って実験動物のハムスターに閉じこめられて、主人公である春日琴理(素粒子加速器研究所研究員)はハムスターになってしまう。意識は本人だが、身体はハムスターだ。したがって、とても不自由。その後、彼女は今度は犬になるが、本質は変わらない。元(?)研究員の彼女は、タイムトラベルの理論を支える高等な数式を解くが、それを人間の研究員に伝えるのは一苦労だ。恋もしている。とても不自由に。
かつて「ナニワの金融道」という傑作があった。このコミックでは、街金という非合法すれすれの金融業者のところに就職した比較的まじめな主人公が、どう生きるか、というテーマの元で、様々な街金のテクニックが披露される。先物取引に嵌り、保証金の追い金が必要なり、街金に借りに来て、だんだんは深みに嵌っていく客。その客から、合法的に、財産をむしり取っていく。ただの悪徳業者の実態を描くというのであれば、この「ナニワの金融道」が傑作になったはずはない。街金の舞台に、まじめに生きたいと願う灰原という主人公を置く。名前からして、白でもなければ黒でもない彼の不自由さがあって初めてこの作品は活きたのだと思う。
浦沢直樹の「PLUTO」の不自由さは、手塚治虫の原作があることか。曽田正人の「昴」の不自由さは、主人公・宮本昴の社会性のなさか。などと考えるのは楽しい。コミックは今なお、その表現の領域を拡大中だが、面白いコミックは、優れた不自由さが仕込まれている。
 しかし本当にそうだろうか。「地平線でダンス」という奇妙なコミックがある。あらすじを書いたら、読んだ人は、何が面白いんだろうと不思議になるかも知れない。でも面白い。どうしてこの作品が面白いのか、と考えているうちに、面白いコミックに存在するある種の共通点に気づいた。それはコミックにおける不自由さ、ということだ。
しかし本当にそうだろうか。「地平線でダンス」という奇妙なコミックがある。あらすじを書いたら、読んだ人は、何が面白いんだろうと不思議になるかも知れない。でも面白い。どうしてこの作品が面白いのか、と考えているうちに、面白いコミックに存在するある種の共通点に気づいた。それはコミックにおける不自由さ、ということだ。コミック(漫画)は、確かにきわめて自由なメディアだ。実写ではないから、どんな世界でも描ける。月世界の宇宙基地もリアルに描けるし、火の鳥だって描ける。潜水艦の中でも、登場人物の内面のつぶやきだって、書ける。そういう自由なメディアだからこそ、おそらく面白いコミックを作るためには、作品の中に、不自由さがなければならない。
「地平線でダンス」では、タイムトラベルを試みる機械に誤って実験動物のハムスターに閉じこめられて、主人公である春日琴理(素粒子加速器研究所研究員)はハムスターになってしまう。意識は本人だが、身体はハムスターだ。したがって、とても不自由。その後、彼女は今度は犬になるが、本質は変わらない。元(?)研究員の彼女は、タイムトラベルの理論を支える高等な数式を解くが、それを人間の研究員に伝えるのは一苦労だ。恋もしている。とても不自由に。
かつて「ナニワの金融道」という傑作があった。このコミックでは、街金という非合法すれすれの金融業者のところに就職した比較的まじめな主人公が、どう生きるか、というテーマの元で、様々な街金のテクニックが披露される。先物取引に嵌り、保証金の追い金が必要なり、街金に借りに来て、だんだんは深みに嵌っていく客。その客から、合法的に、財産をむしり取っていく。ただの悪徳業者の実態を描くというのであれば、この「ナニワの金融道」が傑作になったはずはない。街金の舞台に、まじめに生きたいと願う灰原という主人公を置く。名前からして、白でもなければ黒でもない彼の不自由さがあって初めてこの作品は活きたのだと思う。
浦沢直樹の「PLUTO」の不自由さは、手塚治虫の原作があることか。曽田正人の「昴」の不自由さは、主人公・宮本昴の社会性のなさか。などと考えるのは楽しい。コミックは今なお、その表現の領域を拡大中だが、面白いコミックは、優れた不自由さが仕込まれている。
2007年10月12日
通訳としての要約筆記−承前
 前回、要約筆記が通訳として機能させることを困難にした理由について、私の考えるところを書いた。では、なぜ要約筆記は通訳として機能しなければならないのか、そのためには何が必要なのか、について考えるところを書いてみたい。
前回、要約筆記が通訳として機能させることを困難にした理由について、私の考えるところを書いた。では、なぜ要約筆記は通訳として機能しなければならないのか、そのためには何が必要なのか、について考えるところを書いてみたい。前者については、すでに何度かこのブログに書いてきたが、要するに、要約筆記の目的をその場の情報保障に求めたからだ。9月20日付けのブログ「聞こえの保障と要約筆記」に表として示したものを再掲する。
横軸:前もって準備できるものか、その場で対応するしかないものか
縦軸:話の内容が重要か、どんな風には話されたかといった表現が重要か
内容が重要
☆ ↑ ★ 会議
事 | 講演
前 ◆映画 プラネタリウム
に←————————┼——————→その場で発言
準 芝居 |
備 |
落語 ↓
表現が重要
(等幅フォントで表示してください)
要約筆記が用いられる対象を、その場で話されるものであり、内容を重視するもの、と考えると、伝えるべきは内容であって、どのような話されたか、といった側面は後回しにせざる得ない。これも繰り返しになるが、聴覚障害者に対する情報保障のすべての領域に対して、私は「通訳として」の行為が必要になると言っているのではない。この表の中で言えば、「通訳としての要約筆記」が求められる領域は右上のわずかな部分だ。それ以外の領域、例えば映画の情報保障は、「通訳として」の行為ではない。また、内容よりもその表現を重視する領域(図の下方)でも、「通訳として」の行為だけでは対応できない。
しかし、この図の右上の領域については、逆に通訳としての要約筆記でなければ対応できないと考えている。というか、この領域で、聴覚障害者を本当の意味で支援するためになされている行為を、「通訳として要約筆記」と呼んでいるということなのだ。その場で話されている内容をその場の参加者に伝え、その場の参加者が、伝えられたものによって自らの考えをまとめ、判断し、参加できる、そのための情報保障の姿はどのようなものか、それが問われているのだ。
このとき、伝えるべきは、まずなにより内容だ。話題となっている事項に対する話し手の意見や、話し手の立場、つまり賛成か反対かが問われているのであって、大阪弁で意見を言ったか、あるいは賛成したか名古屋弁で反対したかが問われている訳ではない。次に、伝達行為の遅れには許容限度があることも大きい。要約筆記を使う聴覚障害者の、その場への参加を保障しようとすれば、遅れは、話し終わりから、10秒程度までしか許容されないことが多いだろう。これらの条件を満たそうとすれば、要約筆記者が行なう行為は、話し手の言葉ではなく、話し手が自らの話で伝えようと願った意図を、できる限り短い書きことばで、再現しようとする行為以外考えられない。にもかかわらず、要約筆記者が、話し手の使った言葉を大切にしようとする理由は何だろうか。畢竟、話し手の言葉は、話し手が自らの言葉で伝えようと願ったものをよく表わしているという理解ではないか。しかし、言葉を丸ごと再現できない限り、話し手の言葉それ自体が、話し手の伝えようとした意図を最もよく伝えることにならないのだ。
相手との関係を配慮して、例えば「あまりお引き留めして、後のご予定に差し支えては、と心配しておりますが。」と話したとき、その配慮の気持ちは、そこで用いられた言葉のすべてを、百歩ゆずっても大部分を再現しない限り、十全には再現されないし、伝えられない。書き取れる文字数の制約があるとき、話し手の言葉を使って、「お引き留めしては?」とか、「心配しておりますが?」とだけ要約筆記の画面に書かれたとすれば、話し手の意図は、伝わらない可能性が高い。まして「あまりお引き留めして」まで書いて後が書けなければ、なにも伝わらない。この例で言えば、「退席されては?」と書いた方が、話し手の意図は少なくとも伝わるはずだ。
その場の情報をその場で保障する、しかも内容を重視して伝える、という場面に限れば、要約筆記は、話し手の意図の伝達をその使命とすることは明らかではないだろうか。話し手の意図の伝達という目的、そのために、第一の言語形態(ここでは話しことば)によって語られた話し手の意図を、第二の言語形態(ここでは書きことば)によって伝えようとする、と考えれば、これは言語間の通訳が目指すものとなんら変わりはない。第一の言語形態に例えば英語を、第二の言語形態に例えば日本語を、それぞれ入れてみれば、これは明らかだろう。要約筆記は、この意味で、「通訳」と呼んで差し替えない。

では、第一の言語形態(ここでは話しことば)によって語られた話し手の意図を、第二の言語形態(ここでは書きことば)によって伝えること、結果的に、話し手の意図を伝達するという目的は、どのようにして達成されるのか。その問いに対する回答として、全難聴が2005年度の要約筆記に関する調査研究事業でまとめた「要約筆記者養成カリキュラム」とそのテキスト以上のものを、現時点では私は知らない。このカリキュラムの背後には、十分とは言えないが、それまで誰も取り組まなかった話しことばに対する実証的な検討がある。日本語の話しことばの運用に対して、その話され方がどのような意図に基づくのかという検討がある、同じ内容をより短く表現する場合の原則と例外を類型化しようとした取り組みがある。そこを見て取らなければ、この「要約筆記者養成カリキュラム」を理解したことにはならない。
2000年以降に、主に東京で、個人名をあげれば、東京の要約筆記者である三宅初穂氏によって行なわれたこの実証的な検討は、それまで誰も取り組まなかった類のものだ。おそらくは、話しことばの録音と、実際に書かれた要約筆記のシートを使ってなされたその考証は、日本語を普通に使っている人の気づきや思いつきのレベルを越えて、話しことばによる意図の伝達の仕組みに迫る初めての取り組みになった。
通訳としての要約筆記、つまり聞こえない人、聞こえにくい人の権利擁護のために役立つ要約筆記を実現しようとする私たちに求められているのは、この実証的な検討を押し進めることだ。三宅氏は、その検討の成果を「話しことばの要約」(発行:杉並要約筆記者の会「さくらんぽ」)など何冊かの本にまとめて上梓されているが、実証的な検討それ自体はほとんど明らかにしていない。しかし、実際に行なわれたその実証的検討の内容と意味を知り、その道を、要約筆記者を養成しようとする者が通らないと、「通訳としての要約筆記」は、本当の意味では成熟しないのではないか。三宅氏の取り組みの成果だけを学ぶのではなく、その取り組みの課程を学ばなければ、本当のところで、話し手の意図を、手書きの書きことばによって通訳する道は、拓けない。
2007年10月09日
要約筆記と通訳行為(補遺)
 先に、要約筆記が通訳として認められにくかった理由として3つの観点から整理した。その2番目、3番目として、
先に、要約筆記が通訳として認められにくかった理由として3つの観点から整理した。その2番目、3番目として、[2]要約筆記を利用する人の要望
[3]話しことばと書きことばの速さのギャップの前で
の二つを挙げた。しかし私はここで、誰かの責任を問おうとしている訳ではない。中途失聴者・難聴者が、音から隔てられていると感じ、要約筆記に対して、言葉それ自体の回復を求めたとしても、それは自然なことだと思う。その要望それ自体か間違っているとは全く思わない。ろう者は手話を母語にしている。私たち、日本語を母語として育った者が日本語を誤らないように、手話を母語として育った人は手話を誤らない。しかし、中途失聴者・難聴者は、要約筆記を母語として育つ訳ではない。ここに、手話と要約筆記の決定的な違いがある。
中途失聴者・難聴者の要望は、要望として存在するし、それはいつか、技術の発展と支援の形の充実によって、満たされる日が来ると私は思う。現在のパソコン要約筆記では、まだその要求に十分に応えることはできないが、いずれその要望に応える機械か活動が生まれるだろう。しかし、手書きの要約筆記は、その要望に応えられるものではない。どんなにがんばっても、話すように書くことはできない。それだけのことだ。
しかし、中途失聴者・難聴者の聞こえの保障を求める要求のうち、ある部分は、手書き要約筆記以外にこれを支援する方法はなかったのだ。そして現在でも、手書き要約筆記が対応しなければならない領域はまだまだ広い。その要望に応える方法は、隔てられた音をそのまま回復することではなく、話し手の意図したもの、話し手が伝えようと願った内容(概念)を、書き取ることができる文字数の中で、明快に伝えていく、そういう方法だったということだと思う。中途失聴者・難聴者の要望を聞き届け、しかし現実に可能な支援を構築していく、そういうことが試みられたのだ。良い悪いの問題ではなく、その支援の形が、なかなか「通訳行為」として整理できなかった、ということに過ぎない。
また、要約筆記奉仕員養成講座で養成された要約筆記奉仕員が、話しことばと格闘して、話しことばの性質を十分には検討できなかったとしても、それは要約筆記奉仕員の責任ではない。もともと奉仕員に、そうした責務が課されていた訳では全くなかったのだから。
むしろ課題は、要約筆記奉仕員という形にいつまでもとどまって、話しことばと本気で格闘する人を育てなかった点にある。要約筆記の専門性、というのであれば、ただ単に、50時間程度の講座を受けたことをもって「専門性」と呼ぶのではない。訓練しないかぎりできないことをする、というのが専門性の最初の意味のはずだ。そしてその次に、通訳行為への意図的な取り組みがくる。全難聴の要約筆記に関する調査研究事業が、「要約筆記者」の到達目標として掲げた「「通訳」という行為に対する自覚的な理解をしていること」とは、まさにこのことを伝えようとしている。
要約筆記奉仕員が育つ中、先を見通して、話しことばと格闘する人を育てる必要があったと言えるだろう。
繰り返しになるが、犯人捜しは全く本意ではない。要約筆記の短からぬ歴史の中で、できたこと、できなかったことを整理しておきたい。整理して、見通しを作ることで、次のステップに進める。そう思っている。
2007年10月09日
要約筆記と通訳行為−その2
このブログを始めて間もない頃に、「どうして要約筆記は通訳として認められにくいのか」という問いを立ててそのままにしている(8月26日付け、「要約筆記の現状」参照)。今日は少しこの点を整理してみたい。要約筆記が通訳として認められにくかったのは、大きく分けて三つの理由があったと私は考えている。
一つは、要約筆記が日本語間のやりとりを媒介しているために、通訳としての側面が見にくかったということ。もう一つは、要約筆記を利用する中途失聴・難聴者の要望。そして最後が、要約筆記者自身が、話し言葉の速さにどうしても目を奪われて、他人の話を媒介するという作業の本質に対して十分に迫れなかったこと、だ。順を追って説明したい。
[1]日本語間のやりとりである、ということ
まず要約筆記が日本語間のやりとりを媒介するから、という点だが、これは異言語間の通訳と比較するとわかりやすい。もともと異言語間通訳は、いわゆる逐語訳ではつとまらない。このことは異なる二つ以上の言語を少し扱った経験のある人ならすぐに了解される。分からない単語のすべてについて辞書を引いて、単語の意味が分かったとしても、文を正しく訳すことはできない。まして達意の言葉にして通訳することはできない。
例として、言語学者の鈴木孝夫氏がその著書「日本語と外国語」(岩波新書)で挙げたフランス語における「オレンジ色の封筒」という表現を取り上げてみよう。鈴木孝夫氏は、この表現に接して、あるとき、フランス人にとって「オレンジ」という色は、我々日本人にとっての「茶色」を含むのだと気づく。つまり「オレンジ色の封筒」とは「茶封筒」のことだったのだ。日本では虹は七色だが、世界中で虹を七色と数えている国は少ない。ヨーロッパでは、「リンゴのような頬の女の子」とは青白い病弱なイメージを喚起する。したがって、異言語間の翻訳や通訳は、言葉に沿って訳す逐語訳ではなく、話し手が言おうとしたことを理解して伝えるという作業が絶対に必要になる。言葉のままに訳したのでは、意味が伝わらず、場合によっては誤解や行き違いを生じるからだ。実際、「オレンジ色の車でお迎えに参ります」と言われた鈴木孝夫氏は、いつまでたったも現われないオレンジ色の車を、茶色の車の傍らで待ち続けたという。異言語間の通訳は、こうした文化的な読み替え、言い替えの上に成り立っている。「言い替え」と書いたが、それは「替える」のではなく、本当は、話し手が伝えたいと願ったことを、通訳者が理解し、理解したものを、聞き手(読み手)が使う言語の世界で表現する行為なのだ。
これに対して、要約筆記は同じ日本語間で話を媒介するものだ。話し手が、頬の紅い健康的な女の子をイメージして「リンゴのような頬の女の子」と言えば、聞き手にも同じイメージが喚起されると期待することができる。話し手が「オレンジ色の車」と言えば、確かにオレンジ色の車がお迎えに来るだろう。であれば、話し手の言葉をそのまま使えばよい、話し手の言葉と異なる言葉を使うべきではない、と要約筆記者が考えたとして不思議はない。話し手の言葉をできるだけ生かして話を伝えるとは、この間の消息を伝えるものだ。

[2]要約筆記を利用する人の要望
第二の理由、要約筆記を利用する中途失聴者・難聴者の要望はどうだろうか。これには更に二つの側面がある、と私は考えている。一つは、音から隔てられた中途失聴者・難聴者の心情、もう一つは、話し手としての中途失聴者・難聴者の心情、だ。中途失聴者は、人生の途中で聴力を失ったから、それまでは音声が聞こえていたことになる。したがって、音は最初から失われていた訳ではなく、音はあり、そこから隔てられていると感じているのではないだろうか。難聴者の受けとめ方も似ているのでないだろうか。1975年に岩波新書の一冊として発行された「音から隔てられて」(編集・入谷仙介、林瓢介)という書籍の書名は、この中途失聴者・難聴者の心情を端的に表わしていると、と私は感じてきた。中途失聴者・難聴者にとって、隔てられている音声を回復したい、という要望は当然のことだ。補聴器が、隔てられている音声を、音声のまま少しでも取り戻そうとする装置である考えられるとすれば、音声を文字化することで、これを取り戻そうという利用の仕方を要約筆記に求めるということがあったのではないか。聞き取りにくい言葉を時に補聴器が明確にするように、聞き取りにくい言葉を要約筆記のスクリーンに求めて明確にしようする、そういう利用の立場から言えば、話し手の使った言葉はそのままスクリーンに現われて欲しいはずだ。
もう一つ、話し手もまた中途失聴者・難聴者だったとはどういうことだろうか。要約筆記が当初使われた場面は、中途失聴者・難聴者の会合、例えば典型的には、中途失聴者難聴者協会の例会などだった。そうすると要約筆記の利用者は、同時に、要約筆記における話し手でもあったのだ。したがって、要約筆記の現場では、話し手も中途失聴・難聴者、それを見ているのも中途失聴・難聴者だった。話し手からすれば、自分の使った言葉が使われない、というのは不満になる。話し手には、その言葉を使って物事を伝えたいという気持ちがある。その気持ちがあるからその言葉が選択されたのだといえる。例えば、相手に対して十分な気遣いをして、「あまりお引き留めして、後のご予定に差し支えては、と心配しておりますが」と話したとき、要約筆記の画面に例えば「退席されては?」と書かれると、「自分はこんな言い方はしなかった、こんな直接的な言い方では失礼に当たらないか」と感じてしまう、ということは、話すことに対して意識的な話し手であればあるほど、起きるはずだ。自分の話したままに書いて欲しい、と話し手である中途失聴者・難聴者が感じ、そのように要望したとしても不思議ではない。
要約筆記者は、聴覚障害者、とりわけ中途失聴者・難聴者を支援しようという気持ちで活動をしている立場だから、中途失聴者・難聴者の要望に耳を傾け、その要望を尊重したいと考えるだろう。「音から隔てられて」いる気持ちに立って、音声それ自体を取り戻したいという要望、話し手である中途失聴・難聴者の、言葉に託した自らの心情をそのまま伝えるために、託した言葉自体を書いて欲しいという要望、要約筆記者は、それらに応えようとしてきたのだと言える。それが、話し手の話の内容を伝える、つまり通訳としての要約筆記ではなく、話し手の言葉を生かした要約筆記という目標を掲げる理由につながったのではなかったか。
[3]話しことばと書きことばの速さのギャップの前で
最後に、話しことばと書きことばの速さの違いという問題がある。一般に話しことばの速度は1分間に300字程度とされ、他方、手書きの速度は1分間にせいぜ60字程度だとされる。書き取ることができる文字数は話しことばの約20パーセントでしかない。私たち要約筆記者はその速度のあまりに大きな違いの前で、どのようにこの差異を乗り越えるかという点について、十分な検討ができなかったように私は思う。もちろん、全要研集会では毎年のように「技術」の分科会がもたれ、その主要なテーマは「要約」の技術であり、研究誌にも要約をめぐるたくさんの論考が掲載されてきた。はやく1994年発行の研究誌第5号、翌年の第6号には、ユニークな要約の技術的な考察が掲載されている。しかし、それらの研究が、その後の要約筆記における要約の研究の発展には、うまく結びつかなかった。それはなぜか。
思うに、私たち要約筆記者は、話しことばと十分な格闘をしなかったのだ。要約筆記者、当時の要約筆記奉仕員は、一般の人がボランティアである奉仕員の養成講座を受けることで養成される。当然、日本語の研究者ではないから、「要約」について関心をもっても、なかなか実証的な検討をするところまで至らない。いわゆる素人の思いつきの域をでることが難しいのだ。
日本語の普通の使い手として、日本語に関してものを言うことは難しくない。例えば、「○○しないこともない。」という二重否定文に出会えば、これを「○○する。」と言い得る、ということは気づくだろう。しかし、日本語の中で二重否定文が使われる理由、その場合のあるうべき類型の発見、肯定文に変形できる原則と例外の整理、といったところまで、普通の要約筆記者にできる訳ではない。日本語の専門家によるこうした仕事は、確かに行なわれてはいるが、私たちが毎日使っている日本語の豊かな表現と比べると、その研究はきわめて限定的なものだ。日本語は、他の多くの言語同様、文法(言語の運用規則)の決定や語彙の選定が先にあって、それに基づいて運用されている言語ではない。私たち日本人が、おそらく何千年も昔から自然に使い始め、様々な外来の文化と共に受け入れた言葉を消化しつつ、日本の社会のあり方を反映させて、分化と統合を繰り返しながら作り上げられてきた言語、すなわち自然言語の一つだ。したがって、ある言葉の運用が正しいかどうか、同じ意味を伝える別の、より短い表現はどうのようなものか、という問いに直ちに答えることは、日本語の研究者にとってもきわめて難しい。研究されている領域は決して広くはない。しかも、そのほとんどは、書きことばを対象としており、話しことばに対して行なわれた研究というものはほとんどない。
このため、他人に伝達することを目的として話しことばを書きとる際、日本語のどのような性質が利用できるのか、という点について、要約筆記者はほとんど徒手空拳だったと言わざるを得ない。自然言語としての日本語は、そのとき巨大な壁となって、要約筆記者の前にあった。

以上の3つが、要約筆記を通訳として機能させることに対して、これを阻害する要因として働いてきたのではないか、私は、現時点ではそんなふうに整理している。もちろんこれ以外の理由もあったかも知れない。が、主な理由は、この3つではなかっただろうか。
一つは、要約筆記が日本語間のやりとりを媒介しているために、通訳としての側面が見にくかったということ。もう一つは、要約筆記を利用する中途失聴・難聴者の要望。そして最後が、要約筆記者自身が、話し言葉の速さにどうしても目を奪われて、他人の話を媒介するという作業の本質に対して十分に迫れなかったこと、だ。順を追って説明したい。
[1]日本語間のやりとりである、ということ
まず要約筆記が日本語間のやりとりを媒介するから、という点だが、これは異言語間の通訳と比較するとわかりやすい。もともと異言語間通訳は、いわゆる逐語訳ではつとまらない。このことは異なる二つ以上の言語を少し扱った経験のある人ならすぐに了解される。分からない単語のすべてについて辞書を引いて、単語の意味が分かったとしても、文を正しく訳すことはできない。まして達意の言葉にして通訳することはできない。
例として、言語学者の鈴木孝夫氏がその著書「日本語と外国語」(岩波新書)で挙げたフランス語における「オレンジ色の封筒」という表現を取り上げてみよう。鈴木孝夫氏は、この表現に接して、あるとき、フランス人にとって「オレンジ」という色は、我々日本人にとっての「茶色」を含むのだと気づく。つまり「オレンジ色の封筒」とは「茶封筒」のことだったのだ。日本では虹は七色だが、世界中で虹を七色と数えている国は少ない。ヨーロッパでは、「リンゴのような頬の女の子」とは青白い病弱なイメージを喚起する。したがって、異言語間の翻訳や通訳は、言葉に沿って訳す逐語訳ではなく、話し手が言おうとしたことを理解して伝えるという作業が絶対に必要になる。言葉のままに訳したのでは、意味が伝わらず、場合によっては誤解や行き違いを生じるからだ。実際、「オレンジ色の車でお迎えに参ります」と言われた鈴木孝夫氏は、いつまでたったも現われないオレンジ色の車を、茶色の車の傍らで待ち続けたという。異言語間の通訳は、こうした文化的な読み替え、言い替えの上に成り立っている。「言い替え」と書いたが、それは「替える」のではなく、本当は、話し手が伝えたいと願ったことを、通訳者が理解し、理解したものを、聞き手(読み手)が使う言語の世界で表現する行為なのだ。
これに対して、要約筆記は同じ日本語間で話を媒介するものだ。話し手が、頬の紅い健康的な女の子をイメージして「リンゴのような頬の女の子」と言えば、聞き手にも同じイメージが喚起されると期待することができる。話し手が「オレンジ色の車」と言えば、確かにオレンジ色の車がお迎えに来るだろう。であれば、話し手の言葉をそのまま使えばよい、話し手の言葉と異なる言葉を使うべきではない、と要約筆記者が考えたとして不思議はない。話し手の言葉をできるだけ生かして話を伝えるとは、この間の消息を伝えるものだ。

[2]要約筆記を利用する人の要望
第二の理由、要約筆記を利用する中途失聴者・難聴者の要望はどうだろうか。これには更に二つの側面がある、と私は考えている。一つは、音から隔てられた中途失聴者・難聴者の心情、もう一つは、話し手としての中途失聴者・難聴者の心情、だ。中途失聴者は、人生の途中で聴力を失ったから、それまでは音声が聞こえていたことになる。したがって、音は最初から失われていた訳ではなく、音はあり、そこから隔てられていると感じているのではないだろうか。難聴者の受けとめ方も似ているのでないだろうか。1975年に岩波新書の一冊として発行された「音から隔てられて」(編集・入谷仙介、林瓢介)という書籍の書名は、この中途失聴者・難聴者の心情を端的に表わしていると、と私は感じてきた。中途失聴者・難聴者にとって、隔てられている音声を回復したい、という要望は当然のことだ。補聴器が、隔てられている音声を、音声のまま少しでも取り戻そうとする装置である考えられるとすれば、音声を文字化することで、これを取り戻そうという利用の仕方を要約筆記に求めるということがあったのではないか。聞き取りにくい言葉を時に補聴器が明確にするように、聞き取りにくい言葉を要約筆記のスクリーンに求めて明確にしようする、そういう利用の立場から言えば、話し手の使った言葉はそのままスクリーンに現われて欲しいはずだ。
もう一つ、話し手もまた中途失聴者・難聴者だったとはどういうことだろうか。要約筆記が当初使われた場面は、中途失聴者・難聴者の会合、例えば典型的には、中途失聴者難聴者協会の例会などだった。そうすると要約筆記の利用者は、同時に、要約筆記における話し手でもあったのだ。したがって、要約筆記の現場では、話し手も中途失聴・難聴者、それを見ているのも中途失聴・難聴者だった。話し手からすれば、自分の使った言葉が使われない、というのは不満になる。話し手には、その言葉を使って物事を伝えたいという気持ちがある。その気持ちがあるからその言葉が選択されたのだといえる。例えば、相手に対して十分な気遣いをして、「あまりお引き留めして、後のご予定に差し支えては、と心配しておりますが」と話したとき、要約筆記の画面に例えば「退席されては?」と書かれると、「自分はこんな言い方はしなかった、こんな直接的な言い方では失礼に当たらないか」と感じてしまう、ということは、話すことに対して意識的な話し手であればあるほど、起きるはずだ。自分の話したままに書いて欲しい、と話し手である中途失聴者・難聴者が感じ、そのように要望したとしても不思議ではない。
要約筆記者は、聴覚障害者、とりわけ中途失聴者・難聴者を支援しようという気持ちで活動をしている立場だから、中途失聴者・難聴者の要望に耳を傾け、その要望を尊重したいと考えるだろう。「音から隔てられて」いる気持ちに立って、音声それ自体を取り戻したいという要望、話し手である中途失聴・難聴者の、言葉に託した自らの心情をそのまま伝えるために、託した言葉自体を書いて欲しいという要望、要約筆記者は、それらに応えようとしてきたのだと言える。それが、話し手の話の内容を伝える、つまり通訳としての要約筆記ではなく、話し手の言葉を生かした要約筆記という目標を掲げる理由につながったのではなかったか。
[3]話しことばと書きことばの速さのギャップの前で
最後に、話しことばと書きことばの速さの違いという問題がある。一般に話しことばの速度は1分間に300字程度とされ、他方、手書きの速度は1分間にせいぜ60字程度だとされる。書き取ることができる文字数は話しことばの約20パーセントでしかない。私たち要約筆記者はその速度のあまりに大きな違いの前で、どのようにこの差異を乗り越えるかという点について、十分な検討ができなかったように私は思う。もちろん、全要研集会では毎年のように「技術」の分科会がもたれ、その主要なテーマは「要約」の技術であり、研究誌にも要約をめぐるたくさんの論考が掲載されてきた。はやく1994年発行の研究誌第5号、翌年の第6号には、ユニークな要約の技術的な考察が掲載されている。しかし、それらの研究が、その後の要約筆記における要約の研究の発展には、うまく結びつかなかった。それはなぜか。
思うに、私たち要約筆記者は、話しことばと十分な格闘をしなかったのだ。要約筆記者、当時の要約筆記奉仕員は、一般の人がボランティアである奉仕員の養成講座を受けることで養成される。当然、日本語の研究者ではないから、「要約」について関心をもっても、なかなか実証的な検討をするところまで至らない。いわゆる素人の思いつきの域をでることが難しいのだ。
日本語の普通の使い手として、日本語に関してものを言うことは難しくない。例えば、「○○しないこともない。」という二重否定文に出会えば、これを「○○する。」と言い得る、ということは気づくだろう。しかし、日本語の中で二重否定文が使われる理由、その場合のあるうべき類型の発見、肯定文に変形できる原則と例外の整理、といったところまで、普通の要約筆記者にできる訳ではない。日本語の専門家によるこうした仕事は、確かに行なわれてはいるが、私たちが毎日使っている日本語の豊かな表現と比べると、その研究はきわめて限定的なものだ。日本語は、他の多くの言語同様、文法(言語の運用規則)の決定や語彙の選定が先にあって、それに基づいて運用されている言語ではない。私たち日本人が、おそらく何千年も昔から自然に使い始め、様々な外来の文化と共に受け入れた言葉を消化しつつ、日本の社会のあり方を反映させて、分化と統合を繰り返しながら作り上げられてきた言語、すなわち自然言語の一つだ。したがって、ある言葉の運用が正しいかどうか、同じ意味を伝える別の、より短い表現はどうのようなものか、という問いに直ちに答えることは、日本語の研究者にとってもきわめて難しい。研究されている領域は決して広くはない。しかも、そのほとんどは、書きことばを対象としており、話しことばに対して行なわれた研究というものはほとんどない。
このため、他人に伝達することを目的として話しことばを書きとる際、日本語のどのような性質が利用できるのか、という点について、要約筆記者はほとんど徒手空拳だったと言わざるを得ない。自然言語としての日本語は、そのとき巨大な壁となって、要約筆記者の前にあった。

以上の3つが、要約筆記を通訳として機能させることに対して、これを阻害する要因として働いてきたのではないか、私は、現時点ではそんなふうに整理している。もちろんこれ以外の理由もあったかも知れない。が、主な理由は、この3つではなかっただろうか。

